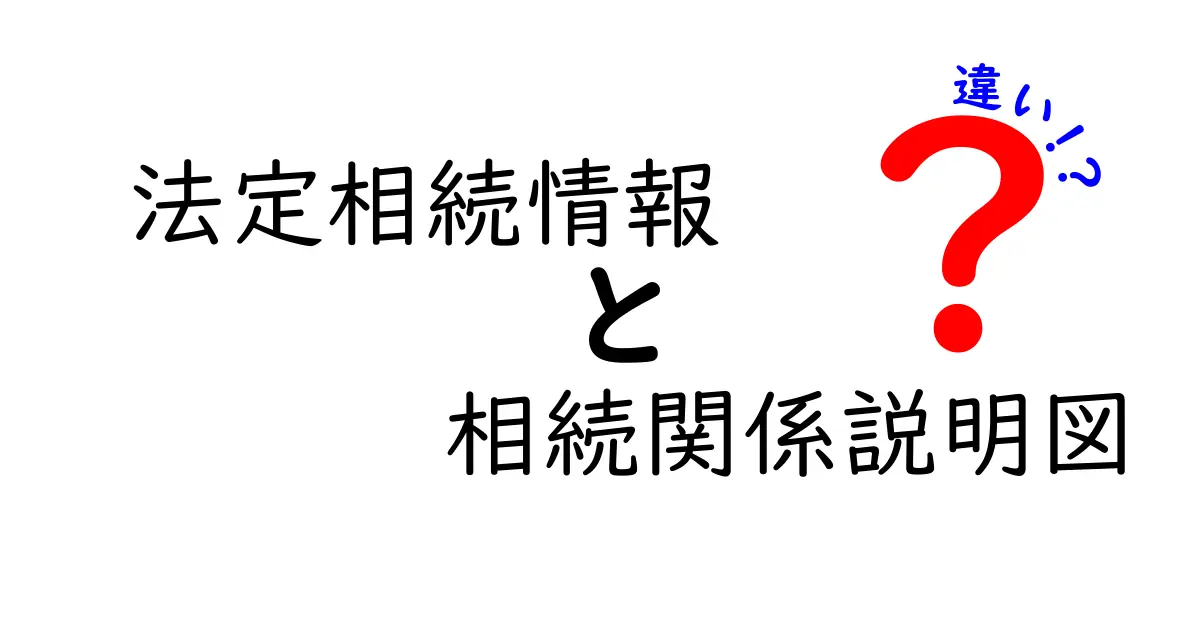

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
法定相続情報とは何か?基本をしっかり理解しよう
法定相続情報とは、亡くなった人の相続がどのように行われるかを示す公的な情報です。法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を指し、これを使うことで相続手続きがスムーズになります。
この情報は、相続人の名前や続柄、亡くなった人との関係性などが一覧表の形でまとめられています。複数の金融機関や行政機関への相続手続きを行う際に、一度法定相続情報を提出すれば、他の機関に再度同じ資料を出す必要がなくなります。
これにより手続きの簡略化や時間短縮が期待できるのが大きなメリットです。また、紙媒体での証明書として活用できるので、金融機関での相続預金の解約などにも利用されます。
この法定相続情報は、申請者(通常は被相続人の相続人)が出生から現在までの戸籍謄本を提出し、法務局でまとめてもらう形になります。
相続関係説明図とはどんなものか?見やすさがポイント
相続関係説明図は、相続人の関係性をわかりやすく図で表したものです。「誰が亡くなった人の子どもで誰が孫か」など血のつながりを視覚的に示せるのが特徴です。
一般的には専門家(司法書士や弁護士)が相続関係の説明を依頼された際に作成します。相続手続きや遺産分割協議の際に分かりやすい説明資料として役立つため、相続人間の誤解やトラブルを避ける手助けにもなります。
図の形式は様々ですが、家系図に似た形が多く、名前・続柄・生年月日が記載されていることが一般的です。また、死亡した人の関係性が色分けされたり線で繋がれていたりして、一目で関係性が把握できます。
法定相続情報と相続関係説明図の違いを比較表で確認
ここまで説明した二つの資料ですが、以下の表で違いを明確にまとめました。
| ポイント | 法定相続情報 | 相続関係説明図 |
|---|---|---|
| 発行元・作成者 | 法務局(公的機関) | 司法書士や専門家、又は自身で作成 |
| 目的 | 相続手続きの簡素化、証明 | 相続人の関係説明、理解促進 |
| 形式 | 一覧表形式の公的書類 | 図(家系図形式が多い) |
| 使う場面 | 金融機関や役所の手続き | 遺産分割協議や説明時 |
| 必要性 | 法的手続きに公式に認められる | 法律上の強制力は基本なし |
このように用途や作成方法、活用場所が異なるため、両方を理解し適切に使い分けることが大切です。
まとめ:正しい書類選びで相続手続きをスムーズに
相続の手続きは複雑でわかりにくいため、法定相続情報と相続関係説明図の違いをしっかり押さえておくことは非常に重要です。
法定相続情報は公的な証明書としての役割があり、多くの手続きで必須になります。一方、相続関係説明図はわかりやすく関係性を示すための道具として補助的に使われます。
どちらも間違えずに準備し、相続人同士や関係機関とのトラブルを防ぎましょう。
また、専門家への相談も有効ですので、必要に応じて利用を検討してください。
最後に、図と一覧をうまく活用して、相続手続きを円滑かつ安心して進めてください。
法定相続情報の申請には、戸籍謄本の提出が不可欠ですが、実はここに意外な落とし穴があります。戸籍は婚姻や死亡によって複数に分かれている場合も多く、すべて集めるのに時間がかかることもあります。加えて、昔の戸籍は手書きで読みづらいことも…。こうした事実は知られていないため、申請する際は余裕を持って戸籍の準備を始めるのが賢明です。ちょっとした雑談ですが、法定相続情報のスムーズな発行には「戸籍マラソン」とも呼ばれる準備作業が必要なんて、面白いですね。
次の記事: 法定相続情報と法定相続情報一覧図の違いとは?わかりやすく解説! »





















