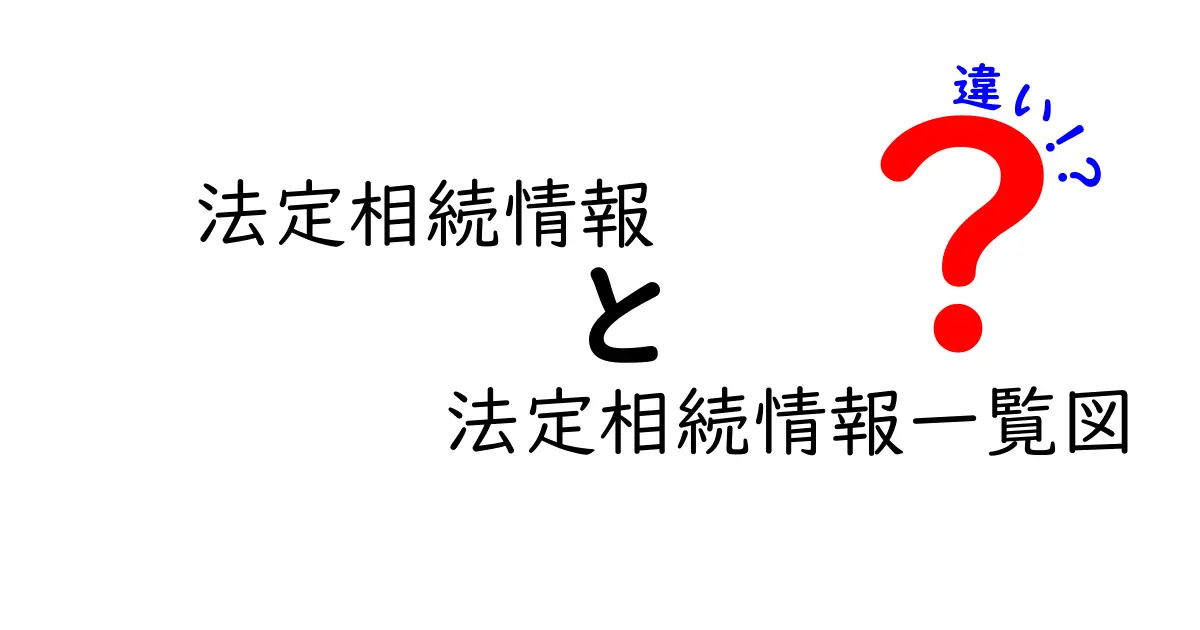

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
法定相続情報と法定相続情報一覧図の基本的な違い
相続に関する手続きをするとき、『法定相続情報』と『法定相続情報一覧図』という言葉を聞くことがあります。この二つは似ているようで実は意味や役割が少し違います。
まず、法定相続情報とは、亡くなった人の相続人が誰であるかを証明するための情報のことを指しています。これは戸籍などの書類をもとに、相続関係をまとめたものです。
一方、法定相続情報一覧図は、その情報を図でわかりやすく表したものです。つまり、相続人の名前や続柄を一覧形式で示し、内容を一目で理解しやすくした書類です。
このように違いをまとめると、情報の内容そのものと、それをわかりやすく図で表したものという関係になります。
この違いを理解することは、相続手続き時にどの書類を用意すればよいかを知るうえで非常に重要です。また、役所や銀行などへの提出時にも混同しないように気をつけましょう。
法定相続情報と一覧図の利用目的と作成方法の違い
法定相続情報は、相続が発生したときに誰が相続人であるかを示す重要な情報で、戸籍謄本や除籍謄本などを集めてまとめます。
これに対して、法定相続情報一覧図は、行政機関に提出して証明書として発行される図面です。これを使うと、各種相続手続きがスムーズになる便利な書類となります。
作成方法も異なっていて、法定相続情報は自分たちで戸籍などを確認して整理する作業ですが、法定相続情報一覧図は法務局に提出して認証を受けることで公式の証明書として発行されます。
また、一覧図は法定相続情報をわかりやすい形式にしているため、窓口での説明や書類提出時に大変役立ちます。
まとめると、情報を整理し認証を受けるかどうかと、その見やすさや利便性が主な違いとなります。
法定相続情報と法定相続情報一覧図の違いを表で比較
| 項目 | 法定相続情報 | 法定相続情報一覧図 |
|---|---|---|
| 意味 | 相続人の情報をまとめたもの | まとめた情報を図にした書類 |
| 作成者 | 相続人(本人や代理人) | 法務局が認証して発行 |
| 提出先 | 主に自分または関係機関 | 行政機関や金融機関など複数の提出先 |
| 利用目的 | 相続人の証明準備 | 相続手続きをスムーズにするための公式書類 |
| 発行手続き | 自分で手元に用意する | 法務局に提出し発行を受ける |
これから相続手続きを控えている人は、まず法定相続情報を準備し、そこから法務局に法定相続情報一覧図の交付申請を行うと便利です。うまく利用して手続きを簡単にしましょう。
法定相続情報一覧図について、実は名前が少し長くて難しそうに感じるかもしれません。でも、この書類は相続人同士の関係がパッと見てわかる便利な図なんです。法務局が認証して発行してくれるので、銀行や役所に何度も戸籍を持って行く手間が減ります。こうした仕組みは、相続の複雑なやりとりをぐっと簡単にしてくれるので、知らないと損をするかもしれませんね。
次の記事: 借地人と借地権者の違いとは?わかりやすく解説! »





















