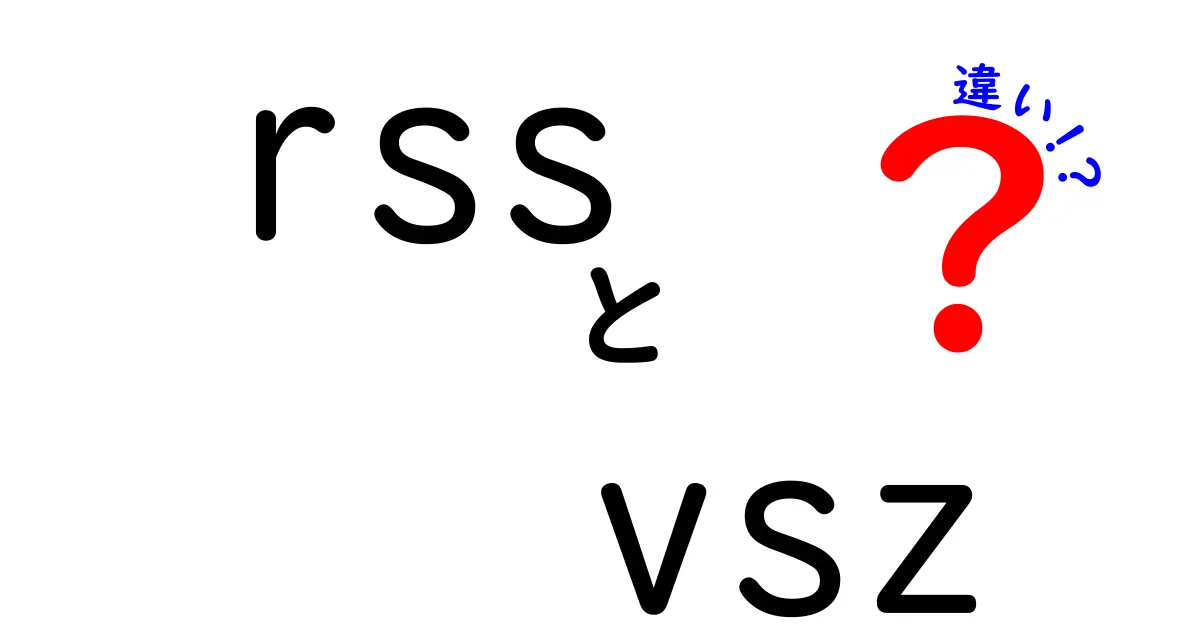

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
RSSとVSZの違いを正しく理解するための基礎知識
このガイドは、RSSとVSZの違いを、初心者にもわかるように丁寧に解説します。メモリの話は難しく感じることが多いですが、日常のスマホやPCの動作を思い浮かべれば理解が深まります。まずは両者の根本的な意味を押さえ、それから使い分けのポイントへ。
本記事を読めば、なぜ同じアプリでもプロセスごとにメモリ表示が違うのか、どうして VSZ が大きくても危険ではないケースとそうでないケースがあるのかが、スッと理解できます。
この解説の要点は「実際にRAMに載っている量か」「仮想アドレス空間として確保した総容量か」という二軸で見ていくことです。
続いて、各指標の意味を順番に深掘りしていきます。まずは代表的な用語である RSS について押さえましょう。RSS は「実際にRAMに存在しているページのサイズ」を指します。実務ではこの値を見て現在どれだけのRAMを実際に使っているのかを判断します。なお、同じデータを複数のプロセスが共有する場合、RSS はその分だけ“重複して”カウントされることがある点に注意してください。つまり、RSS が大きいからといって必ずしも全体のRAM消費量を正確に表すわけではない、という現実があります。
続いて、VSZ の説明です。VSZ は「仮想アドレス空間として確保した総容量」を指します。これは実際にRAMに載っているかどうかに関係なく、コード・データ・ヒープ・スタック・メモリマップドファイルなどを含んだ総容量です。
したがって VSZ が大きいからといって必ずしも現在のメモリ不足を意味するわけではありません。仮想アドレス空間が大きくても、実際には一部が未使用だったり、後で解放されたりすることがあるからです。
RSSとVSZをどう使い分けるか。実務での使い分けの基本は、現状のRAM使用量を知りたい時は RSS を、潜在的なメモリの余地を見たい時は VSZ を見る、という二段構えです。
また、複数のプロセスが同じライブラリを共有している場合、RSS の総和が実際のRAM総量より大きく見えることがあり、個別のRSSだけを足して全体を判断しないことが重要です。さらに、pmap や smem、ps, top の表示を組み合わせると、どの部分が大きく占有しているかが分かりやすくなります。
ここで覚えておくポイントは「RSS は今現在の現実的な使用量」「VSZ はアプリが将来使える最大容量の目安」という二軸です。
友達とパソコンの話をしていたある日、VSZ の話題で盛り上がった。彼は VSZ が大きいと安心だと思っていたけれど、実は RAM に載る実量は RSS が決めることが多いと教えると、彼は「なるほど、仮想空間だけ大きくても意味がないのか」と納得した。私たちは同じライブラリを使う場面で RSS の合計が膨らむ現象にも触れ、共有メモリの仕組みを思わず紙にメモしてしまった。やがて彼は「メモリは箱ではなく現実の動きだ」という結論を共有してくれ、私たちは笑いながら帰路についた。





















