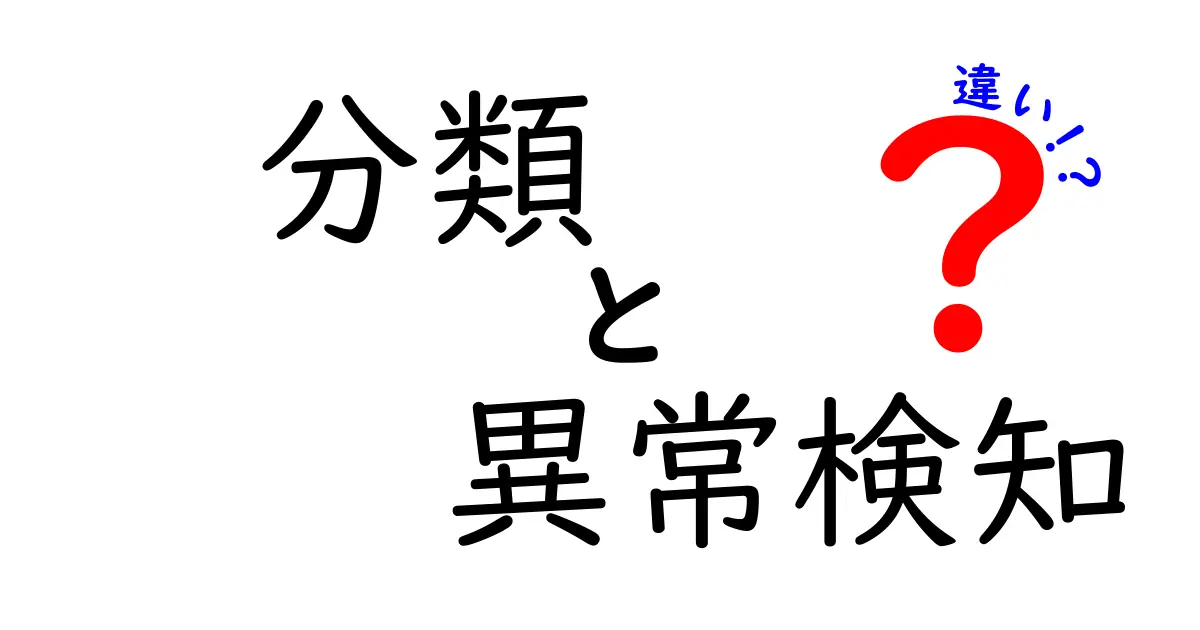

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
分類とは何か?わかりやすく解説
まずは分類について説明しましょう。分類とは、データやものを決められたカテゴリーに分けることです。例えば、リンゴとみかんを見分けてそれぞれのグループに分けることが分類のイメージです。
機械学習の世界では、分類はパターン認識の一つで、データを学習させて何の種類に属するのかを予測します。例えばメールが「スパム」か「重要」メールかを自動で判別するのは分類の代表的な使い方です。
分類は過去のデータをもとに、ラベル(種別)が決まっているものに区分けをするという特徴があります。
簡単に言うと、「これは猫」「これは犬」という風に、あらかじめ決まったグループにデータを振り分けるのが分類です。
異常検知とは?分類とどう違うのか?
続いて異常検知について説明します。異常検知は、日常の状態から外れた「おかしな状態」や「珍しいパターン」を見つける技術です。普段のデータとは違う、不自然なデータを見つけ出すために使われます。
例えば、銀行の取引でいきなり大きな金額が急に動くなど、通常の行動から外れている場合を見つけられます。これが異常検知の役割です。
分類と異なり、異常検知では異常のラベルがあらかじめ決まっていない場合が多いので、「正常データだけを学習して正常から外れたものを異常と判断する」という特徴があります。
つまり、何が異常か分からなくても、普段の正常な状態との違いを見つけて警告するのが異常検知なのです。
分類と異常検知の比較一覧表
まとめ:分類と異常検知は目的も手法も違う
分類と異常検知は似ているようで大きく異なる技術です。分類は既に決まったグループに分けること。一方で異常検知は通常と変わったものを見つけ出すことです。
データの性質や問題の設定によってどちらを使うかが決まります。
これらの基本を知ることで、AIやデータ分析の仕組みがより身近に感じられることでしょう。
ぜひ機械学習やデータ分析に興味がある方は、まず分類と異常検知の違いをしっかり理解して使い分けてみてくださいね。
分類という言葉を聞くと、「ただグループ分けするだけ」と思いがちですが、実はとても奥が深いんです。例えば、機械学習の分類は過去のデータに基づいて未来のデータを予測する力を持ちます。でも、そのとき使う特徴量の選び方で結果が大きく変わることも。だから、良い分類を行うためには、表面的なラベルだけでなく、データの性質を深く理解することが大切なんですよ。意外と奥深い分類の世界、じっくり向き合ってみると面白い発見があります!
次の記事: 売掛帳と売掛金元帳の違いとは?初心者でも簡単にわかる会計用語解説 »





















