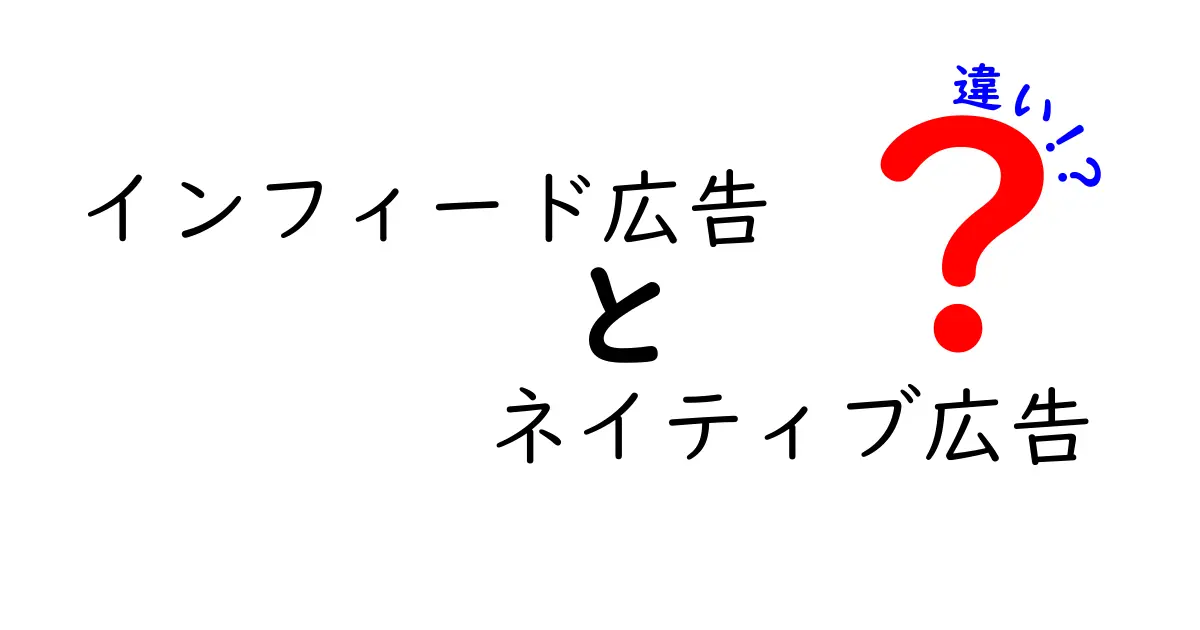

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インフィード広告とネイティブ広告の違いを徹底解説—仕組みから使い分けまで完全ガイド
この二つの用語は広告業界でよく混同されがちですが、実際には狙い方や見せ方、規制の扱いが異なります。まずインフィード広告はニュースフィードやタイムラインの流れに自然に入り込み、ユーザーが情報を閲覧しているときの体験を大きく崩さないよう設計されています。
これはプラットフォームが提供するアルゴリズムと連携して、関心が高そうなユーザーに表示されやすくする仕組みです。
一方、ネイティブ広告は媒体のデザインと合うように文章のトーン・写真・動画のスタイルを合わせ、「広告だと気づかせない」のではなく「広告であることを適切に開示しつつ、読み物としての品質を高める」ことを目指します。
この違いを知ると、広告主がどんな目的を持っているのか、またメディアがどのようなルールを適用しているのかが見えやすくなります。たとえばブランド認知を広げたい場合はネイティブ広告の方が自然さと信頼感を作りやすいです。
一方で、商品やサービスの導入を短期間で促進したいときにはインフィード広告の方が決定の機会を作りやすい場面が多いです。
そもそも広告の“定義”と“使われ方”の違い
インフィード広告とネイティブ広告は広告の定義の観点で区別され、使用される場面も異なります。インフィード広告は情報の流れの一部として配置され、クリック後の遷移はメディアの信頼度に依存します。ネイティブ広告は媒体の編集方針に合わせて作られ、読み物としての一体感を重視します。
この差は、広告の透明性とユーザー体験のバランスをどう取るかという設計の問題にもつながります。
また、規制の観点からも表現の違いが重要です。日本の広告表示規準では、広告であることの開示が求められるケースが増えています。ネイティブ広告は開示表現の設計が難しく、読み手に違和感を与えないようにしつつ、広告の意図を明確に伝えるバランスが求められます。
実務での使い分けと注意点
実務では、媒体特性とターゲットの行動パターンを分析して使い分けをします。若年層や新規ユーザーにはインフィード広告が効く場合が多く、ニュースメディアの購読動機が高い層にはネイティブ広告が馴染みやすいという傾向があります。
また、クリエイティブの作り方にも差が生まれます。インフィード広告は短く誘導的な文言やアイキャッチが有効なことが多いのに対し、ネイティブ広告は長めの解説入りの文章や、ストーリーテリング形式が相性が良いことがあります。
さらに成果の測定にも違いが現れます。クリック率だけを見るとインフィード広告は即効性が出やすい一方で、滞在時間・処理完了率・転換後のリマーケティングの効果を追うとネイティブ広告の方が良い場合があります。実務ではABテストを繰り返し、表示位置や文言・ビジュアル・開示の表現を最適化します。
注意点としては、過剰な誇張や誤解を招く表現、またプラットフォームごとの表示ルールを超えた配置は避けるべきです。特にネイティブ広告は媒体の信頼性に影響するため、透明性のある開示と品質の高いクリエイティブを両立させることが重要です。
比較表とポイント
この違いを踏まえたうえで、広告主と媒体の共同作業として、適切な開示・クリエイティブ・測定指標を選ぶことが重要です。
ねえ、実はネイティブ広告には広告という事実を完全に隠そうとするのではなく、読者の“体験”を壊さずに伝える技術が重要だと気づくんだ。たとえばニュース記事風の書き方を採用して、読み進めると広告だと気づく設計は避けられません。でもそれは“騙す”ことではなく“透明性を保ちつつ価値を届ける”という意図に近い。現場ではデザイン・コピー・開示の表現をABテストして、読みやすさと信頼性のバランスを探るのが基本の流れです。





















