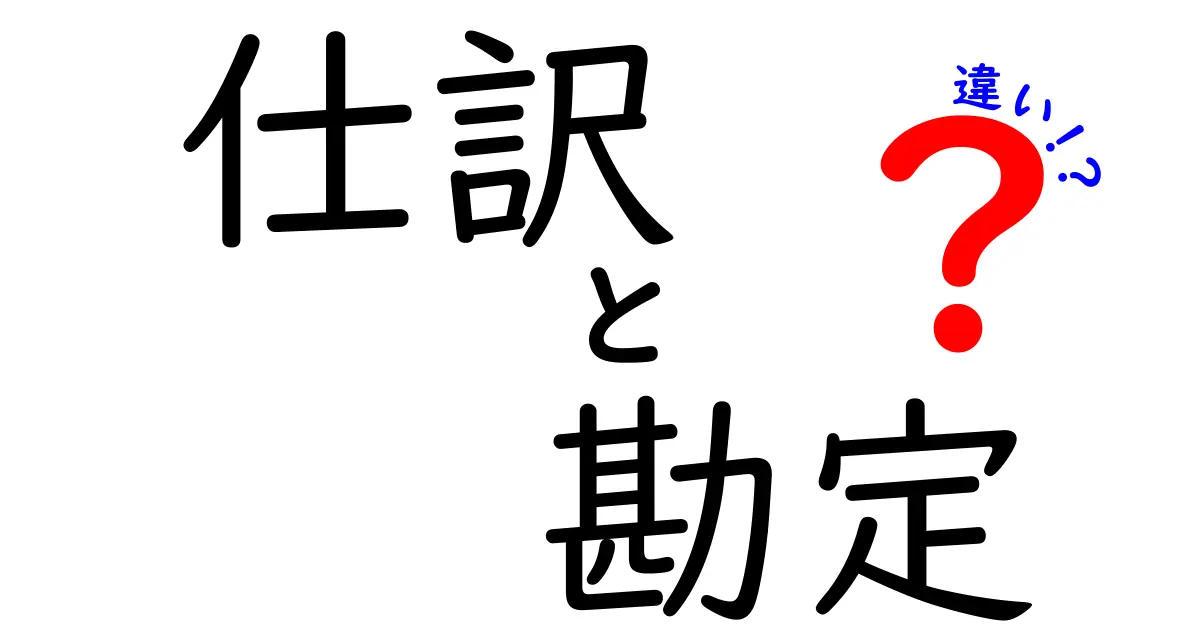

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仕訳と勘定の基本とは何か?
会計を勉強し始めると、よく聞く「仕訳(しわけ)」と「勘定(かんじょう)」という言葉。これらは似ているようで実は役割が違います。まずは、それぞれの意味を整理しましょう。
「仕訳」とは、お金の動きや取引を記録するために、どの勘定科目を借方(左側)に、どの勘定科目を貸方(右側)に記入するかを決める作業のことです。たとえば、お店が商品を現金で仕入れた場合、「仕入(借方)」と「現金(貸方)」という勘定を使って記録します。
一方、「勘定」とは、取引の内容を具体的に記録・分類するための科目です。例として「現金」「売上」「仕入」「交通費」などがあります。勘定はたくさんの取引を整理して合計したり、計算しやすくしたりするための枠組みです。
つまり、仕訳が取引を記録するためのルールや形だとすると、勘定はその取引内容を分類するための項目だということです。
仕訳と勘定の違いを理解するポイント
ここで仕訳と勘定の違いをわかりやすくまとめてみましょう。
| ポイント | 仕訳 | 勘定 |
|---|---|---|
| 役割 | 取引を記録するルールや形 | 取引を分類して管理する科目 |
| 例 | 仕入(借方)/現金(貸方) | 現金、売上、仕入、交通費、給料など |
| 使う場所 | 仕訳帳や会計ソフトの入力画面 | 勘定科目元帳や財務諸表で集計・報告 |
| 目的 | 正確に取引内容を記録する | 取引の内容を分類し集計を簡単にする |
このように仕訳は記録の方法そのもので、勘定はその材料となる科目です。
例えば、同じ「現金」という勘定科目も、仕訳では借方や貸方に記入することで「どのような取引か」がはっきりとわかります。
仕訳と勘定を実際に使う流れ
実際の会計の仕事では、まず取引があったら仕訳作業から始めます。
1. 取引内容を確認する(例えば商品の購入、売上、経費など)
2. どの勘定科目を借方と貸方に使うか決めて記録する
3. 仕訳帳に記入し、仕訳データを保存する
4. それらの仕訳を基にして勘定元帳で各勘定科目ごとに集計
5. 財務諸表などの報告書を作成する
仕訳は一つ一つの取引を正しく記録することが目的で、勘定は記録された取引を整理、分析しやすくするために使います。
この流れを理解すると、実務で迷わず会計処理がしやすくなります。
会計で使う「勘定」という言葉。実は漢字で「勘定」と書きますが、これは「計算」や「計る」という意味を持っています。昔から商売でお金を扱うときに計算することを指し、そこから「勘定科目」として取引を分類する名前がつきました。つまり、勘定は単なる名前ではなく、お金を管理するために古くから使われている伝統的な言葉なんですよ!
前の記事: « 会計年度と会計期間の違いとは?初心者でもわかる基本解説





















