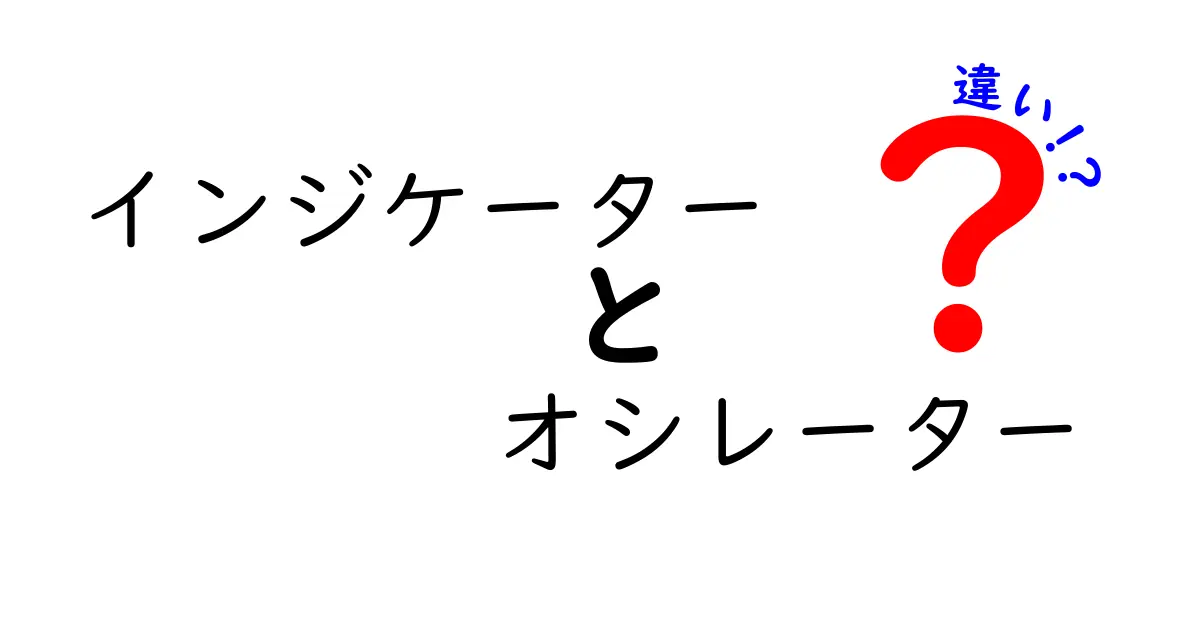

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インジケーターとオシレーターの基本的な違いとは?
株やFXなどのチャート分析でよく聞く「インジケーター」と「オシレーター」という言葉。どちらもテクニカル分析に使われる道具ですが、役割や特徴に違いがあります。まずはそれぞれが何を指しているのか、基本的な部分から確認しましょう。
インジケーターとは、価格の動きや取引量などのデータをもとに計算され、チャート上に表示される指標一般のことを指します。つまり、チャート分析に使える様々な数値や線のことです。
一方、オシレーターはそのインジケーターの中でも特に「特定の範囲内(たとえば0から100の間)」で上下に動き、買われすぎや売られすぎを教えてくれるものを指します。商品としてはRSIやストキャスティクスなどが有名です。
まとめると、インジケーターは幅広い指標の総称、オシレーターはそのうちトレンドの強さや過熱感を教える狭い範囲を動く種類ということになります。
インジケーターとオシレーターの使用例と特徴
インジケーターの中には、トレンド系といわれるものがあります。これは価格の方向性や勢いを示し、たとえば移動平均線(MA)が代表例です。移動平均線は過去の価格の平均を線で繋ぎ、現在の相場が上昇傾向か下降傾向かを教えてくれます。
一方、オシレーターは価格が今どのくらい買われすぎか売られすぎかを示すため、相場の反転タイミングを見つけるのに役立ちます。RSI(相対力指数)なら0から100の間を動き、70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎの目安となります。
重要なのは両者を組み合わせて使うことです。たとえば移動平均線でトレンドの方向を確認しつつ、RSIで行き過ぎた状態を見極めることで売買の判断精度が上がります。
以下の表に主なインジケーターとオシレーターの特徴をまとめました。
| 種類 | 例 | 役割 | 表示形式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| インジケーター(トレンド系) | 移動平均線(MA)、MACD | 相場の方向や勢いを示す | ラインチャート | わかりやすくトレンドを確認できる |
| オシレーター | RSI、ストキャスティクス、CCI | 買われすぎ・売られすぎを示し反転を予測 | 0-100などの一定範囲で上下動 | 相場の行き過ぎを教えてくれる |
オシレーターの中でもRSIはよく使われる指標ですが、実は相場の過熱感だけでなく、値動きの勢いの変化も見せてくれるんです。たとえばRSIが70を超えていても、その数値がさらに上がったり下がったりする動きで、勢いが鈍ったことを察知できるので、単に数値だけで判断せずチャート全体を見るのがコツなんですよ。こうした奥深さがオシレーターの面白いところですね。





















