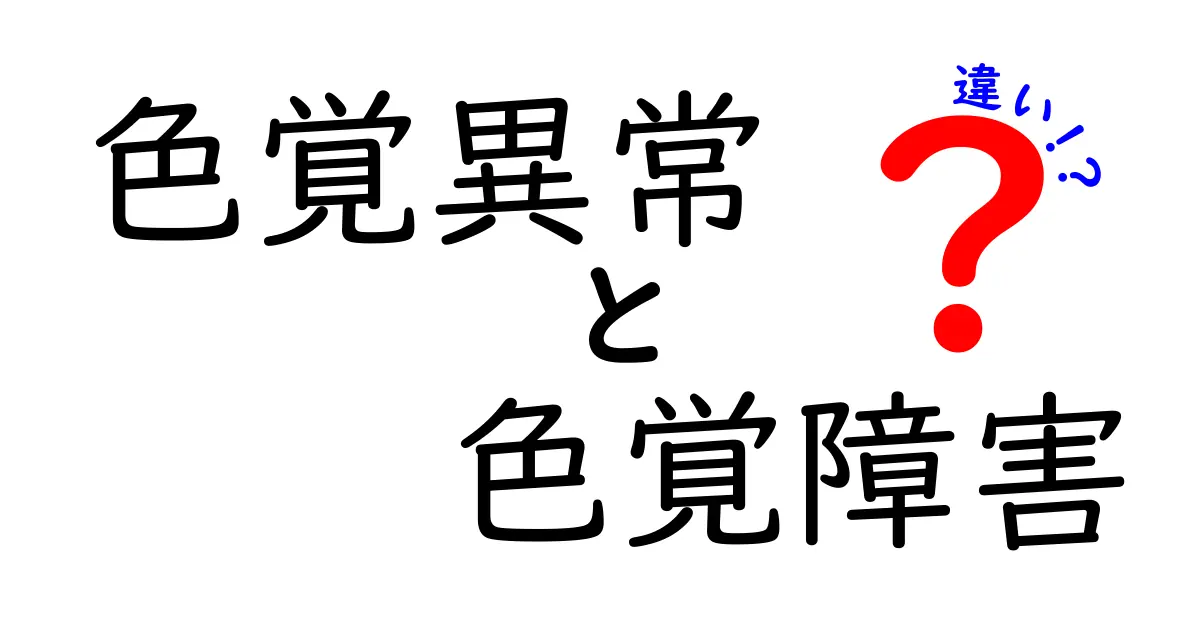

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
色覚異常と色覚障害の違いをご存知ですか?
色覚異常と色覚障害は似ている言葉ですが、実は意味や使われ方に違いがあります。
まずはそれぞれの言葉の基本的な意味を理解してみましょう。色覚異常は、色を感じる能力が一般の人とは異なる状態のことを指します。つまり、色の見え方に変化や偏りが生じている状態です。
一方、色覚障害は医療や福祉の分野でより重い意味を持ち、色をほとんど、または全く区別できない状態、つまり色を識別する力に重大な障害がある場合に使われます。つまり色覚異常は軽度から重度まで幅広く含まれ、色覚障害は特に重度や医学的診断を受けた状態を表す場合が多いのです。
この違いを理解することで、診断や対処法、日常生活での配慮の仕方が変わってきます。
<色覚異常と色覚障害の特徴を詳しく解説!>
色覚異常は色の見え方が一般的なパターンとは異なる状態全般を指します。例えば、赤と緑の区別がつきにくい「赤緑色覚異常」が代表的です。
色覚異常は遺伝によるものが多く、男性に多く見られます。日常生活で自覚がない場合も多く、例えば信号や標識の色が少しわかりにくいと感じる程度で済むこともあります。
一方で色覚障害は特に区別が難しいか、全く色が識別できない重度の状態を指します。医学的には検査によってはっきりと診断されることが多く、生活や仕事に支障をきたす場合もあります。色覚異常の中でも特に強い症状の人を色覚障害者として扱うケースがあります。
このように、色覚異常は広い概念で、そのなかに軽度~重度があり、重度のものが色覚障害として分類されることもあるのです。
色覚異常と色覚障害の違いをまとめた比較表
| 項目 | 色覚異常 | 色覚障害 |
|---|---|---|
| 意味 | 色が一般と異なる見え方をする状態全般 | 色を識別する能力に重度の障害がある状態 |
| 症状の幅 | 軽度~重度まで幅広い | 主に重度の症状 |
| 診断 | 自己申告や簡易検査でわかる場合も多い | 医療機関での検査・診断を受けることが多い |
| 影響 | 日常生活にあまり影響しないことも多い | 生活や仕事に支障が出ることがある |
| 法律や福祉 | 特に指定はないことが多い | 障害者手帳の対象などになることがある |
色覚異常・色覚障害の理解とサポートについて
色覚異常や色覚障害があると診断された場合、日常生活や職場での配慮が大切です。たとえば、色で判断が必要な場面での誤解を防ぐため、カラーユニバーサルデザインを取り入れた表示方法を使うことが推奨されています。
また、学校や職場での理解や、必要に応じた支援が受けられるよう、色覚異常と色覚障害の違いを正しく知ることも重要です。
医学的には色覚異常は治療が難しいとされていますが、日常生活を工夫し工夫することで快適に過ごすことが可能です。
色覚異常の人が使いやすいアプリや色覚特性に配慮した教育教材の開発も進んでいます。適切な理解と配慮があれば、誰もが暮らしやすい社会が作れます。
色覚異常について深く話すと、意外と自分も知らずに色覚異常の人と同じ悩みを持っていることがあります。たとえば、赤や緑のトーンが違うだけで区別がしにくいという経験はありませんか?それは軽度の色覚異常かもしれません。色覚異常は遺伝で決まることが多いですが、環境や加齢によって変わることもあるんですよ。だから、自分の色の見え方を友達と比べてみるのも面白いかもしれませんね!





















