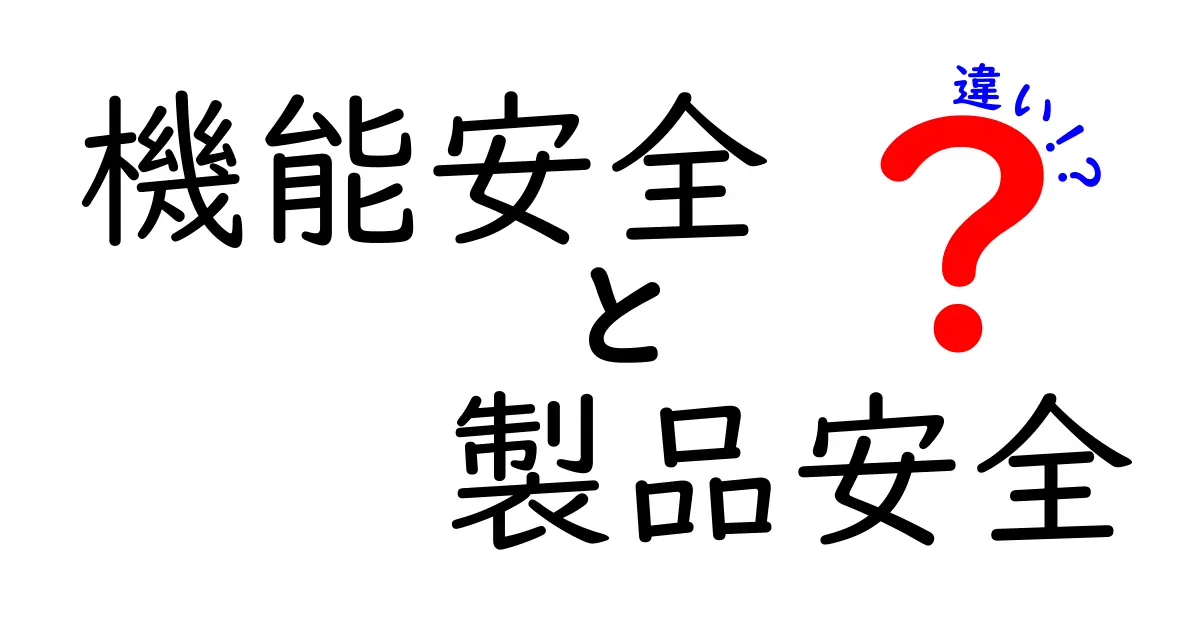

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
機能安全と製品安全って何?基本をわかりやすく説明します
まず機能安全と製品安全という言葉は、どちらも「安全」に関するものですが、意味や目的は少し違います。
機能安全とは、主に機械や装置、電子機器が故障や誤動作をした場合でも、人や環境に重大な危害を与えないように設計・管理することです。
例えば、自動車のブレーキが壊れそうになったときに、システムが自動で安全に停止する機能があれば、これが機能安全の一例です。
一方、製品安全は、製品そのものが使う人に対して安全であることを指します。つまり、製品に危険な部分がないか、説明書や警告表示が適切かなどを確認し、事故を防ぐことが目的です。
例えば、子どもが使うおもちゃに小さなパーツがあって誤飲の危険がないようにすることが製品安全の取り組みです。
このように、機能安全は故障時の安全確保にフォーカスし、製品安全は製品の全体的な安全性を確保するという違いがあります。
機能安全と製品安全の具体的な違いを表で整理してみよう
わかりやすく両者のポイントを表にまとめると以下のようになります。
| 項目 | 機能安全 | 製品安全 |
|---|---|---|
| 目的 | 故障や誤動作時の安全確保 | 製品使用時の全般的な安全性確保 |
| 対象 | 主に電子機器・機械装置のシステム | 製品全体(構造・表示・材料など含む) |
| 関係法規 | ISO 26262(自動車)、IEC 61508(汎用)など | 消費者製品安全法など国ごとの法律 |
| 評価方法 | リスクアセスメント・フォールトツリー解析など | 事故報告、基準適合検査、使用テスト |
| 例 | 車の自動ブレーキシステム | チャイルドロック付き子供用玩具 |
この表の通り、機能安全はシステムの『故障したとき』の安全を重視し、製品安全は使う人が安心して使える全体の安全性を守る認識で捉えると理解しやすいです。
なぜ機能安全と製品安全の理解が大切なのか?
現代の製品はますます複雑になっています。そのため、一つの事故が大きな被害をもたらすこともあります。
機能安全をしっかり考えることで、機械やシステムが故障しても事故が起きにくくなります。
一方、製品安全が守られていると、使う人が製品の危険を前もって理解し、安全に使えます。
両者をしっかり押さえることで、安心・安全なものづくりが可能になり、メーカーも信頼を得やすくなります。
たとえば、自動車メーカーがISO 26262という機能安全規格を守りつつ、製品安全の法律にも対応していることで、故障しても安全、かつ使う人が事故なく安心して使えます。
だからこそ、技術者や製品開発に関わる人は両方の違いを理解して、適切に対応することが求められているのです。
「機能安全」は、実は専門用語としてISOやIECという国際的な規格で定められています。特に自動車業界ではISO 26262が有名です。面白いのは、この規格ができる前は故障して事故になった例が多かったこと。だから新しい技術が安全に動作するかどうかを細かくチェックし、それが守られることで最終的に私たちの身の回りの安全が守られているんですよ。単なる製品の品質チェックよりも一歩踏み込んで、万が一の故障時にも安全を確保する仕組みなんです。これが機能安全が注目される理由の一つですね。





















