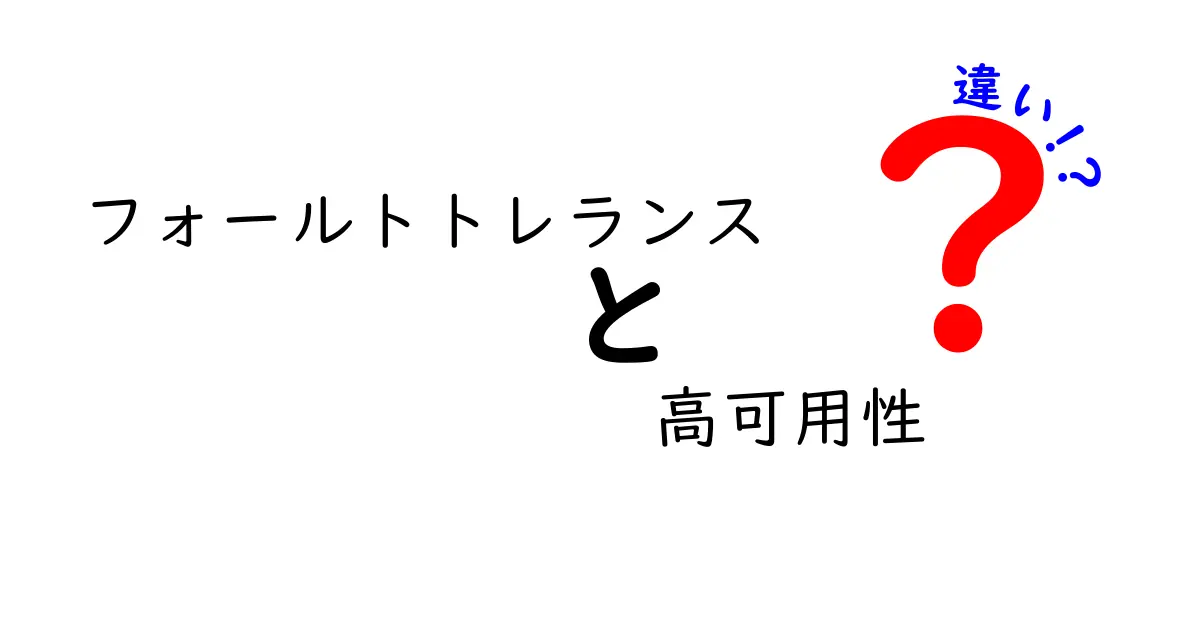

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
フォールトトレランスと高可用性の違いを徹底解説!まずは基本をおさえよう
フォールトトレランスと高可用性は、どちらもシステムを安定して動かすための設計思想ですが、狙いと手法が少し異なります。故障を前提とした設計と故障が起きても止まらせない設計、この二つをしっかり分けて理解することが大切です。日常生活の例えで言えば、学校の演劇部で道具が壊れても別の道具で代用できるかどうか、という視点がフォールトトレランスの考え方に近いです。逆に、演劇が本番で中断せず続くように、舞台裏の連携を自動化しておくのが高可用性の実務的な目的です。
本記事では、まずフォールトトレランスの仕組みを詳しく説明し、次に高可用性の考え方と実践を解説します。最後には、現場での使い分け方や、身近な例を通じて理解を深めます。読むあなたが、なぜこの二つが必要なのか、どの場面でどちらを選ぶべきかを実感できる内容を目指します。
1. フォールトトレランスとは何か
フォールトトレランス(fault tolerance)とは、部品の故障が発生しても、全体としての機能を失わずに動作を継続させる設計のことを指します。主な要素は冗長性の確保、自動検知と自動切替、そしてデータの整合性を保つ同期機構です。冗長性は同一機能を複数の部品に分散させることで、一つが壊れても別の部品が役割を引き継ぎます。自動検知と切替は、障害を人の手を介さずに素早く知らせ、別のノードへ処理を移す仕組みを可能にします。データの整合性を保つためには、複製されたデータの同期や排他制御、トランザクションの整合性を保証する設計が不可欠です。
この考え方を実現するには、設計段階から「故障を前提とする」発想と、障害時の手順を自動化するプログラムが必要です。つまり、冗長化と自動復旧の両方を組み合わせることが鍵といえます。実際の例としてはデータベースのレプリケーション、ストレージのミラーリング、電源の二重化、ネットワークの二重経路確認などがあります。これらを組み合わせることで、局所的な障害が全体の性能に影響を与えにくくなるのです。
ただしフォールトトレランスはコストと運用の複雑さが増えやすく、すべてのシステムで採用するのは現実的でない場合もあります。重要なのは、目的とコストのバランスを見極めることです。
2. 高可用性とは何か
高可用性(high availability)は、システムを「できるだけ長く停止させずに動かす」ことを狙う設計思想です。ここで重要なのは「停止時間を最小限に抑える」ことと、迅速な復旧・自動化・監視の組み合わせです。可用性を数値で表すとき、一般的には99.9%や99.99%、場合によっては99.999%といった目標が設定されます。これらの数値は、年間の停止時間を想定して評価され、どの程度の距離をとって停止を許容するかの指標になります。
高可用性を実現する具体的な手法には、ロードバランサーによるトラフィックの分散、クラスター化によるノード間の冗長、データベースのシャーディングとレプリケーション、バックアップとリストアの自動化、監視ツールによるアラートと自動切替などが挙げられます。
ここでのポイントは、人力介入を最小限に抑える運用設計と、計画的なメンテナンスを影響を最小化する方法の両立です。高可用性は、コストがかかる場合が多いですが、金融機関や医療、公共サービスのように「止まると大きな損害が発生する」場面では特に重要になります。実務では、目的の機能と影響度、投資対効果を天秤にかけ、優先度の高い機能から段階的に高可用性を追求していくのが一般的です。
3. 二つの違いをどう使い分けるか
フォールトトレランスと高可用性は、似ているようで目的が異なるため、使い分けが重要になります。観点別の違いを整理すると、以下のようになります。
- 目的:フォールトトレランスは障害を起こさせない設計を重視。一方、高可用性は障害が起きても影響を最小限に抑えて停止を許さないことを重視。
- 時間軸:フォールトトレランスは瞬時の切替と自動回復が中心。高可用性は計画的なメンテナンスと復旧手順を含む、長期的な連続運用を目指します。
- コストと運用:フォールトトレランスは冗長化の度合いが高くなるため初期コストと運用負荷が大きくなる傾向。高可用性は運用の自動化と監視の強化で効果を出しやすく、段階的な実装が可能です。
- 適用分野:金融や医療のように“停止が許されない”領域ではフォールトトレランスと高可用性の両方を組み合わせるケースが多いです。一般的なウェブサービスでは、運用コストと可用性のバランスを取りつつ高可用性を優先する場面が多いです。
このような違いを理解すると、実際のシステム設計で「どこまでの冗長性を持たせるか」「どう自動化して停止を減らすか」が見えてきます。目的に合わせて段階的に導入するのが鍵です。
4. 実世界の例と用語解説
現場での具体例を見てみましょう。例1はウェブアプリのバックエンドです。フォールトトレランスを高めるには、データベースを複数のノードで動かし、処理を分散させます。障害が発生しても別のノードが直ちに代替し、ユーザーにはほとんど影響がありません。例2はクラウドサービスの運用です。高可用性を追求するために、複数のアベイラビリティゾーンにまたがる展開、自動スケーリング、監視とアラートの自動化を組み合わせます。
どちらを選ぶべきかは、サービスが止まるとどれだけの被害が出るか、コストはどれくらい出せるか、そして復旧に要する時間はどれくらいか—この三つの要素で判断します。結論としては、「止まらせないこと」を重点に置くなら高可用性を中心に、さらに停止が許されない場面にはフォールトトレランスの考え方を組み込むのが現実的なやり方です。
5. まとめと実践のヒント
この記事の要点は、フォールトトレランスと高可用性は別々の設計思想であるが、相互補完的に使うことでシステム全体の信頼性を高められるという点です。目的とコストを明確に分けて考え、段階的に実装することが実務のコツです。まずは重要度の高い機能から高可用性を導入し、続いてフォールトトレランスの要素を追加していくと、安定性とコストのバランスが取りやすくなります。技術的な用語に惑わされず、現場の実運用とビジネスの要件に合わせて設計を進めてください。
表: 観点別の比較
友だちと話すように、フォールトトレランスの話をします。たとえば部活の道具が壊れても、別の道具や仲間がその役割をすぐ引き継ぐ――そんな“失敗を想定して備える”考え方がフォールトトレランスです。僕らは日常でも、データが消えないように複製をとっておく、電源を二重化して停電に備えるといった具体的な工夫をしています。実際には、故障を感知して自動的に切り替える仕組みと、データの整合性を保つ仕組みを組み合わせて動かしています。これが現代のシステム設計の基本だと感じます。
次の記事: アラームと時報の違いを徹底解説!毎朝の準備が変わる使い分けガイド »





















