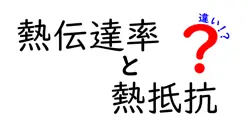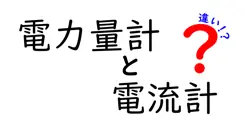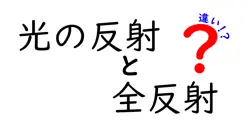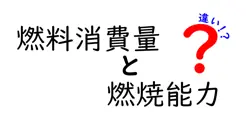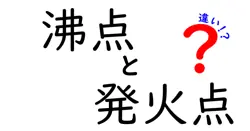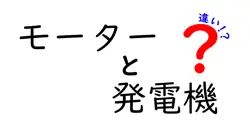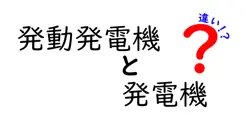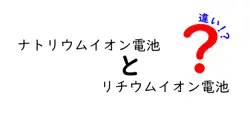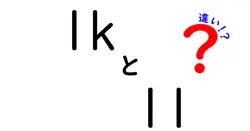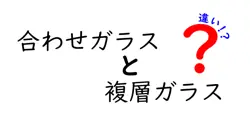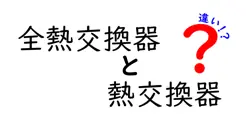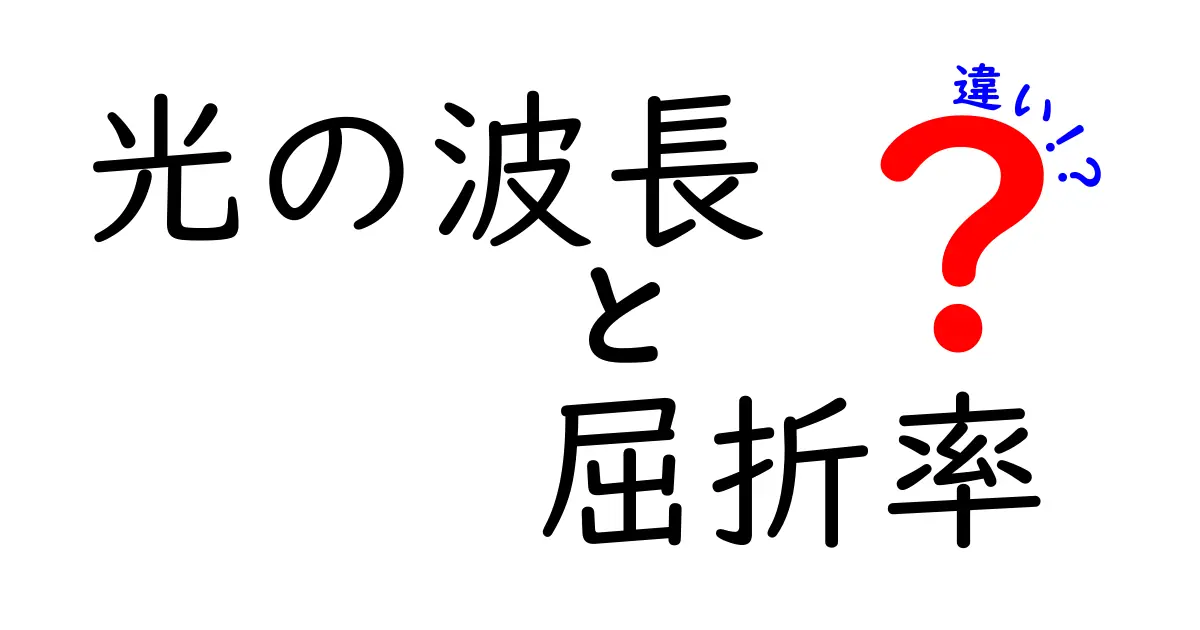
光の波長とは何か?
光の波長は、光が1回波の形を繰り返す距離のことを指します。これは光の波の長さを意味し、通常はナノメートル(nm)という単位で表します。例えば、赤い光の波長は約700nm、青い光の波長は約450nmと違いがあります。
光の波長が異なると色も変わります。これは光が持つエネルギーや波の性質が変わるからです。波長が短い光ほどエネルギーが高く、波長が長い光ほどエネルギーが低いと言われています。
つまり、波長は光の色の違いや性質を決める基本的な特性の一つなのです。
日常生活では、虹を見たときに七色の光が並んでいるのも、この光の波長の違いによるものです。波長の違いで光は屈折しやすさも変わりますが、それは次の屈折率の話で詳しく説明します。
屈折率とは?
屈折率は、光がある物質の中を通るときにどれだけ進む速度が遅くなるかを示す値です。空気中の屈折率は約1ですが、水やガラスになるとそれより大きくなります。
屈折率が高い物質ほど光はゆっくり進み、そのため光の進む方向が曲がります。この現象を「屈折」と呼びます。例えば、水にスプーンを入れるとスプーンが曲がって見えるのは、光が空気から水に入るときに屈折するためです。
屈折率は物質ごとに異なり、同じ物質でも光の波長によって変わります。一般に波長が短い青い光は屈折率が大きく、波長が長い赤い光では屈折率が小さくなります。このため光は色ごとに曲がる角度が変わり、プリズムで虹色に分かれる理由になります。
屈折率は光の曲がり方を決める重要な数値で、光の色や物質の種類によって変化します。
光の波長と屈折率の違いをまとめると?
ここまでの話を簡単にまとめると、
光の波長は光そのものの性質であり、色やエネルギーの違いを生み出します。
一方で屈折率は、その光が物質の中でどのように進み、どれだけ曲がるかを示す値です。
この二つは密接に関係していますが、意味は全く異なります。光の波長は光の固有の長さであり、屈折率は光が物質を通るときの進みやすさを表現しています。
下の表に光の波長と屈折率の主な違いをまとめました。
| 項目 | 光の波長 | 屈折率 |
|---|---|---|
| 意味 | 光の波の長さ(色や性質を決める) | 光が物質中を進む速さの割合 |
| 単位 | ナノメートル(nm) | 単位なし(比率) |
| 影響 | 色やエネルギーの違い | 光の曲がり方や屈折現象 |
| 変化の要因 | 光源や波の性質 | 物質の種類や光の波長 |
この違いを理解することで光の仕組みや見え方をより深く知ることができます。
光の波長について面白い話をすると、光の波長が影響するのは色だけではありません。実は、光の波長が異なると、光が物質を通り抜ける速さも変わるんです。青い光は波長が短いため屈折率が高くなり、赤い光よりも物質中で遅く進みます。この違いがプリズムで虹色に分かれる現象のキモなんです。つまり、色の違い=光の波長の違いが、屈折率にも影響を与えているというわけ。こう考えると波長と屈折率はお互いに関係しているけど、役割は違うことがわかりますね。