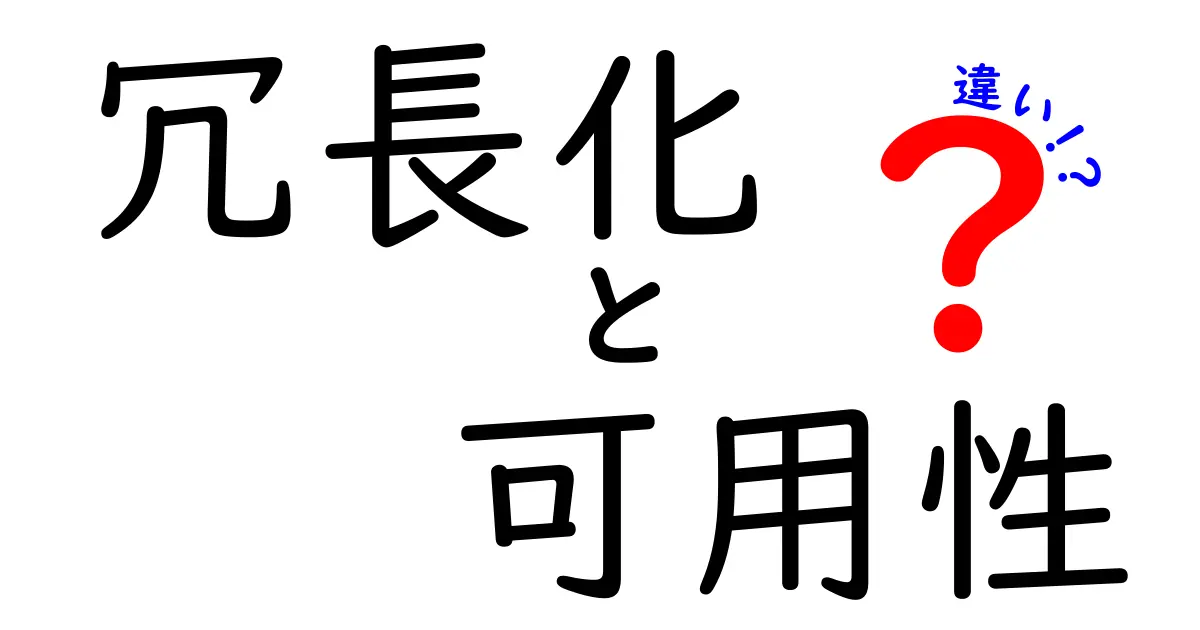

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
冗長化とは何か?
システムの話をする時に出てくる言葉のひとつに「冗長化」があります。これは簡単に言うと、機械やソフトウェアの部品を二つ以上用意しておくことを指します。例えば、コンピューターの中にあるデータを保存するハードディスクを2台以上用意し、もし1台が壊れてもすぐにもう1台で動かせるようにする方法です。
こうすることで、一部の機械や部品が故障してもシステム全体が止まらないようにすることができるのです。システムの信頼性を守るための基本的な技術の一つと言えます。
この考え方は、電気や通信のインフラ、銀行のシステム、大規模なウェブサービスなどで特に重要です。つまり、誰もが使うサービスが途中で止まってしまうことがないように、あらかじめ故障しても大丈夫な仕組みを用意しているわけですね。
可用性とは?
一方で「可用性」という言葉もよく出てきます。これはシステムがどれだけ問題なく使える時間が長いかを表す指標のことです。たとえば、24時間のうちで23時間正常に使えるなら、そのシステムの可用性は約95.8%になります。
可用性はシステムの運用状況を評価する重要な数字で、高ければ高いほど安心して使えるシステムということになります。
システム設計の目標として、99.9%や99.99%の可用性を達成しようとしたりします。これを実現するために、先ほど説明した冗長化などの対策を取り入れることが多いのです。
冗長化と可用性の違いとは?
ここで「冗長化」と「可用性」の違いをはっきりさせましょう。
- 冗長化はシステムの設計や仕組みの一部であり、機械やソフトウェアを複数用意して故障に備えること。
- 可用性はシステムがどれだけ長く問題なく動き続けられるかを示す、評価や目標となる数値。
つまり、冗長化は可用性を高める手段の一つとして使われます。
冗長化によって万が一の故障の影響を減らし、結果として可用性が向上するのです。ただし、可用性を上げる方法は冗長化だけでなく、監視体制や障害対応の速さなどいろいろありますので、冗長化=可用性ではありません。
冗長化と可用性の比較表
| 項目 | 冗長化 | 可用性 |
|---|---|---|
| 意味 | システムの部品を二重化して故障に備える仕組み | システムが問題なく稼働し続ける割合や時間の指標 |
| 役割 | システムの耐障害性を強化する手段 | システムの信頼性や使いやすさを示す評価数値 |
| 例 | ハードディスクを2台用意し同時にデータを保存する ネットワークを複数用意する | 99.9%、99.99%など可用性の目標数値 |
| 目的 | 故障時のサービス停止を防ぐ | サービスが中断なく使えることを保証 |





















