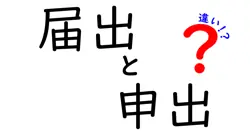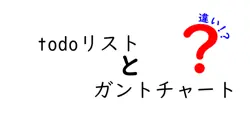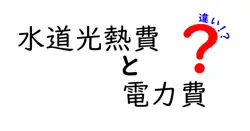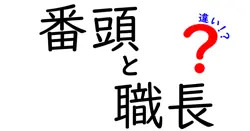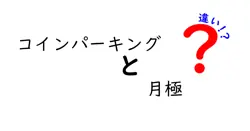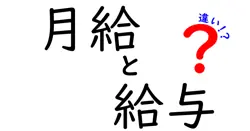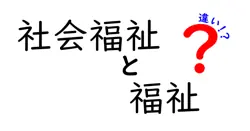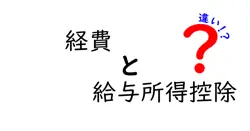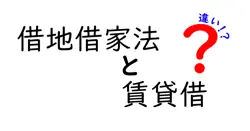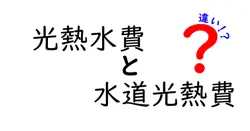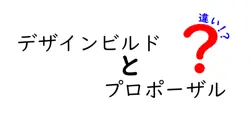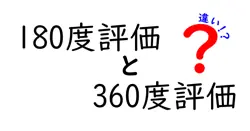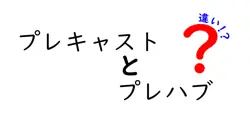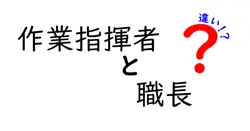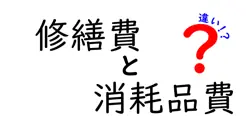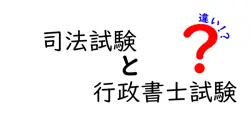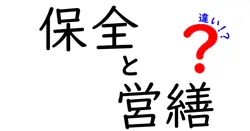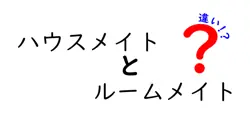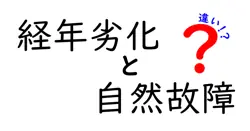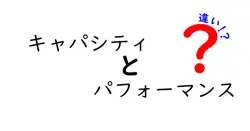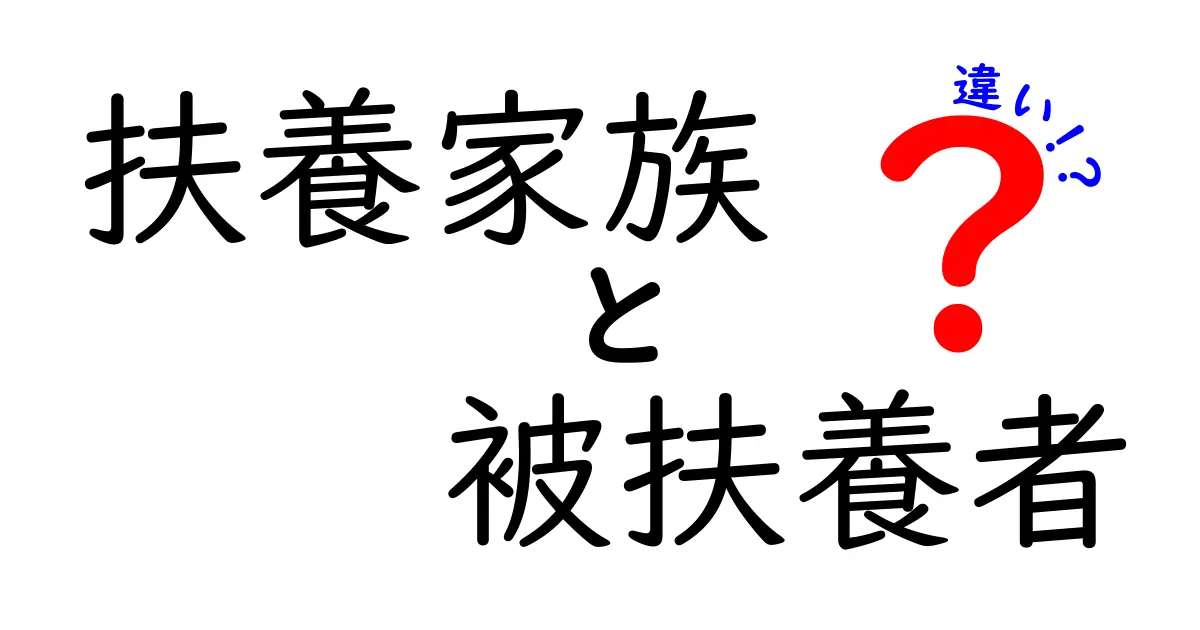
扶養家族と被扶養者の基本的な違い
日常生活や税金、社会保険の話題でよく出てくる「扶養家族」と「被扶養者」。一見同じように感じますが、実は意味や使われる場面が違います。
まず「扶養家族」とは、法律的に生活の面倒を見ている家族のことを指し、主に税金や所得申告で使われる言葉です。それに対して「被扶養者」は、主に健康保険や年金などの社会保険制度上での呼び方で、保険料の負担を免除される条件に当てはまる家族のことを意味します。
つまり、扶養家族は主に“税制上の関係”を表し、被扶養者は“社会保険上の関係”を表していると覚えておくとわかりやすいです。
この2つは重なるケースもありますが、使われる場面によって意味合いが少しずつ違うため、混同しないことが大切です。
扶養家族の詳細なポイント
「扶養家族」は所得税や住民税の計算の際に重要な概念です。
働き手(例えば親など)が収入の一部を家族の生活費として使って支えている状態で、扶養控除などの税金の軽減措置が受けられます。
例えば配偶者、子ども、親などが該当しますが、一定の収入以下であることや生計を一にしていることが条件です。
所得税の扶養控除を受けると税金が安くなるので、多くの働く人が気にするポイントです。
なお、扶養家族の条件は法律の定めにより細かく規定されていますので、なんとなく扶養していると申告しただけでは適用されないことにも注意が必要です。
たとえば、年間の収入が103万円を超えると扶養控除の対象外になります。この線引きは非常に重要で、この金額を超えると税金の扱いが大きく変わります。
また、税制上の扶養は家族の構成や収入だけでなく、住民票や生活実態も関係してくる場合があります。
被扶養者と社会保険の関係
「被扶養者」は社会保険の中で使われる用語です。
健康保険や厚生年金保険の被保険者(働いている本人)が負担する保険料の計算や負担範囲を決めるときに重要です。
被保険者に扶養されていて収入が一定以下の家族は、被扶養者として認められると、本人が負担している保険料の一部負担から除外されるメリットがあります。
具体的には、被扶養者の健康保険は被保険者の保険からカバーされ、被扶養者自身の加入や保険料負担は不要になります。
被扶養者に認められるためには、収入要件や同一生計要件があり、収入は年間130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)が基本的な基準です。
なお、被扶養者には配偶者や子ども、親などが含まれますが、申請や手続きが必要です。
被扶養者として認められることで、医療費等の負担が少なくなるため、家計に大きな影響があります。
この制度は働いている本人の会社や保険組合によって多少の違いがありますが、基本的なルールは厚労省の指導に基づいています。
扶養家族と被扶養者の違いをまとめた表
| 用語 | 意味 | 使われる場面 | 収入の目安 | メリット |
|---|---|---|---|---|
| 扶養家族 | 収入のある人が生活費を支えている家族 | 税金(所得税・住民税)の申告 | 年間103万円以下で扶養控除対象 | 所得税・住民税が軽減される |
| 被扶養者 | 社会保険上で保険料負担が免除される家族 | 健康保険・年金など社会保険制度 | 年間130万円未満(年齢・障害等条件あり) | 保険料負担不要、医療費負担が減る |
まとめ:どんな時に使い分ければいいの?
「扶養家族」は税金の話の時に注目し、「被扶養者」は社会保険の話をするときに意識すれば問題ありません。
例えば、年末調整や確定申告の時は扶養家族の要件を確認し、健康保険の扶養に関しては勤務先の保険担当者や社会保険事務所の指示を受けることが重要です。
どちらも家族の経済的支援関係を示す言葉ですが、細かな基準や手続きが異なるため混同しないようにしましょう。
これから税金や保険に関する書類を作成・申請するときは、この違いを理解しておくとスムーズに対応できます。
「被扶養者」という言葉を聞くと、なんとなく家族のうち特に保険の対象になる人をイメージしますよね。でも実は、この制度には意外と知られていないポイントがあります。たとえば、被扶養者の収入条件は130万円未満が一般的ですが、60歳以上や障害者の場合は180万円未満まで認められているんです。これは高齢者や障害のある人の生活を守るための配慮で、社会保障の温かさを感じさせますよね。こうした制度の細かい仕組みを知ると、家族の健康保険の管理や手続きももっと理解しやすくなりますよ。
前の記事: « マザコンと親孝行の違いとは?その意味と考え方をわかりやすく解説!
次の記事: 再婚と結婚の違いとは?知っておきたいポイントをわかりやすく解説! »