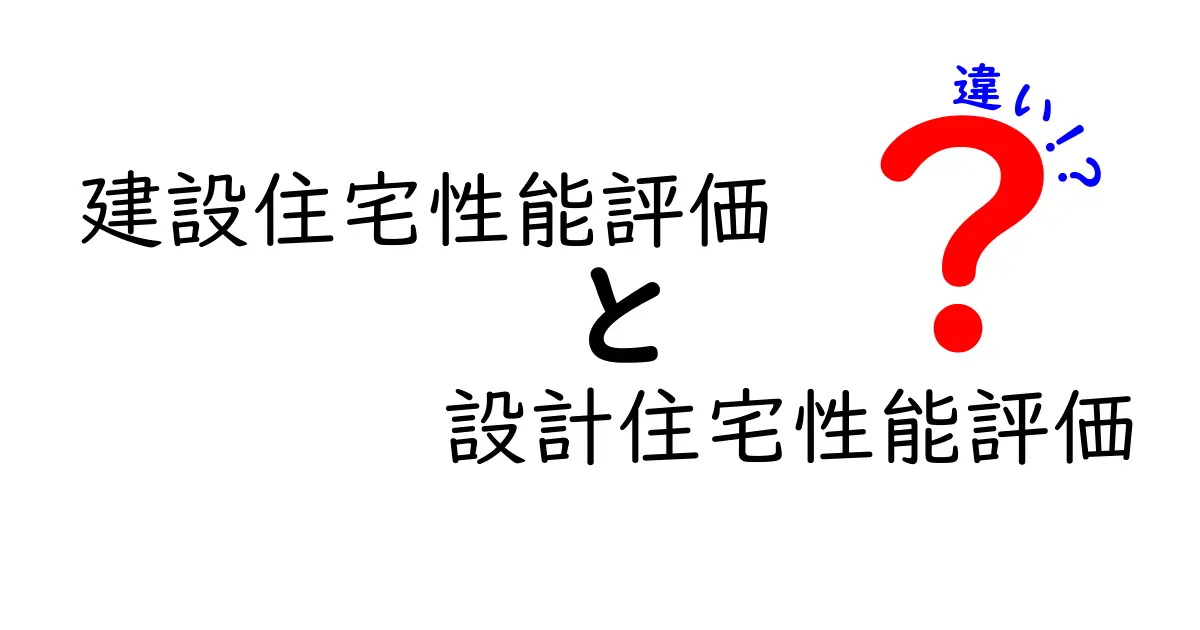

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
建設住宅性能評価と設計住宅性能評価の基本とは?
住宅を建てるときに、家の性能を数値や評価で確認できる制度があることをご存じでしょうか。これは「住宅性能評価」という国家の制度で、家の安全性や耐久性、省エネ性能などがきちんと確かめられるため、安心して住める家づくりに役立ちます。
その住宅性能評価には主に二つの種類があります。「建設住宅性能評価」と「設計住宅性能評価」です。この二つは似ているようで、実は役割やタイミングが違います。
今回はこの二つの住宅性能評価、その違いについてわかりやすく解説します。中学生でも理解できるように、難しい専門用語はできるだけ使わずに説明していきますのでご安心ください。
設計住宅性能評価とは何か?
設計住宅性能評価は、家の設計図ができた段階で住宅がどんな性能を持っているかを評価する制度です。
つまり、まだ家が建っていない、設計だけの状態で評価を受けるということです。
具体的には、耐震性や断熱性、耐久性などさまざまな項目において、「この設計図ならしっかり性能が出せる」ということを第三者の専門家が証明してくれます。
この評価を元に家づくりを進めると、設計段階で問題点を見つけて改善できるのが大きなメリットです。
また、住宅ローン減税や補助金の申請時に、設計住宅性能評価書が必要なケースもあるため、もらっておくと便利な場合があります。
建設住宅性能評価とは何か?
建設住宅性能評価は、実際に家が完成し、建物が建ったあとに行われる性能の評価です。
建設された住宅が設計通りの性能を持っているか確認するために、実際の工事内容や使用した材料でチェックします。
家が完成してから評価を受けるので、完成した家の住みやすさや安全性が保証される証明になります。
これにより、建てた住宅の性能に安心感が生まれ、売買や賃貸の際にも効果的です。
実際に検査をするので、設計図だけでなく施工の過程も含めて正しく実施されていることが分かる点が重要です。
設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の違いを表で比較!
ここまで説明した内容をもとに、違いが分かりやすいように表にまとめました。
| 項目 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
|---|---|---|
| 評価のタイミング | 設計図が完成した時点 | 家が完成した後 |
| 評価される内容 | 設計図に基づく性能 | 実際の施工・仕上げまでの性能 |
| 評価の目的 | 問題箇所の早期発見・改善 | 完成した住宅の性能保証 |
| 取得のメリット | 補助金申請やローン優遇に有利 | 売買・賃貸時の信頼性向上 |
| 評価を受ける主体 | 設計者(建築士)が中心 | 施工業者・検査員が関与 |
まとめ:安心の家づくりには両方の評価が大切!
家を建てるときに設計住宅性能評価を受ければ、設計段階で問題に気づきやすくなります。そして建設住宅性能評価を受けることで、完成した家の性能がしっかり保証されていると証明されます。
どちらも第三者機関がチェックすることで、施主や家族が安心して過ごせる家づくりを支えています。
初めての家づくりや買い替えでも、性能評価の仕組みを理解して活用すると良いでしょう。
設計住宅性能評価と建設住宅性能評価、この違いを押さえたうえで、信頼できる施工業者と相談しながら安心安全な家を建ててください。
「設計住宅性能評価」は、設計図の段階で住宅の性能を評価するための制度です。でも、その評価は実際の家が建つ前の「予測」にすぎません。だから、建ったあとにどうなるかまだ分からないんです。だからこそ、設計図が正しく性能を満たしているかしっかりチェックする専門家の役割はとても大事。ちょっとした設計ミスが将来の住み心地に影響するので、「設計での評価」があると安心感が格段にアップします。





















