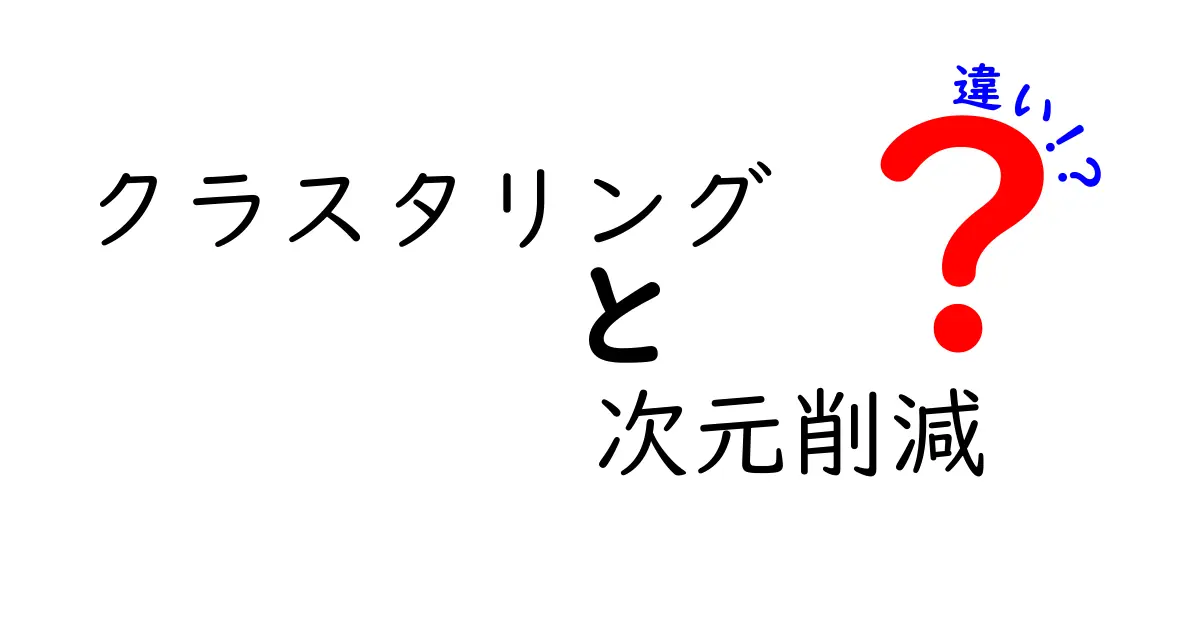

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クラスタリングとは何か?
クラスタリングは、たくさんのデータを似ているもの同士でグループ分けする技術のことです。
例えば、学校のクラスメートを性格や趣味が似ているグループに分けるようなイメージです。
数学や情報の分野では、データの特徴を元にして自動で似ているものをまとめるためによく使われます。
クラスタリングのポイントは「グループ分け」が目的であることですね。
それにより、データの中の潜在的なパターンや構造を見つけることができます。
クラスタリングは教師なし学習の一つで、あらかじめ正解ラベルがないデータでも利用可能です。
次元削減とは何か?
次元削減は、データの特徴数(変数の数)を減らす技術です。
データが多くの特徴を持っていると分析が難しくなったり、計算が大変になったりします。
そこで、特徴の数を減らして扱いやすくする目的で次元削減を行います。
例えば、数学のテストで点数がたくさんあるけど、似たような意味の問題が多い場合、それらをまとめて大事なポイントだけにして分かりやすくするようなイメージです。
次元削減の目的は「データの特徴を簡略化して可視化や分析しやすくすること」にあります。
代表的な方法には主成分分析(PCA)やt-SNEなどがあります。
クラスタリングと次元削減の違い
ここからはクラスタリングと次元削減の違いをわかりやすく解説します。
- 目的の違い
クラスタリングはデータをグループ分けすることが目的ですが、次元削減はデータの特徴数を減らして簡略化することが目的です。 - 結果の違い
クラスタリングの結果は、どのデータがどのグループに入るかを示します。一方、次元削減はもとの多い特徴を少ない特徴に変換したデータを出します。 - 使い方の違い
クラスタリングは群分けやパターン発見に使い、次元削減はデータの可視化やノイズ除去、計算の高速化に使われます。
下の表でも簡単にまとめてみました。
まとめ:どう使い分ける?
クラスタリングと次元削減はどちらもデータ分析には欠かせない技術ですが、
着目するポイントが違います。
データの性質や目的に応じて両方を組み合わせて利用することもよくあります。
例えば、次元削減で特徴を減らしてからクラスタリングを行うと、よりわかりやすくグループ分けできることがあります。
中学生でも理解しやすいようにまとめると、
・クラスタリングはデータをグループに分ける作業
・次元削減はデータの情報を減らして見やすくする作業
このように覚えておくと便利です。データ分析に興味がある人はぜひ知っておきたい基本の違いですね。
次元削減は実はただ特徴を減らすだけでなく、『情報の本質を残す』ことがとても大切です。
例えば、たくさんのテストの点数をまとめて一つの成績評価にするのはまさに次元削減の考え方。でも、まとめ方を工夫しないと本当に重要な部分が見えなくなってしまうことも。
データ科学者たちは、どの特徴を残してどれを捨てるかをとても慎重に選んでいます。
次元削減は単なる数を減らすテクニックではなく、情報の価値を保つための『賢い簡略化』なのです。これが意外と面白いポイントですよね。





















