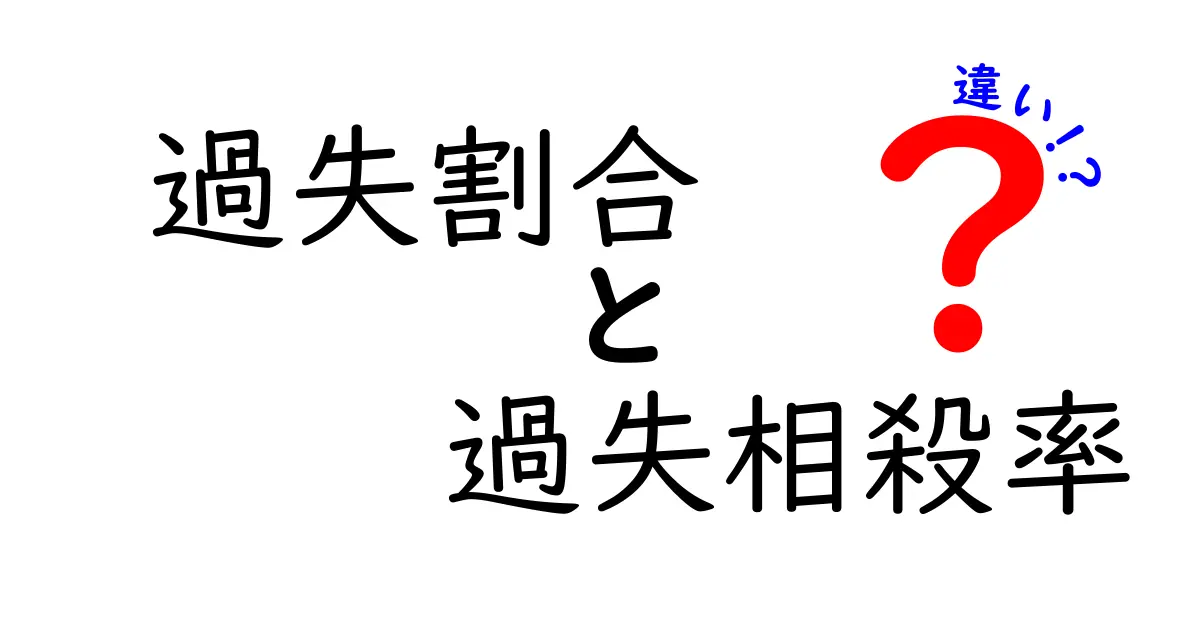

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
過失割合と過失相殺率、まずは基本を知ろう
交通事故やトラブルのときによく出てくる言葉に「過失割合」と「過失相殺率」があります。この二つは似ているようで違う意味を持つ言葉です。
まず、「過失割合」は事故や損害が起きたとき、どちらがどれだけ悪いかを数字で示したものです。例えば、100%の事故の原因を分けると、片方が70%、もう片方が30%のように決められます。
一方で、「過失相殺率」は「過失割合」を使って、損害賠償の額を減らす割合のこと。損害賠償は本来、事故の損害全額を全て負担するわけではなく、過失(悪かった部分)に応じて減らされます。その減らされる割合を「過失相殺率」といいます。
つまり、過失割合は原因の割合、過失相殺率は実際のお金の計算で使う割合と覚えるとわかりやすいです。
次の見出しでは、それぞれの詳しい意味と違いを見ていきましょう。
過失割合の意味と使い方
過失割合は損害が起きた原因を「どのくらいその人に過失(ミス・悪さ)があるのか」で示す数字です。
たとえば、あなたが自転車で交差点を渡っているときに車とぶつかった場合、警察や保険会社は事故の証拠や証言をもとに「車側が60%、自転車側が40%」などの過失割合を決めます。
この割合は事故の責任を公平に判断するためのもの。
過失割合は事故の原因を分けることで、誰がどれだけ悪いかをはっきりさせる役割があります。
ただし、この割合を決める基準は法律や判例、保険会社の基準によって微妙に違うこともあります。早い段階で正確に決めることは、もめごとを防ぐためにとても重要です。
過失相殺率とは?過失割合との関係
過失相殺率は、過失割合を使って実際に損害賠償の計算をする時に出てくる言葉です。
たとえば、事故であなたが100万円の損害を受けたとします。そこにあなたの過失が30%あった場合、保険会社や裁判では損害額から30%を引いた70万円が相手から受け取れる金額となるわけです。この70%の部分が「過失相殺率」と呼ばれます。
つまり、過失相殺率=1−過失割合(自分の過失分)なので、損害賠償で実際に手にするお金の計算に使います。
過失相殺率は損害の金額を調整するための割合なので、事故の原因とは違う目的で使われます。
まとめると、過失割合は責任の割合、過失相殺率は受け取る賠償金の割合、と言えるでしょう。
過失割合と過失相殺率の違いを表で比較
まとめ:違いを理解してトラブル回避を!
「過失割合」と「過失相殺率」は似ているように見えますが、「責任の割合」と「賠償金の調整」という違いがあります。
事故やトラブルの際に、過失割合がきちんと判断されているかを確認し、そのうえで過失相殺率を使って賠償金の計算がされているか理解することが大切です。
これを知っておくことで、保険会社との話し合いや裁判での理解がスムーズになり、不公平な損害負担を防ぎやすくなります。
みなさんも、事故にあったときや誰かとトラブルの時には、過失割合と過失相殺率の違いをしっかり押さえて適正な対応を心がけましょう。
「過失相殺率」という言葉は聞き慣れない人も多いかもしれませんね。でもこの言葉の大切なポイントは、損害賠償でどれだけお金が減らされるかを決める割合だということです。事故で自分にどれだけ過失があるかがわかると、相手からもらえるお金がその分減っちゃうんです。こうした仕組みがあるから、みんなもっと安全に気をつけるんですね。身近な法律のルールを知ると、日常のトラブルに強くなれる面白さもありますよ!
前の記事: « 判決と対審の違いとは?裁判の仕組みをわかりやすく解説!





















