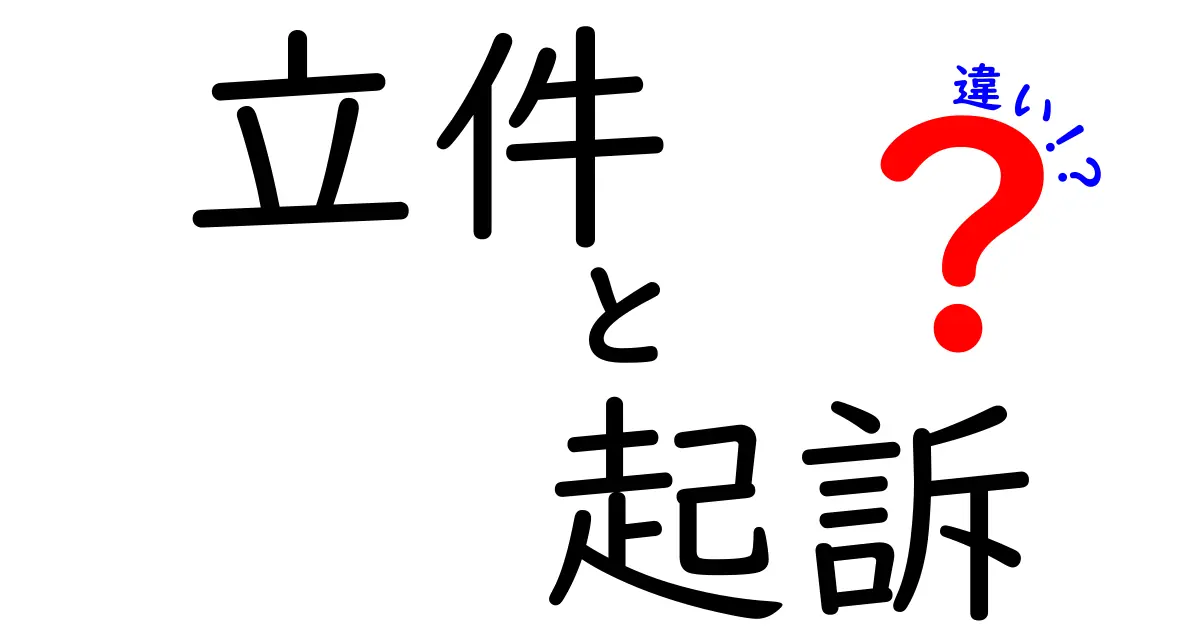

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
立件と起訴の違いについて基本を知ろう
私たちがニュースなどでよく耳にする言葉に、「立件」と「起訴」があります。どちらも刑事事件に関する言葉ですが、実は意味や役割が違うんです。
立件は、警察や検察が犯罪の可能性があると思い調査を始める段階で、一方起訴は、調査や捜査が終わり裁判で罪を問うために正式に告訴することです。
この違いを知れば、ニュースの内容をより正しく理解できるようになります。
この記事では、立件と起訴の意味や手続きの流れ、そして両者の違いをわかりやすく説明します。
立件とは何か?捜査の始まりを意味する
立件とは、警察や検察が犯罪が起きた可能性があると判断し、事件として正式に捜査を開始することを指します。
例えば被害届が出されたり、警察が何か不審な出来事を知った時点で調査が始まりますが、その調査がある程度進んで「この事件は犯罪の可能性が高い」と見なされた際に立件となります。
立件は正式な刑事事件として認められる最初の段階であり、ここから証拠を集めたり関係者から事情聴取を行ったりします。
しかし、立件=逮捕や起訴を意味するわけではありません。あくまで「事件」として取り扱うかの判断段階なのです。
起訴とは?裁判にかけるための正式な告発
起訴は、検察官が十分な証拠が揃い、被疑者(容疑者)を裁判で審理すべきだと判断した時に行う手続きです。
起訴後は裁判所で裁判が開かれ、被疑者の罪状が審理され有罪か無罪かが決まります。
つまり起訴は、犯罪を犯したかどうかを裁判所に判断してもらうために事件を送ることと言えます。
ここで重要なのは、起訴されて初めて正式に裁判で罪について争うことになる点です。
また起訴には「公判請求」と「略式起訴」があり、それぞれ裁判の進み方が異なります。
立件と起訴の主な違いを表でまとめてみよう
| 項目 | 立件 | 起訴 |
|---|---|---|
| 意味 | 犯罪の疑いがあると判断して事件として扱うこと | 裁判で罪を問うために検察が正式に告発すること |
| 段階 | 捜査の開始・事件として認定される段階 | 捜査終了後に裁判に移す段階 |
| 実施主体 | 警察や検察 | 検察官 |
| 結果 | 捜査継続または不起訴 | 裁判開始(有罪・無罪の審理) |
| 裁判所の関与 | なし(裁判前の段階) | あり(裁判開始) |
このように立件は事件として取り扱うことを決める段階、起訴は裁判にかけるべきと判断して告発する段階だと理解してください。
まとめ:立件と起訴の違いを正しく理解しよう
刑事手続きでは、立件→捜査→起訴→裁判という流れがあります。
立件は捜査の入り口であり、起訴は裁判の入口です。両者は連続していますが役割が違います。
ニュースなどで「〇〇事件が立件された」「起訴される見込み」と聞いたら、この流れを思い出してみてください。
そうすれば、どの段階で何が行われているのか、より詳しく理解できるはずです。
刑事事件の仕組みを知ることで、法律への関心も高まり、社会のニュースもより身近なものになりますよ。
「起訴」と聞くと、つい「犯罪者が裁判で罰せられること」と思いがちですが、実は「起訴」とは裁判を始めるための公式な手続きのことです。
興味深いのは、全ての事件が起訴されるわけではないという点です。厳密には証拠や事情を検察官が調べ、起訴しない場合も多々あります。つまり、起訴は犯罪者を決める瞬間ではなく、裁判のスタートラインなのです。
この区分けを知っておくと、ニュースの報道やドラマを見る際も「どうしてこの人が起訴されないのか?」という疑問を持ちやすくなり、法律の理解が深まりますよ。
前の記事: « 提訴と起訴の違いをわかりやすく解説!法的手続きの基本ポイント





















