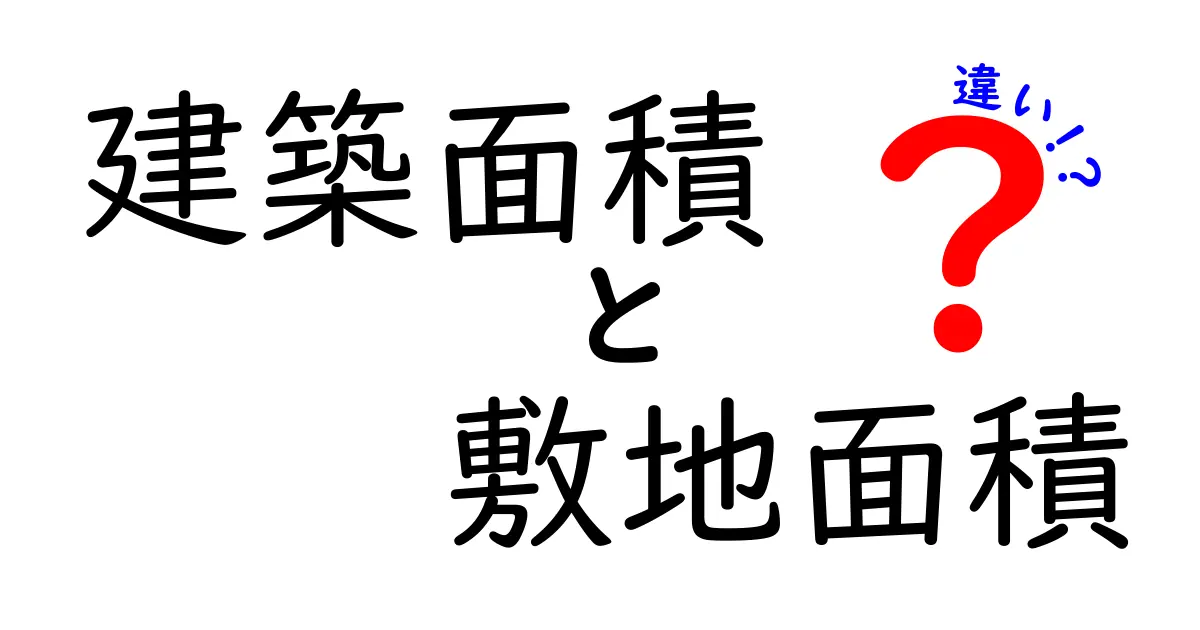

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
建築面積と敷地面積の基本的な違い
建築面積と敷地面積は、不動産や建築の世界でよく使われる言葉ですが、その意味や使い方は全く違います。建築面積とは、建物が地面に接している部分の面積のことを指します。一方で、敷地面積は、建物が建てられている土地全体の面積を指します。つまり、敷地面積は土地の大きさ、建築面積はその土地上の建物の大きさを表しているのです。
例えば、敷地面積が200平方メートルの土地に建物が建っているとします。この建物の建築面積が100平方メートルだとすると、その土地の半分に建物が広がっているということになります。
この違いを知ることは、住宅を選んだり、土地の活用方法を考えたりする際にとても重要です。なぜなら、建築面積が大きければ、その建物の規模が大きいことを示し、逆に敷地面積が広くても建物が小さければ、庭や駐車場などのスペースが多い可能性があるからです。
さらに、建築基準法上、敷地面積に対しての建築面積の割合(建ぺい率)が制限されている場合があり、これが建物の大きさを決める目安になります。このような基準は安全性や住環境の質を守るために設けられているのです。
建築面積と敷地面積が建築計画で持つ役割
建築計画を立てる時、建築面積はどれだけ土地に建物を広げるかを決める重要な数字となります。建ぺい率という、敷地面積に対する建築面積の最高割合が法律で定められていて、例えば建ぺい率が60%なら、敷地面積の60%までしか建物を建てられない決まりです。
一方、敷地面積は土地の広さや形を把握するための基礎情報として使われ、その土地にどのような建物を建てられるか、どんな利用が可能かを判断する材料になります。土地が広ければ、建築面積を大きくしても建ぺい率の制限内に収まるため、大きな建物が建てられる場合もあります。
また、敷地面積は不動産の売買や賃貸の際に重要な基準であり、土地の価値判断にも使われるので、どちらも建築と土地利用の計画に欠かせない情報となるのです。
これらの数字を正しく理解して計画を立てることで、法律違反を避け安全で快適な住まいを作ることができます。
建築面積と敷地面積の違いをまとめた表
以上のように、「建築面積」と「敷地面積」は似ているようで全く違う意味があります。建築面積は建物の footprint、敷地面積は土地のサイズというイメージです。住宅購入や土地探し、建築計画の際には必ず押さえておきたい基礎知識なので、ぜひ正しく理解してください。
建築面積という言葉を聞くと、建物の延べ床面積(すべての階の床の面積の合計)と混同しがちですが、この2つは全く違います。建築面積は建物が地面に接している部分の面積だけを示し、2階や3階の面積は含まれません。例えば、1階部分が100平方メートルで2階が50平方メートルの建物でも、建築面積は100平方メートルです。この違いは建築基準法の建ぺい率や容積率を計算する時にとても重要なので、建築計画の際にはぜひ押さえておきましょう。
前の記事: « 敷地境界と隣地境界の違いを徹底解説!初心者でもわかる基本ポイント





















