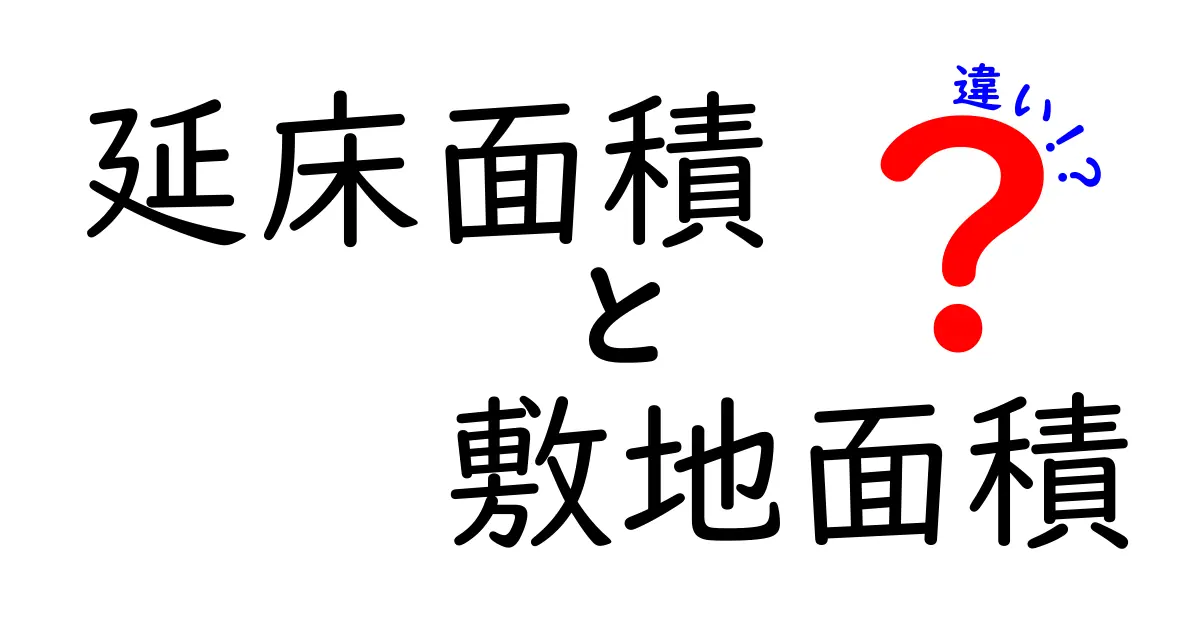

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
延床面積とは何か?
延床面積とは、建物の各階すべての床の面積を合計したものです。
例えば、2階建ての家があるとき、1階と2階の床面積を足した数値が延床面積となります。
この数字は建物の「延べ」の広さを示し、建築基準法などで建物の大きさを考える際の基準として使われます。
つまり、延床面積は建物の中で実際に使える床の面積の合計と考えてください。
延床面積には、玄関や廊下、部屋はもちろん、倉庫やトイレ、押入れ、階段部分も含まれますが、屋根裏収納やベランダ、バルコニーは含まれない場合が多いです。
延床面積は建物の広さやゆとりをイメージするためにとても大切な情報となっています。
一般の人にとっては「家がどれくらいの広さか」という目安になる数字で、住宅のパンフレットや広告にも必ず記載されています。
次に、延床面積と対比される敷地面積とは何かについて見ていきましょう。
敷地面積とは何か?
敷地面積とは、その建物が建っている土地の面積のことを指します。
つまり、家やビルではなく、その建物が占めている土地全体の広さです。
土地の形や大きさによって敷地面積は変わります。
一般的には不動産の売買や登記の際に使う数字で、土地の「外枠」の広さを示す数値です。
たとえば、家が建っている敷地が100平方メートルなら、これが敷地面積です。
この広さの中に建物の延床面積が入るというイメージです。
また敷地面積は土地の購入や資産価値を考える際の重要な指標となります。
土地の広さが大きいほど庭を広くしたり駐車場を置く余裕が出ることも多いため、生活の快適さにも関わってきます。
ただし土地の形状や接道の状況によっては、利用しづらい部分もあるので注意が必要です。
延床面積と敷地面積の違いをわかりやすく比較
簡単に言うと、延床面積は「建物の合計床面積」、敷地面積は「土地の広さ」です。
具体的な違いは以下のような点にあります。
| 項目 | 延床面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|
| 意味 | 建物の全階の床の面積の合計 | 土地の面積の全体の広さ |
| 単位 | 平方メートル(㎡) | 平方メートル(㎡) |
| 使い方 | 建物の大きさや建蔽率の計算 | 土地の評価や購入時の基準 |
| 含まれる範囲 | 部屋、廊下、倉庫などの床面積の合計 | 建物以外の庭や駐車場も含む |
| 住宅広告に見られる | 必ず記載されていることが多い | 販売物件の土地面積として記載 |
このように二つは似ているようで役割や対象がまったく違います。
住宅購入や建て替えの際にはそれぞれの意味をしっかり理解することが失敗しないために大切です。
まとめ:延床面積と敷地面積の違いを理解して賢く住まい選びを!
今回は延床面積と敷地面積の違いについて詳しく解説しました。
延床面積は建物の中で実際に使える床の広さの合計で、敷地面積はその建物が建っている土地の広さ全体を指します。
両者は住宅選びや建築計画を考えるうえで基本中の基本の指標です。
例えば広い家を建てたい場合、延床面積を大きくすれば床の面積は増えますが、その建物を建てるための土地(敷地面積)が小さければ制限にあった建物しか建てられません。
逆に広い土地があっても建物の延床面積が小さければ生活空間は狭くなります。
このように両者のバランスがとても重要です。
また不動産広告や住宅の資料を見る際は、「延床面積」と「敷地面積」の単位がどちらも㎡で同じだから混乱しやすいですが、必ずその対象が土地か建物かを意識してください。
この記事を参考にして、家や土地の広さの意味を正しく理解し、より満足のいく住まい選びに役立てていただければ嬉しいです。
少し深掘りしてみましょう。
延床面積は実は建築基準法でのルールによって計算方法が厳密に決まっています。
例えば、屋根裏の収納は床面積に入れないことが多いですが、倉庫や玄関は含まれます。
このため、単純に「床の広さ」を測れば良いというわけではなく、法律のルールを守って計算しなければなりません。
その点は「延床面積」を理解するときの、ちょっとした奥深いポイントです!
さらに、延床面積は家の快適さだけでなく、固定資産税の評価にも影響します。
建物の広さが大きければ税金も変わるため、具体的な数字は大切に扱われています。
前の記事: « 敷地面積と開発面積の違いとは?わかりやすく解説!





















