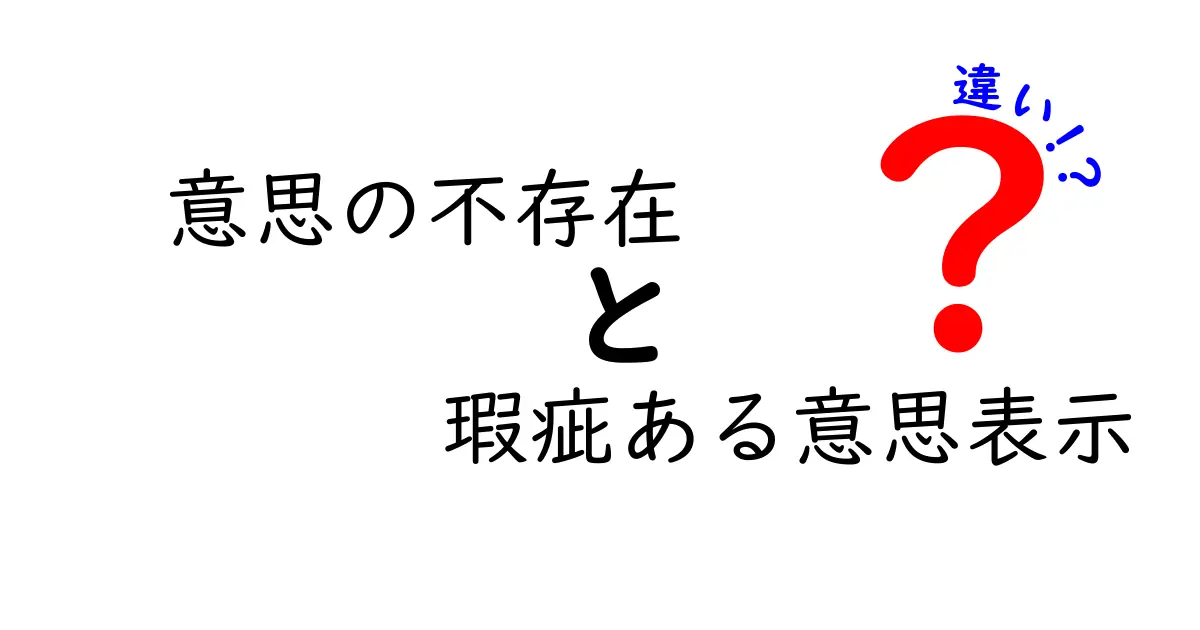

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
意思の不存在と瑕疵ある意思表示とは何か?
契約や合意をする場面でよく出てくる法律用語に、「意思の不存在」と「瑕疵(かし)ある意思表示」があります。どちらも「意思表示」と関係していますが、意味合いや法律上の扱い方が異なります。今回はこの二つの言葉の違いを、中学生にもわかりやすく、丁寧に解説していきます。
まずは「意思表示」とは何か?意思表示とは、自分の考えや意思を相手に伝えて示すことを指します。例えば、「この商品を買います」「旅行に行きたい」などの発言や書面がそれに当たります。
意思表示が正しく成立していないと、契約の成否に大きな影響があるため、法律では特別に扱われています。
意思の不存在とは?
意思の不存在とは、そもそも有効な意思表示が最初から存在しなかった状態を指します。言い換えると、本人がその意思表示をしなかった、または意思決定が全く行われていない状態です。
例えば、眠っている間に誰かが代理で売買契約をしたような場合です。この場合「本人の意思」はありません。だから、その意思表示は「無効」となります。
意思の不存在の例には以下があります。
- 失神状態での意思表示
- 重大な錯誤により全く違う内容の意思表示をした場合
- 強迫(脅迫)されて意思が完全に奪われた場合
これらは、意思がそもそも存在していなかったか、本人の意思とは全く異なる表示になったため「無効」とされます。
瑕疵ある意思表示とは?
瑕疵ある意思表示とは、一応本人が意思表示をしたものの、何か問題(瑕疵)があって、その意思表示が本当の自由な意思に基づいていなかった状態を指します。
つまり、完全に意思がないわけではなく、誤解や騙されたりしたことで間違った意思表示をした状態です。法律では「取り消すことができる」とされています。
瑕疵ある意思表示の例は以下の通りです。
- 錯誤(誤った理解に基づく意思表示)
- 詐欺による意思表示
- 強迫による意思表示(意思の不存在と異なり、意思があるが自由が制限されている状態)
つまり、瑕疵は「意思はあるが何か問題がある」という意味で、法的には「取り消せばなかったことにできる」という扱いになります。
意思の不存在と瑕疵ある意思表示の違いを表で比較
まとめ:契約や取引をする際の注意点
契約では本人の自由な意思に基づく意思表示が大切です。意図しない契約や勘違いによる契約は、あとでトラブルの種になります。
「意思の不存在」は、そもそも意思がないので契約は最初から無効になります。一方「瑕疵ある意思表示」は、意思はあるものの問題があるため、取り消し手続きをすれば無効にできます。
どちらもトラブルになったときには法律上の救済措置がありますが、なるべくトラブルを避けるためには、しっかりと内容を理解し、自由な意思で判断することが重要です。
法律の専門家に相談するのも良いでしょう。
このように「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の違いを理解しておくことは、契約や合意を結ぶ際の安心材料になります。
契約の基礎知識として、ぜひ覚えておきましょう!
法律の世界でよく聞く「意思の不存在」という言葉は、一見すると難しいですが、実はとても重要な意味があるんです。たとえば、眠っている間に契約したらどうなる?実はその契約は無効になります。なぜかというと、本人の意思がそもそも存在していないから。つまり、契約は“本人の自由な意思”があって初めて成り立つもの。これを知らずに契約すると後で大変なことに!覚えておくと役立ちますよ。
次の記事: 取消権と同意権の違いをわかりやすく解説!法律の基本ポイントまとめ »





















