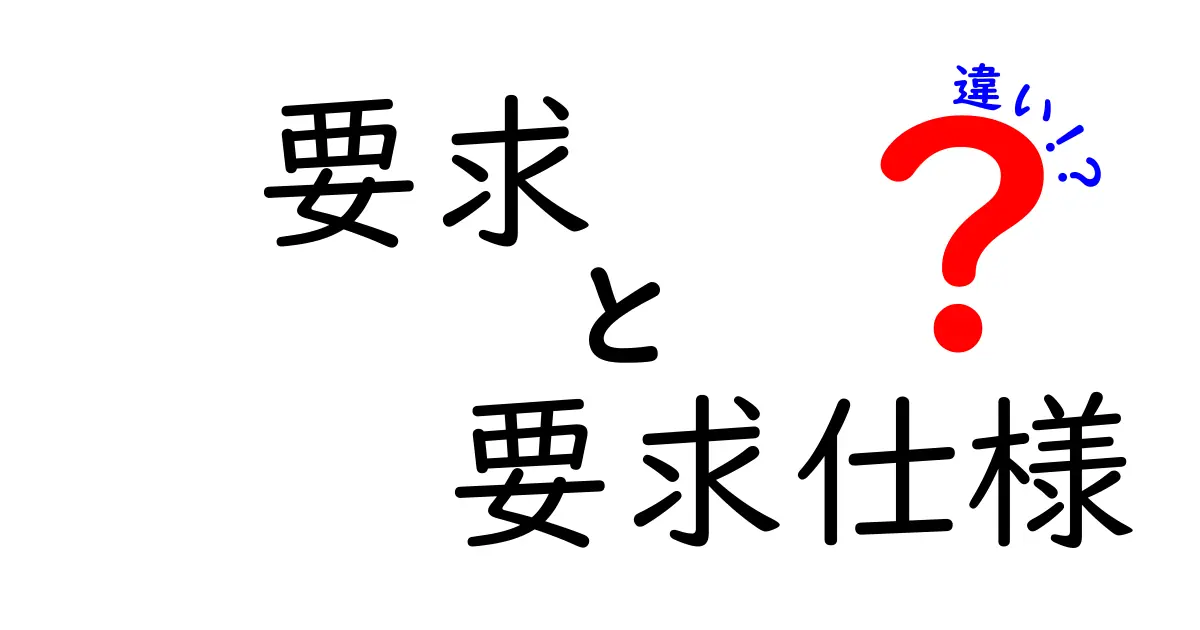

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:要求と要求仕様の基本を押さえよう
ここでは、「要求」と「要求仕様」と「違い」を中学生にもわかる言葉で解説します。まずは用語の定義からです。要求という言葉は「こうしてほしい」「こんな状態が望ましい」という私たちの気持ちやニーズを指します。
つまり、まだ形が決まっていない“願望”に近いイメージです。これに対して要求仕様は具体的な機能や条件を言語化したものです。たとえば「ゲームアプリなら1秒で反応する」「1画面あたりの表示は768x1024(px)以上必要」など、誰が何をどう動かすかを決める設計の土台となるものです。
違いをもう少し分かりやすく整理すると、要求は“願いごと”で、要求仕様は“実現のレシピ”です。ここを混同すると、作るものがズレてしまいます。人と物の関係で言えば、要求は顧客の声、要求仕様は開発チームの設計図と考えるとイメージしやすいでしょう。
実務の世界では、要求と要求仕様を分けて考えることが品質や納期に大きく影響します。要求が曖昧だと、途中で仕様を変えやすく、仕様が決まっていても実装時にずれが生じやすいです。これらを理解しておくと、プロジェクトの方向性を正しく導く手助けになります。
違いの整理:現場の例と整理のコツ
実際の例を通じて、要求と要求仕様の差を体感します。例えば学校のイベント管理アプリを作るとします。要求は「イベントを円滑に運営したい」「保護者にも知らせたい」という声で、だれがいつ何をするかの情報はまだ抽出されていません。これに対して要求仕様は検証可能な条件です。例えば「通知はSMSとメールの二通りで、遅延なく送信されること」「イベント作成時に自動カレンダー登録が行われ、編集履歴が残ること」など、誰が見ても同じ意味になる明確な数値や機能が並びます。
この差を理解することで、後の設計やテストがずれません。
さらに、現場での整理のコツとして、以下を意識します。
- 優先度の設定:最も影響が大きい要求仕様から取り組む
- 用語の統一:同じ言葉を別の意味で使わない
- トレーサビリティの確保:要件-仕様-実装の紐づきを記録する
実務では、こうした整理があるかないかで納期や品質が大きく左右されます。経験則として、要件の詳細が少ない状態では開発者は推測を増やしますが、それはリスクです。逆に、仕様が過度に詳細すぎると柔軟性が失われ、変更対応が難しくなります。重要なのは適切なバランスです。ここまでの理解を日常の勉強や部活動の計画にも応用すると、将来のプロジェクト運営にも役立ちます。
今日は、要求仕様という言葉の話をしてみました。私が中学生の頃、友だちと部活のイベント準備で、まず何をしたいのかを口に出していました。そこで先生がそれを実現するには何をどう作るのかを考えてくれたので、段階的に決める大切さを学びました。要求は気持ちであり、要求仕様は設計図です。もしあなたがアプリを作るなら、まず何を達成したいのかを声に出し、次にそれをどう測定するかを決めることが成功の鍵です。





















