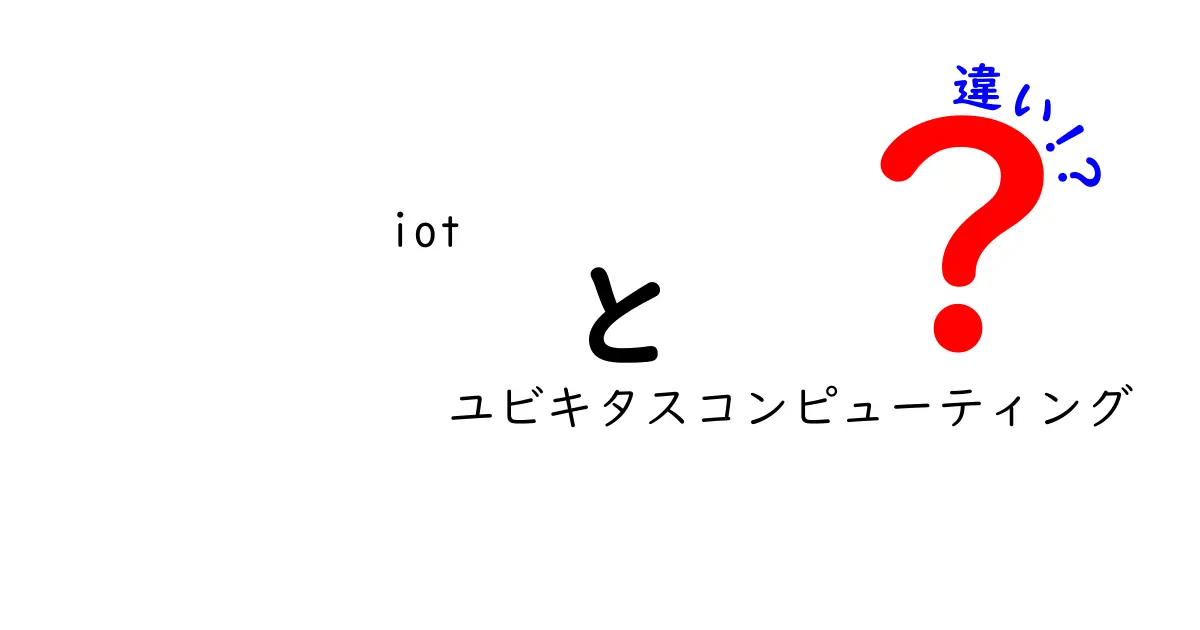

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IoTとユビキタスコンピューティングの基本的な違いとは?
みなさんは、「IoT(モノのインターネット)」と「ユビキタスコンピューティング」という言葉を聞いたことがありますか?どちらもコンピューターやネットワークに関係していて、よく似た意味にも見えますが、実は少し違う特徴を持っています。
まず、IoTは「Internet of Things」の略で、身のまわりにあるさまざまなモノをインターネットに接続して、データを収集・やりとりしながら便利なサービスを作り出す技術です。たとえば、スマート家電やウェアラブル端末、工場の機械などがインターネットにつながって、自動で動いたり情報を送ったりするイメージですね。
一方、ユビキタスコンピューティングは、日本語で「遍在コンピューティング」とも言い、コンピューターがどこにいても自然に使えるようになる未来の考え方を指します。私たちは意識しなくても、どこにいても情報やシステムにアクセスできることを目標にしているんです。つまり、IoTがモノの繋がりを作る技術であるのに対し、ユビキタスコンピューティングは生活の中にコンピューターが溶け込むイメージと言えます。
このように、IoTは技術やシステムの側面が強く、ユビキタスコンピューティングはその技術が実現する社会や環境の理想形と捉えることができます。
IoTとユビキタスコンピューティングの具体例から見る違い
少しイメージをふくらませるため、具体例を比べてみましょう。
・IoTの例
温度や湿度を感知するセンサーが設置されたスマートホーム。スマホを使って遠隔で電気やエアコン(関連記事:アマゾンでエアコン(工事費込み)を買ってみたリアルな感想)のスイッチを入れたり切ったりできるのがIoTの仕組みです。
・ユビキタスコンピューティングの例
街中の照明や交通信号、公共施設の案内板がユーザー一人ひとりの状況を感知し、必要な情報やサービスをその人に合わせて提供してくれる。
ここでポイントになるのは、ユビキタスコンピューティングは「いつでもどこでも必要なコンピューターサービスが使える」ことが重視されているところです。
両者の例をさらにわかりやすく表にまとめてみました。ポイント IoT ユビキタスコンピューティング 目的 モノをネットにつなげて便利にする 生活全般に自然にコンピューターが利用できる環境作り 主な技術 センサー、ネットワーク、クラウドなど 分散コンピューター、センサー、AIなど 利用シーン スマート家電、健康管理機器、工場の自動化 スマートシティ、パーソナルアシスタント、公共サービス ユーザーの意識 操作や設定が必要なことが多い ほとんど意識せず自然に利用できる
なぜこの違いを知ることが大切なのか?
IoTもユビキタスコンピューティングも、将来の生活を大きく変える技術です。
しかし、それぞれの特徴を正しく理解しておかなければ、どの技術がどう役立つのか分からず、誤解や混乱を招いてしまうこともあります。たとえばビジネスの現場では、IoT技術を導入しながらも、生活の利便性を高めるためにユビキタスの考え方も取り入れる必要が出てきます。
さらに、私たち一般の生活者も、今どんな技術が使われているのかを知っておくことで、より安全に便利にそれらのサービスを活用できます。
ですから、両者の違いをしっかりと把握し、どのような場面でどちらの考え方や技術が役立つのかを考えることが大切なのです。
IoTとユビキタスコンピューティングは似ているようで違いますが、意外とユビキタスコンピューティングの考え方は未来的で少し“魔法”っぽいんです。例えば、街の至るところにコンピューターが溶け込み、私たちが意識せずに使いこなしている…そんなイメージです。実は、その実現にはAIや分散システムなどの最先端技術が必要で、IoTの普及が大きな一歩なんですよ。だからIoTは未来のユビキタス生活の前提とも言えるんです。すごいですよね!





















