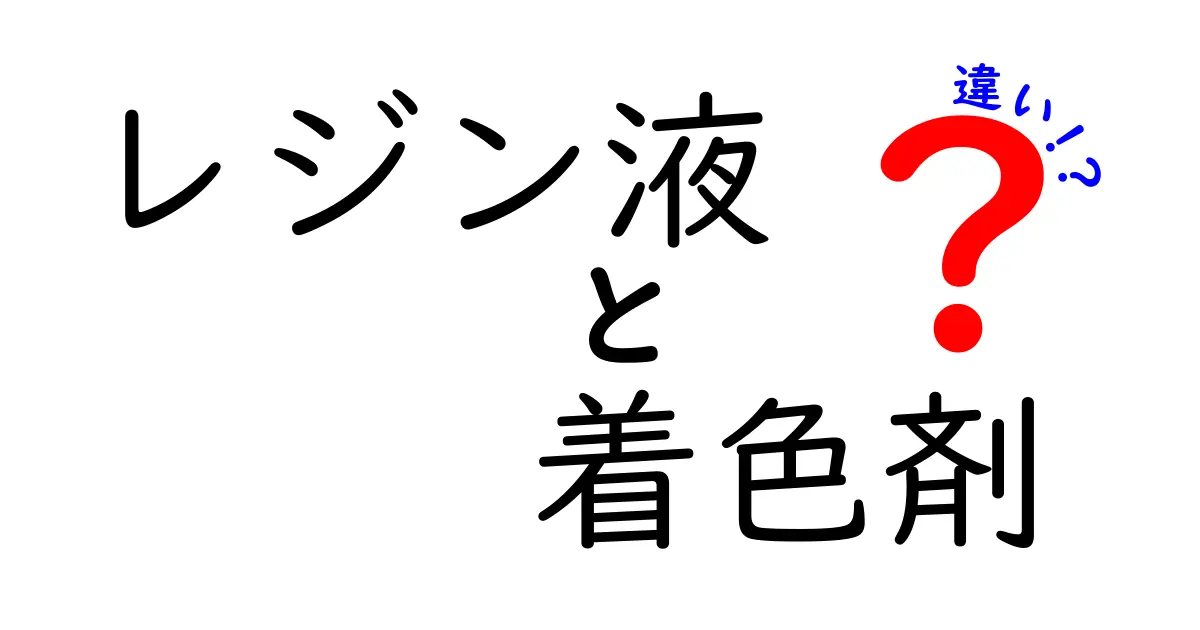

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
レジン液と着色剤の違いをしっかり理解するための基礎知識
まずはレジン液と着色剤の基本を区別して理解することが大切です。
レジン液は完成品の素材として型に流して固めることで硬い物体を作る材料であり、透明感や光沢が特徴です。家庭でのDIYやアクセサリー作りで広く使われています。
使用する時は、型に流す前に気泡を抜く作業や、硬化後の余分を削る作業が必要になることがあります。
着色剤はレジン液に色をつけるための添加剤で、粉状・液状・パウダー・ラメなど形状も様々です。発色の強さや透明度の調整、ムラの有無は使う材料のタイプによって左右されるため、初めての人は最初から複数の色を混ぜる前に透明のレジンでテストするのがおすすめです。
混ぜ方のコツとしては少量ずつ加え、すばやく均一に混ぜること、時間をかけすぎて泡が増えると仕上がりが曇ったり泡が目立つ原因になります。ここまでを押さえるだけで、作品の美しさや仕上がりの透明感が大きく変わります。
さらに、レジン液と着色剤を組み合わせる時には必ず推奨の混合比を守ることが重要です。濃い色を使うと露光時の光の通り方が変わり、暗い陰影が強く出ることがあります。濃色を使う時には薄く重ね塗りをするテクニックを取り入れると均一な発色を保てます。実際には作品の厚みや型の形状によって乾燥時間や硬化時間が多少変わるため、硬化後の仕上がりを見て追加で硬化させる判断が必要です。
ここから後半では、実際の違いを比較できる具体的なポイントと、選び方のガイドを提示します。表と実例を見ながら、あなたの作品に合った組み合わせを選ぶヒントをつかみましょう。
実践で分かる違いのポイントと選び方
このセクションでは、実際の作業段階での注意点と、道具選びのコツを詳しく解説します。
まず最初に――混ぜ方です。レジン液と着色剤を別々に計量し、混ぜるときは時間をかけすぎず手早く混ぜ合わせるのがポイントです。粘度が低めのレジン液は、着色剤を混ぜるときにも泡が入りにくく、透明感の高い仕上がりが期待できます。逆に粘度が高いタイプは、少しずつ混ぜるとムラが出にくくなります。
次に、硬化時間とペースト量の関係です。色が濃くなるほど乾燥に時間がかかる場合があるため、時間配分を頭に入れて作業を進めましょう。短時間で仕上げたいときは薄い色を数回重ねる方法も有効です。
また、発色のコツとしては、下地を透明なレジンで固めたあと、薄く色を敷くレイヤリングがおすすめです。
強い色を使いすぎると、透明度が落ちてしまい、光が透けるような美しさが損なわれます。
小さな模様なら粉状の顔料を少量ずつ混ぜ、微妙な濃淡を楽しむのがコツです。大判の作品では透明度を保つことを常に意識しましょう。
また、仕上がりの美しさを左右するのは温度と湿度です。室温は25度前後、湿度は40〜60%程度を目安にすると、固まる速度と表面のツヤが安定します。
この基本を守れば、初心者でも失敗を減らし、楽しく作業ができるはずです。
最後に、作品に適した着色剤のタイプを選ぶ判断材料を一覧にします。
以下の表は、代表的な着色剤の特徴とおすすめ用途をまとめたものです。
作業の前に必ず手元に準備して、スムーズに進めましょう。
| タイプ | 特徴 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| 粉末状 | 透明度を保ちやすく、細かな発色が得意 | 淡い色出し、透明感を重視するデザイン |
| 液状 | 混ざりやすく発色が鮮やか | 濃い色やはっきりしたアクセント |
| パウダー | ラメ効果やパール感を出しやすい | 煌めきのある作品や立体感を強調する場合 |
着色剤についての小ネタ。実は同じ色でも粉状と液状で発色の仕方が全く違います。粉状は水に溶けにくい分、ゆっくりとムラなく混ぜやすい一方、透明感を保ちつつ淡い色を作るのに向いています。一方液状はすぐ馴染み、濃い発色を出しやすいので深い色を一発で表現するのに適しています。ただし濃い色は透け感を失いやすいので、薄い下地を作ってから重ねると美しく仕上がります。結局は用途と作品のイメージ次第で使い分けるのがコツ。デザインを決めるときはまず試し塗りを数回行い、色の重ね方を体で覚えると失敗が減ります。





















