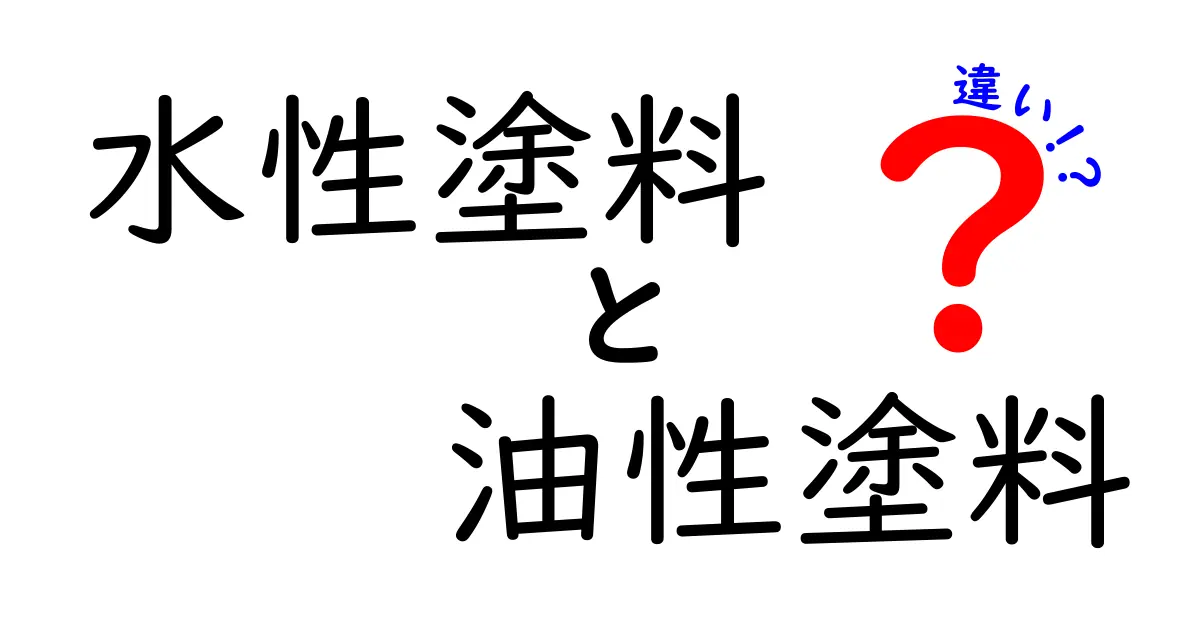

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
水性塗料と油性塗料の違いを徹底解説:どちらを選ぶべきか?
水性塗料と油性塗料の違いを知ると、家具の塗装、壁の塗り替え、外装のメンテナンスなど日常のDIYがぐっと楽になります。水性塗料は主成分として水分散性樹脂や水を使い、溶剤の臭いが少なく、指触乾燥時間が短いのが特徴です。
一方の油性塗料は有機溶剤を使うため、塗膜の強さや耐水性が高い反面、臭いが強く、拭き取りや道具の手入れに溶剤が必要です。
この違いは、作業場所の換気や使う素材によって大きく選択を左右します。室内での作業や子ども部屋の家具など、臭いと有害物質の心配がある場所では水性を選ぶと安心です。
ただし、屋外の木部や金属部、長期間の耐候性を求める場合には油性の方が適していることが多く、耐久性と美しさのバランスをとるためには用途別の選択が欠かせません。
ここで覚えておきたいのは、水性は手軽さと環境配慮を重視、油性は耐久性と仕上がりの重視、という基本軸です。
さらに、製品ごとに“耐水性・耐候性のレベル”“乾燥時間の目安”“再塗装の容易さ”“清掃に使う道具の洗浄方法”といった数値的な指標が異なります。
初心者の方は、室内で使う家具や壁には水性を中心に、外部の木材や金属には油性を補助的に選ぶと失敗が減ります。
最後に、購入前には必ずVOCの含有量、使用可能な環境条件、換気の要件、乾燥時間の目安を製品ラベルで確認してください。
水性と油性の基本的な違い
水性と油性の違いをさらに詳しく見ると、主成分、臭い、乾燥時間、清掃、耐久性、環境影響、用途の七つの視点で大きく変わります。
・主成分は水性が水分散性樹脂、油性が有機溶剤系樹脂
・臭いは水性が低め、油性は強め
・乾燥時間は水性が速い、油性は遅い
・清掃は水で洗える、油性は溶剤が必要
・耐久性は用途次第で差が出る
・環境影響はVOCの量・成分の違いに左右される
・用途は室内・家具・壁など水性、外装・木部外部・金属部など油性の傾向が強い
水性塗料の魅力は、まず手軽さと環境へのやさしさです。初めて塗装に挑戦した日のことを思い出しますが、水で道具を洗える手軽さは大きな安心材料でした。匂いが穏やかで、換気の負担も小さいため、夏の日の室内作業でも気軽に始められます。さらに、失敗してもやり直しが比較的簡単で、色の調整もしやすい点もポイントです。環境への配慮も忘れず、子ども部屋の安全性にも良い影響があります。





















