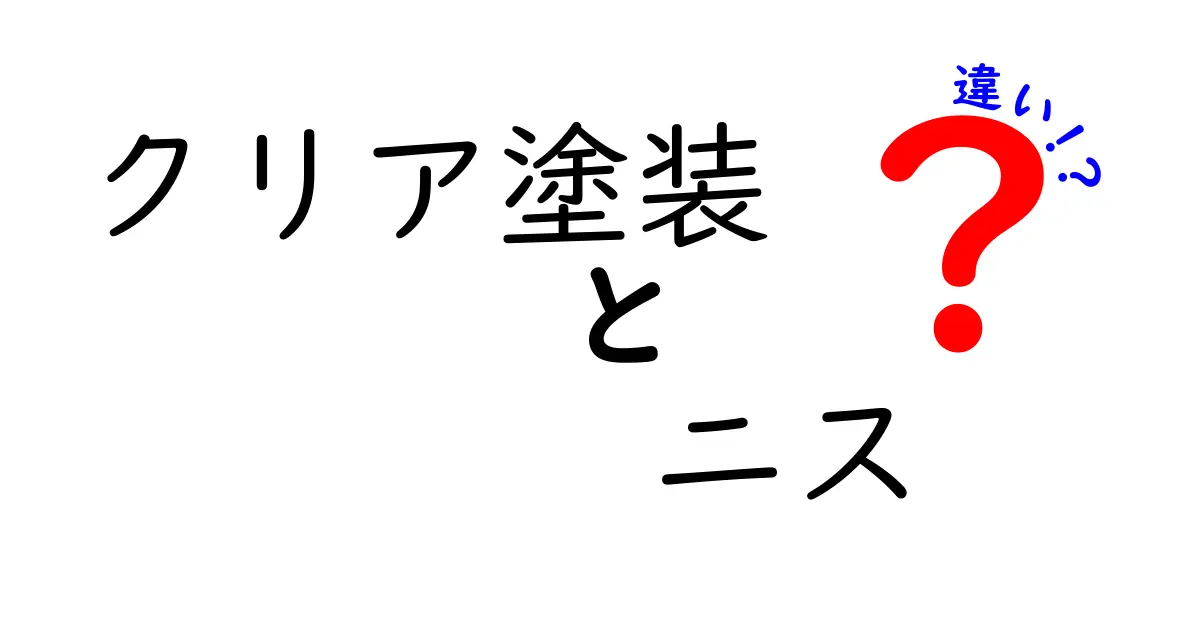

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クリア塗装とニスの違いを理解するための総論
クリア塗装とニスは、木材の表面を守る基本的な方法です。どちらを使うかで、見た目の印象や耐久性、手入れの頻度が変わります。まず前提として覚えておきたいのは、木材は呼吸を続ける素材であり、水分を吸ったり放出したりします。その水分の動きを妨げすぎないことが大切です。
クリア塗装は、透明な膜を作り、木目を活かしつつ保護します。
ニスは、硬い膜を作って水や傷への耐性を高めますが、光沢と厚みが出やすく、時には木の呼吸を少し制限することもあります。
用途の目安としては、室内の家具や床で木目を楽しみたい場合にはクリア塗装が向くことが多く、長期間の耐水性を重視する場所にはニスが適していることがあります。
さらに、作業性・安全性・予算も重要です。
これらを踏まえた「選び方のコツ」は、目的と場所を最初に決めること、次に塗膜の厚さと乾燥時間を確認すること、最後に使う材料の環境への配慮(臭い・VOCなど)を考えることです。
木の美しさを活かしつつ、しっかり守るためには、これらのポイントを押さえることが大切です。
クリア塗装とは何か?
クリア塗装は、木の表面に薄い膜を作って保護する塗装の一種です。透明なので木の色や木目をそのまま楽しむことができます。主な成分は樹脂と揮発性の溶剤で、乾燥して膜を作る仕組みです。
膜の厚さは塗布回数や重ね方で変わり、一般的には数十ミクロン程度の薄さです。膜は柔らかく、衝撃を受けても比較的割れにくい特徴を持ちます。
【メリット】木目を隠さず美しく見せる、施工が比較的簡単、初期コストが低い。
【デメリット】傷が付きやすい環境では、傷跡が目立つことがある、長期の水や薬品には弱くなることがある。
室内の家具や床、船舶のデッキなど、木の表情を大切にしたい場所に適しています。
ニスとは何か?
ニスとは、木材を保護するための厚みのある膜を作る塗料のことです。種類としては主に溶剤系と水性系があり、それぞれ特徴が違います。
溶剤系は深い光沢と硬さが出やすく、耐水性も高い一方、強い臭いと換気が必要です。水性系は低臭で扱いやすいですが、光沢が控えめで経年変化が出やすい傾向があります。
いずれも乾燥後には硬い膜を作るため、傷が付きにくく、耐水性も高いのが強みです。
使用場面としては、室内の家具・床・棚など、長く美観を保ちたい木製品に向いています。定期的なリタッチで長期の美観を維持できます。
似ている点と違う点を整理してみる
似ている点は、どちらも木材を保護し、外部の刺激から守る点です。違う点は、仕上がりの見え方と耐久性、そして使い勝手です。
以下の表で要点を比べてみましょう。
友だちとDIYの雑談風に話してみます。ニスって木を守るだけでなく木の色を深くしたり光をどう反射させるかも選べます。友だちが言いました――
「ニスは匂いが強いから換気が大事だよね」
そうだね、というと、私たちは水性と溶剤系の違いを、塗布の厚さと乾燥時間の観点から考えます。水性は扱いやすく匂いも控えめ、しかし光沢が落ちやすいことがある。溶剤系は深い光沢と強い耐水性を得られるが換気が必須。こうした違いを知ると、学校の工作や日曜大工での木の仕上がりが確実にアップします。





















