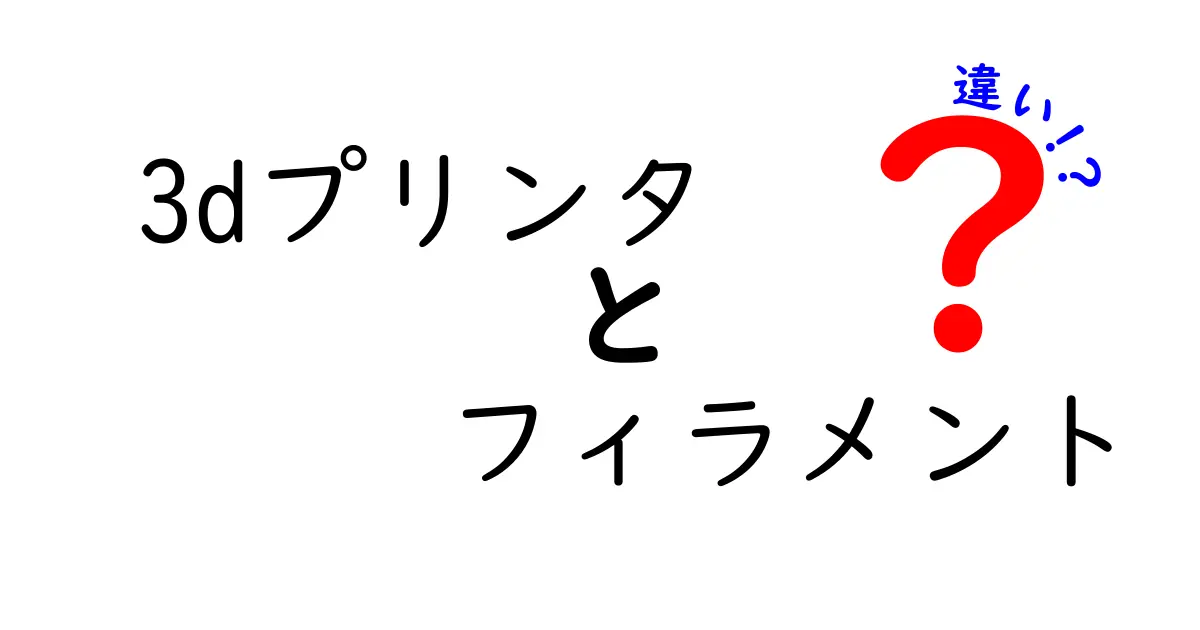

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3Dプリンタのフィラメントの違いを理解する基本ガイド
このガイドは3Dプリンタで使われるフィラメントの違いを理解するための基本ガイドです。材料の性質はプリンタの挙動と仕上がりに大きく影響します。
PLAは温度が低く匂いが穏やかで扱いやすい一方、ABSは耐熱性と衝撃性が高い反面反りが起きやすいという特徴があります。
PETGはこの二つの中間に位置し、強度と耐薬品性のバランスが良いと評価されています。
初心者はまず自分の作りたいものの用途とプリンタの環境を整理してから材料を選ぶと失敗が少なくなります。
この後で、各材料の具体的な性質と実際のプリントにどう影響するかを、日常の例とともに詳しく見ていきます。
さらに最後には各材料を比較する表と、選び方のコツも紹介します。
それではいよいよ各フィラメントの特徴へ進みましょう。
まずは全体像として、PLAは初心者向けの第一候補として最も適しており、ABSは耐熱部品や強度を重視する方向け、PETGは両者の中間の性質を持つ万能型として位置づけられます。
この三つを軸に考えると、どんな用途に適しているかの判断がしやすくなります。
なお、作業環境やプリンタの機能に応じて微妙な調整が必要になる点にも注意してください。
PLAの特徴と使いどころ
PLAはポリ乳酸という生分解性の材料から作られています。
熱変形温度は比較的低く180度前後から印刷可能で、ノズル温度は180〜210度が目安です。
床面の安定性や排気の匂いも穏やかで、家庭内の机の上プリンタでも扱いやすいのが魅力です。
PLAは初心者向けの代表格で、色の再現性が高く仕上がり表面が滑らかに出やすいのが特徴です。
しかし、耐熱性は低く長時間高温になる環境や機械的な負荷が大きい部品には向きません。
ぼくらの日常の模型作りやプロトタイプ作成には最適ですが、機能部品としての長寿命を期待する場面は別の材料を検討する必要があります。
PLAの利点はいくつかの具体例でよく分かります。例えば小物のケース、装飾用のモックアップ、教育用の部品など、形状の再現性と細かなディテールを高いレベルで確保したい場合に適しています。
印刷時のトラブルも比較的少なく、初回の学習曲線を穏やかにしてくれます。
ただし耐久性や耐熱性が不足する場面では別材料に切り替える判断が必要です。
PLAの購入時のコツとしては、保管環境を乾燥させておくこと、湿気を避けること、プリンタのファームウェアとノズルの清掃を定期的に行うことです。
これだけで仕上がりの安定性が大きく向上します。
ABSの特徴と使いどころ
ABSは耐熱性と衝撃強度が高く、機能部品や耐熱を要する用途に向いています。
しかしその分反りや収縮が起きやすく、印刷時にはベッドの温度を90〜110度程度に保つ必要があります。
また、印刷時には蒸気が出ることがあり、換気が重要です。
ABSは強度重視の部品には有利ですが取り回しは難易度が上がります。
プリンタの封じ込めやカーボン系のパーツを作る際にも適していますが、最初はPLAから始めて段階的に移行するのが良いでしょう。
ABSの実用場面の例としては、機械部品のプロトタイプ、耐熱ケース、耐久性を求める工具の一部などが挙げられます。
エポキシ系のコーティングや後処理を施すことで、外観と機械的特性をさらに高めることが可能です。
ただしDIY環境ではホコリや匂い、床下の反りなどのトラブルが起きやすい点を忘れずに対策を講じてください。
ABSを安定させるコツとしては、プリンタのベッド温度を適切に管理すること、周囲の換気を確保すること、プリント中の冷却を過剰に行わないことが挙げられます。
設置場所の温度安定性も重要で、急激な温度変化を避ける工夫が有効です。
PETGの特徴と使いどころ
PETGはPLAとABSの良い点を取り入れた素材で、高い耐久性と柔軟性のバランスを持ちます。
印刷温度はPLAよりやや高めで、180〜240度程度が目安です。
水滴のような鏡面仕上げが出やすく、表面の滑らかさと透明感を両立させやすいのが特徴です。
耐薬品性も向上しており、工具や実用品のプリントにも適しています。
一方で粘着性が高い素材なのでプリンタのノズル詰まりを防ぐため、フィラメントの乾燥と適切な保存が重要です。
総じて、実用性と扱いやすさのバランスを取りたい人に特におすすめです。
PETGは強度と柔軟性の適切なバランスを保ちながら、加工性も良い点が魅力です。
表面仕上げは滑らかで、少ない後処理で実用品として使用できるケースが多いです。
ただし湿度の影響を受けやすい特性があり、長時間湿気を含んだ状態で保管するとプリント品質が落ちることがあります。
そのため、乾燥剤を入れた密閉容器で保管することをおすすめします。
その他のフィラメントと用途のヒント
TPUやNylonなどの素材はPLA/ABSより難易度が高いですが、弾性が必要な部品や高い耐摩耗性が求められる部品には強い味方になります。
TPUは柔らかく曲げに強い特性があり、靴の部品やケースのストラップなどに向いています。
Nylonは耐摩耗性と強度が高く、機械部品やギアにも使われますが、水分を吸いやすく印刷条件が難しい点に注意です。
これらの素材を使う場合は、機械設定の細かな最適化と適切な保管が成功の鍵になります。
フィラメント選びのポイントとお手入れのコツ
まずは作りたいものの用途と求める特性を整理します。
強度重視ならABSやPETG、形状の再現性と色の美しさを重視するならPLAを検討します。
柔軟性が必要ならTPU、適切な耐熱性を求めるなら耐熱性の高い材料を選ぶなど、用途別の判断が大切です。
次にプリンタの環境を整え、ノズル温度とベッド温度、冷却の有無を適切に設定します。
乾燥と保管にも気をつけ、湿気を避けることで詰まりや弱体化を防げます。
表面仕上げの好みや、後加工の難易度も材料選びの大事な要素です。
フィラメント比較表
PETG についてちょっと雑談風に深掘りしてみよう。僕が初めてPETGを使ったとき、PLAより温度を少し上げても反りが少なく、ABSほど強硬には出てこない感触だった。中間の性質が魅力で、実用品を作るときの失敗が減ると感じた。湿気には要注意で、乾燥保存がキモ。柔軟性と耐久性のバランスが取れるので、透明感のある部品を試したいときにもおすすめだ。友人と話していてもPETGは“これ一択で済む場面が多い素材”と評価されることが多い。僕たちは日常の小物づくりで、強度と美観の両立をどう実現するかをこのPETGで一歩近づけられると思う。
前の記事: « 木型と金型の違いを徹底解説!試作から大量生産までの実務ガイド





















