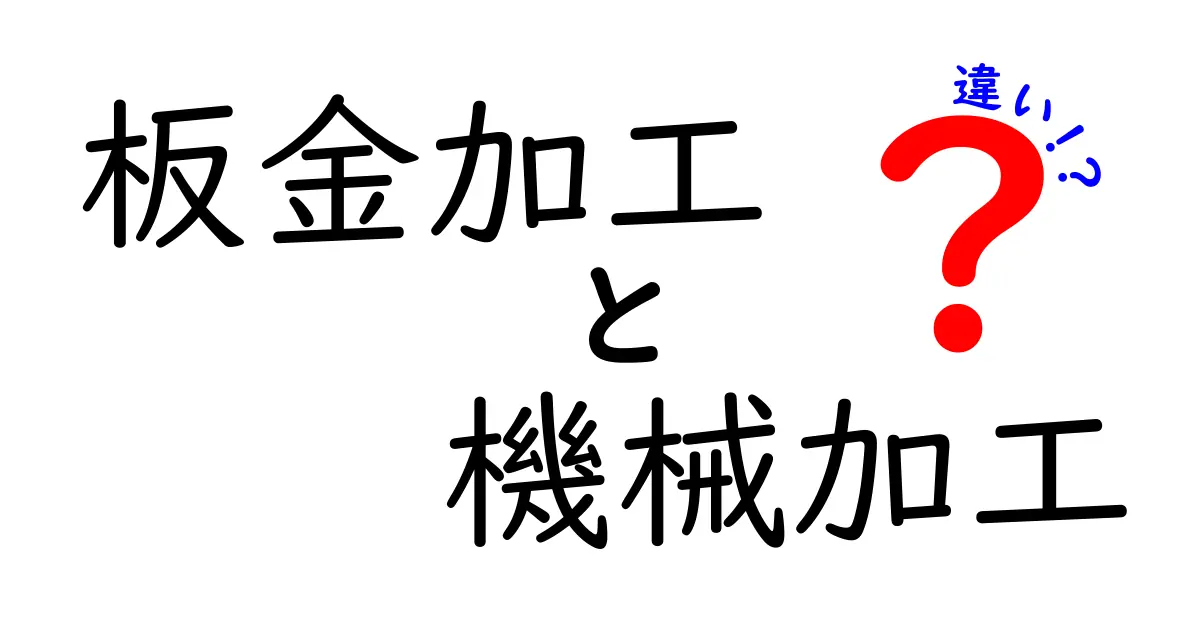

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
板金加工と機械加工の違いを徹底解説!初心者にも分かる使い分けのコツと実例
このテーマは工作・製造の世界でよく取り上げられます。板金加工と機械加工は、どちらも金属を「形」にする作業ですが、目的・材料・工具・工程・仕上がりの公差・コスト感が大きく異なります。初心者の人には、まず「対象となる材料」と「必要な精度・量産性」を想像すると理解が近道です。板金加工は薄い板を使って曲げたり切断、絞りを行い、部品の外形を決める工程が中心です。対して機械加工は金属を削り、切断して部品を作るプロセスです。
この2つを混同してしまうと、設計段階での選択ミスが生じ、後工程での再加工や不良品が増えるリスクがあります。たとえば車のドアや航空機の外板のように大きな面積を持つ部品は板金加工が得意です。一方で高精度のねじ山や軸受けを持つ部品は機械加工の比重が高く、寸法公差・表面粗さ・位置決めの再現性が重要になります。
このページでは、まず両者の基本を整理し、次に実際の加工現場での違い、そして設計・発注時にどう使い分けるべきかを具体例とともに解説します。読み終わるころには、あなた自身が「どちらを選ぶべきか」を判断できるようになっているはずです。
ポイントとして覚えておきたいのは、板金加工は主に薄板を曲げ・切断・絞りで形を作る作業、機械加工は素材を削って寸法を整える作業だという点です。さらに、コスト感や納期、加工難易度、部品の最終用途を総合的に考える必要があります。
板金加工とは?
板金加工は薄い金属板を扱う加工の総称で、主に折り曲げ(ベンディング)、絞り、切断、穴あけ、溶接、表面処理などの工程を含みます。使われる材料は鉄板、アルミ、鋼板、ステンレスなどの薄さ0.3〜3mm程度のものが中心です。代表的な機械はプレスブレーキ、レーザー切断機、パンチングプレス、溶接設備などです。板金加工は大量生産に適しており、同じ形状の部品を複数枚作る場合にコスト効率が高い点が魅力です。例えば車の内装パネルや家電の筐体など、外見と機能の両立が求められる部品に適しています。
公差は機械加工に比べて緩いことが多く、設計段階での余裕を持たせることが重要です。
機械加工とは?
機械加工は、鋼やアルミニウムなどの素材を削ったり、穴を開けたりして部品の寸法を厳密に整える加工です。主な工程には旋削、フライス加工、穴加工、ねじ加工、表面処理前の仕上げなどがあり、CNC機械が中心となっています。材質の揃え方、切削条件、工具の選択、スピンドル回転数、進み量などを組み合わせることで、公差±0.01〜0.05mm級の高精度を実現します。機械加工は少量〜中量の量産に強く、複雑な形状や微細な穴・ねじ加工が必要な部品に適しています。部品の再現性が高い点も大きな利点です。
ただし、材料の厚さや形状によって加工性が大きく変わるため、設計時には「薄く・ただし強く・安価に」を同時に満たす妥協点を探す必要があります。
具体例で見る違い
例えば、車のドアの外板は大きな一枚物を効率よく作る必要があり、板金加工の得意分野です。薄い板を広く曲げて大きな面を作ることで、コストを抑えつつも外観を美しく仕上げられます。
一方で、エンジンのシリンダーブロックのように複雑で高精度な寸法が要求される部品は機械加工で仕上げます。穴の位置ずれが許されず、表面粗さも厳しく管理されるため、±0.01〜0.05mm程度の公差を確保します。両者の使い分けは、設計段階での材料選択・形状設計・コスト計算に大きな影響を与えます。
また、混在するケースも多く、一部を板金加工で作り、他の部分を機械加工で最終仕上げするハイブリッド構成も一般的です。
どう使い分ける?選び方のポイント
設計段階での基本的な判断は「形状の大きさ・ねじれ・曲げの有無・量産性・公差の厳しさ」です。
大きな外形を薄い板で作りたい場合は板金加工を第一候補にします。凸凹のある複雑な3次元形状を高精度で作りたい場合は機械加工が有利です。
コストとリードタイムを同時に考えるときは、部品を構成する面積と複雑さを分解して、どの部分を板金、どの部分を機械加工で作るのかを検討します。
結論としては、部品全体の「形」「大きさ」「精度」「生産数量」を総合的に見て、最適な加工方法を選ぶことが重要です。設計時の早い段階で加工方法を決定するほど、納期とコストを抑えられます。
板金加工の話題を友だちと雑談する形で深掘りします。例えば、私が工場見学で見た、薄い鉄板を折り曲げて車のドアの外板を作る作業の場面。すると友だちが「どうして同じ板金でも場所によって強度が変わるの?」と尋ねる。そこで私は答えます。「板の厚さ、材質、曲げ半径、そして層の重ね方が影響します。実は、曲げ加工は板の伸びと癖を計算して設計する必要があり、同じ形状でも木材のように自由に曲がるわけではないんだ」と。そういった会話を通じて、板金加工が「設計と実際の加工技術の橋渡し役」であることが分かる。現場では技術者がデータを読み解き、最適な加工条件を選定します。身近な例として、家電のケースの美しい表面を保つために、後処理と塗装の組み合わせも重要で、これは板金加工の適用範囲を広げる工夫の一つです。
前の記事: « 切削と金型の違いを図解で完全解説!初心者にも伝わるポイント





















