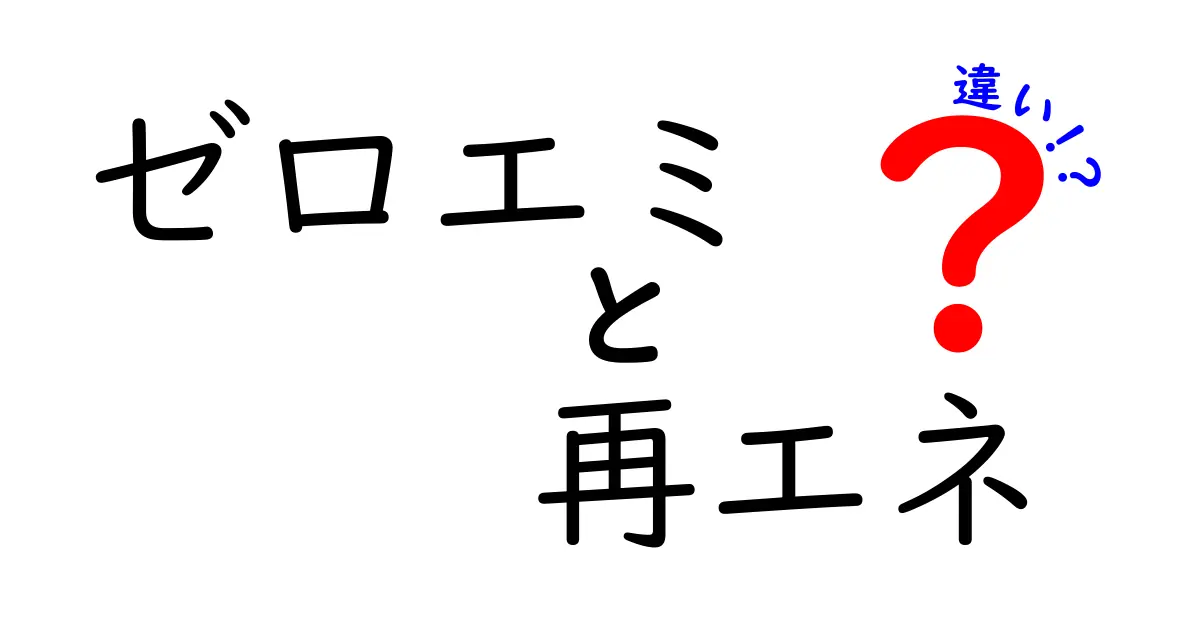

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ゼロエミと再エネの基本を学ぼう
ゼロエミと再エネは、地球を守るために私たちの暮らしを見直すときの核心ワードです。まず大事なことは、ゼロエミという言葉の意味を正しく理解することです。ゼロエミとは“排出をできるだけ減らし、どうしても出てしまう分を補う形で実質0に近づける”という考え方を指します。ここでの“実質0”には、排出を減らす努力と、排出を吸収・オフセットする仕組みの両方が含まれます。つまり、ゼロエミはゴールを決めるための戦略であり、具体的な行動の輪郭を描くものです。これに対して再エネは、エネルギーの作り方そのものを指す言葉です。太陽光・風力・水力・地熱など、自然の力を使って電気を生み出す方法が再エネです。再エネは「エネルギー源の種類」を示します。どちらも地球温暖化対策に深く関わる話題ですが、意味する範囲が違うため混同しやすいポイントでもあります。
日常生活では、ゼロエミは目標設定の考え方、再エネは使う電力の原材料の話として捉えると理解が進みます。私たちが電気を使うとき、単に「安いから選ぶ」だけではなく、どのようなエネルギー源で作られた電力を選ぶのか、そして排出を減らす取り組みに自分がどう関与できるのかを意識することが大事です。政府や自治体の取り組み、電力会社の料金プラン、私たちのライフスタイルの選択が結びつくことで、ゼロエミと再エネの関係性は身近になります。
ここまでの理解を土台に、ニュースで話題になる「ゼロエミが進んでいる」「再エネの発電量が増えた」といった話題を見たとき、いくつかの質問が自然と浮かぶはずです。例えば「ゼロエミはどうやって達成されるのか」「再エネはどう安定供給を支えるのか」「私たちの選択がどこまで影響するのか」といった疑問です。こうした問いに答えるには、まず“排出の量を減らす方法”と“発電の仕組みを変える方法”を別々に考えることが有効です。前提を分けて考えると、難しい用語が頭の中で混ざらず、実生活の決断へつながりやすくなります。この先の章では、それぞれの概念をもう少し詳しく見ていきましょう。
ゼロエミとは何か?
ゼロエミとは、地球の温室効果ガスを「出さない・出しても極力減らす・減らした分を別の形で相殺する」という連携で、最終的に排出量を実質ゼロに近づけることを目標にした考え方です。家庭や企業が自分たちで減らせる分を減らし、どうしても出てしまう分をオフセットする仕組みを取り入れるのが基本的な進め方です。ここには、エネルギーの効率化や新しい技術の導入、そして社会全体の動きが絡んでいます。具体的には省エネ家電の利用、建物の断熱性能を高める工夫、電力の調達で再エネ割合を高める選択、そして木や海など自然の力を使って排出を吸収する取り組みが挙げられます。これらの要素が組み合わさることで、個人の行動から企業の戦略、さらには国の政策へと波及していくのです。
ただしゼロエミは完璧な状態を意味するわけではなく、現実には技術の進歩と社会の変化が同時進行で進む過程を示しています。だからこそ、私たちは毎日の選択を少しずつ変えることが大切です。例えば通勤の方法を変える、家のエネルギー源を再エネ由来の電力に切り替える、エネルギーをムダにしない生活を心掛けるといった小さな一歩が積み重なると、ゼロエミの実現に近づいていきます。
再エネとは何か?
再エネは、太陽光・風力・水力・地熱など自然の力を使って作られる電気を指すエネルギーの総称です。これらは化石燃料のように限りがなく、環境負荷を減らす効果が期待されます。再エネの良い点は、資源が枯れず、長い目で見ればエネルギーコストの安定化にもつながる可能性があることです。一方で課題もあります。発電量は天候に左右されやすく、時間帯によって出力が変わること、設置場所や送電網の容量の制約、初期投資の大きさなどが挙げられます。これらを解決するためには、貯蔵技術の発展やスマートグリッドといった新しい仕組み、そして発電と需要をうまく連携させる工夫が必要です。再エネを普及させるには、技術革新とともに社会制度の整備も不可欠です。
また、再エネは“電力の作り方の話”であり、ゼロエミの実現に向けて重要な役割を果たします。電力会社の供給計画、自治体のエネルギー戦略、私たち消費者の選択が連動して、どれだけ再エネを増やせるかが決まっていくのです。再エネを身近に感じるには、ニュースで出てくる新しい設備の話だけでなく、家庭向けの再エネプランや学校・職場での省エネ運動といった具体的な取り組みを知ることも大切です。
違いを日常生活で見るコツ
ゼロエミと再エネの違いを日常に落とし込むには、まず「意味の使い分け」を意識することがポイントです。ゼロエミは排出を抑えるための目標の考え方であり、再エネはエネルギーの作り方そのものです。これを自分の生活設計にどう反映させるかが鍵になります。たとえば、電力を選ぶときには「再エネ由来比率が高い電力」を選ぶことで、間接的に再エネの普及を応援することができます。また、省エネ家電を使い、待機電力を減らすこともゼロエミの実現に近づく道です。加えて、住居の断熱性を高めると、冬の暖房や夏の冷房に要するエネルギーを減らせます。こうした具体的な行動は、長い目で見て自分の家計にも優しく、地球にも優しい選択です。
日々の生活の中で「どの選択がどのように排出量を減らすのか」「再エネの導入がどのくらい進んでいるのか」を知るには、家計簿のようにエネルギーの使い道を記録する習慣をつけると良いでしょう。電力会社のサイトには、再エネの割合や発電分布を示すグラフが公開されています。時々、ニュースで耳にする
今日は友だちと放課後にエネルギーの話題で盛り上がったんだけど、ちょっとした実験を思いついたんだ。家の電力を再エネ由来100%のプランに切り替えたとき、月末の電気代がどれくらい変わるかを、家族と一緒にチェックしてみる計画。もし「再エネは高い」というイメージがあるなら、それが実際にはどういう理由でそう感じられるのか、技術的な壁や制度の話も交えながら説明していくつもり。エネルギーの話は難しそうに聞こえるけれど、私たちの選択が地球の未来を作る一歩になる、そんな実感を得られたらいいなと思う。ゼロエミという大きな目標を、身近なものに落とし込むコツは、削る努力と作る力の両方を同時に意識すること。私たちにできる小さな変化が、やがて大きな変化へとつながるはずだよ。





















