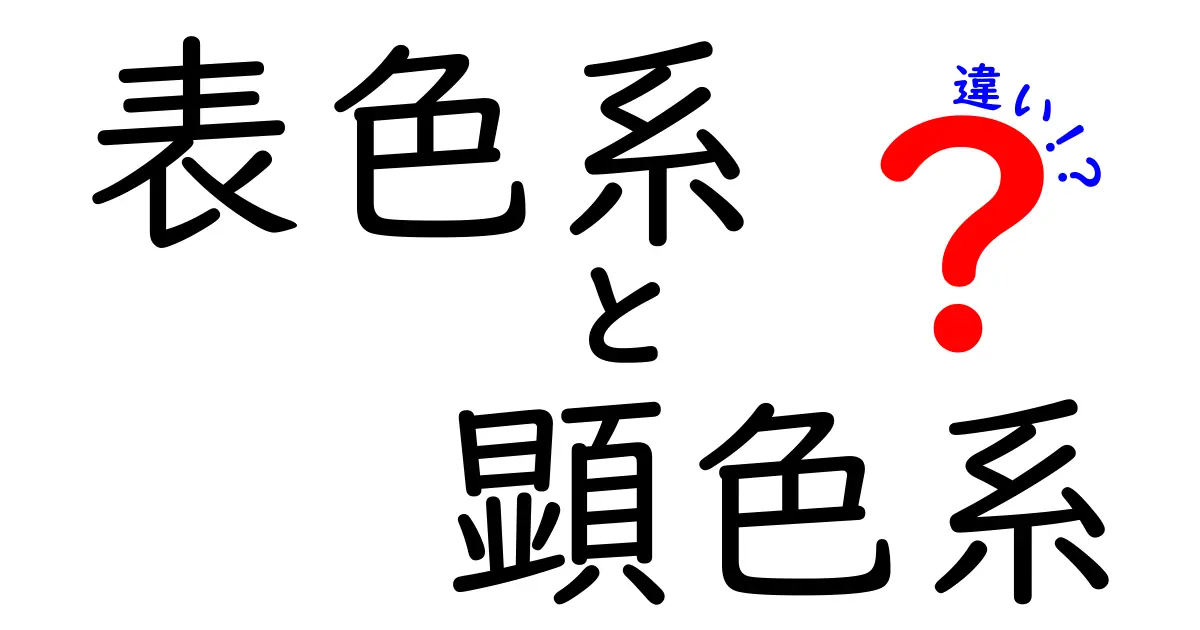

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに—表色系と顕色系の違いを知る意義
色には見え方を決めるしくみが二つあり、それぞれ違う名前と役割があります。日常では色を「赤い」や「青い」といった名前で覚えますが、デザイナーや技術者は色を数字や概念として扱うことがあります。ここで紹介する表色系と顕色系は、色をどう表現し、どう使い分けるべきかを判断するための道具です。
例えば同じ赤色でも照明の色温度が変われば見え方は変わります。この現象は metamers の一つの例ですが、表色系と顕色系の違いを知ると理由がわかります。
この文章は中学生にも理解できるように、身近な事例を用いながら丁寧に解説します。これから紹介する概念を押さえるだけで、印刷物の色味チェックやスクリーンの色合わせ、照明設計の際にも役立ちます。
表色系とは何か
表色系とは色を数値や座標で表現する方法の総称です。実務ではデジタル機器の色空間である sRGB、印刷の CMYK の色表現、そして人間の知覚を理論化した Lab や LCh などが使われます。
これらは色を「数として扱える」点が特徴で、色の再現性が高く、デバイス間の色のずれを最小限にすることが目標です。
表色系の座標には Hue(色相)と Value/Lightness(明度)、Chroma/Saturation(彩度) などの考え方が含まれ、よく使われるのは Lab という人間の見え方に近い指標です。
また表色系は測定機器や標準光源の影響を受けますが、同じ条件下であれば再現性が高く、デザインの一貫性を保ちやすいのが特徴です。重要な点として 数値を揃えるだけで色を管理できる点と、デバイスの特性に依存することがある点を覚えておくと混乱を防げます。
顕色系とは何か
顕色系とは色の“見え方”そのものを表現する系統のことです。照明の色温度や観察者の視覚の特徴に影響を受け、同じ色でも見え方が変わる現象を数理的に整理します。ここで重要なのは dominant wavelength(主波長)や purity(純度)といった perceptual な指標です。
顕色系は色を外見として扱うため、光源が違うと印象が大きく変わるメタマーの問題を解く助けになります。
代表的な考え方には CIE の色見えモデルや最近の Color Appearance Model などがあり、色を「ある条件下でどう見えるか」を前提に設計します。
日常的には、部屋の照明が白色 LED か電球色かで絵の雰囲気が変わるような体験がこれに近いです。顕色系の強みは 見え方の一貫性を保つことが難しい場面でも、照明と観察条件を考慮して色を表現できる点です。
違いの要点と理解のコツ
表色系と顕色系の基本的な違いを一言で言うと 「数で管理するか、見え方で管理するか」です。表色系は色を数値化して再現性を重視します。
顕色系は光と観察者の条件を前提に、色が実際にどう見えるかを扱います。これらは相補的で、同じ色を使う場面でも使い方が変わります。デザインの現場では、まず表色系で正確な色の基準を作り、次に顕色系を用いてどの照明下でどのように見えるかを検証します。 metamers の問題を避けるには両方の視点を持っておくと安心です。
使い分けの実務例
印刷物やウェブデザインなど、再現性を最優先する場面では表色系を使います。
印刷では CMYK の色を Lab や LCh に落とし込み、現場の出力機で色を合わせます。その後、実際の印刷物で見え方をチェックします。室内の照明設計やギャラリー展示では顕色系の考え方が重要です。照明を LED か白熱灯に変えると、同じ対象物でも見え方が変わるため、来場者に伝わる印象を揃えるには光源を統一するか顕色系の見え方モデルを使って色を設計します。ここで大事なのは 場面ごとに基準を切り替え、両方の視点を組み合わせることです。さらに metamers が起きた場合の対処法を事前に用意しておくと現場対応が楽になります。
表と顕色系の違いを整理する簡易表
まとめとしての実務のポイント
表色系と顕色系は対になる概念です。
現場では、まず表色系で色の正確さを確保し、その色が実際にどう見えるかを顕色系で検証します。
照明の条件を変える場合には、色の見え方がどう変わるかを前もって想定しておくと、レイアウトや展示の雰囲気を崩さずに設計できます。
最後に覚えておくべき言葉は metamers です。 metamers とは異なるスペクトルの色が同じ見え方を作る現象のことで、これを理解しておくと色のトラブルを未然に防げます。
メタマーという言葉を知っていますか。夕暮れ時、同じ赤でも街灯の色が違うと看板の赤が少し変わって見えることがありますよね。これが metamers の典型です。私たちの目は、波長が異なる色を同じ“印象”として捉えることがあり、光源が変わると見え方も変化します。表色系はこの見え方の変化を厳密に扱うモデルで、顕色系はその見え方自体を評価する“日常の感覚”を数理で支える考え方です。ある日、友人と写真を撮っていて室内と屋外で同じシャツがどう映るかを比べたとき、表色系と顕色系がどう協力して色を説明できるかを体感しました。色の世界は、単なる色名だけでなく、光と観察条件の組み合わせで大きく変わる複雑さをもっています。だからこそ、場面に応じた見え方の理解が大切なのです。リズムよく色を扱うと、紙の上の色もスクリーンの色も、実際の印象に近づけやすくなります。
前の記事: « 明朝体と楷書の違いを徹底解説!中学生にも分かる図解つき





















