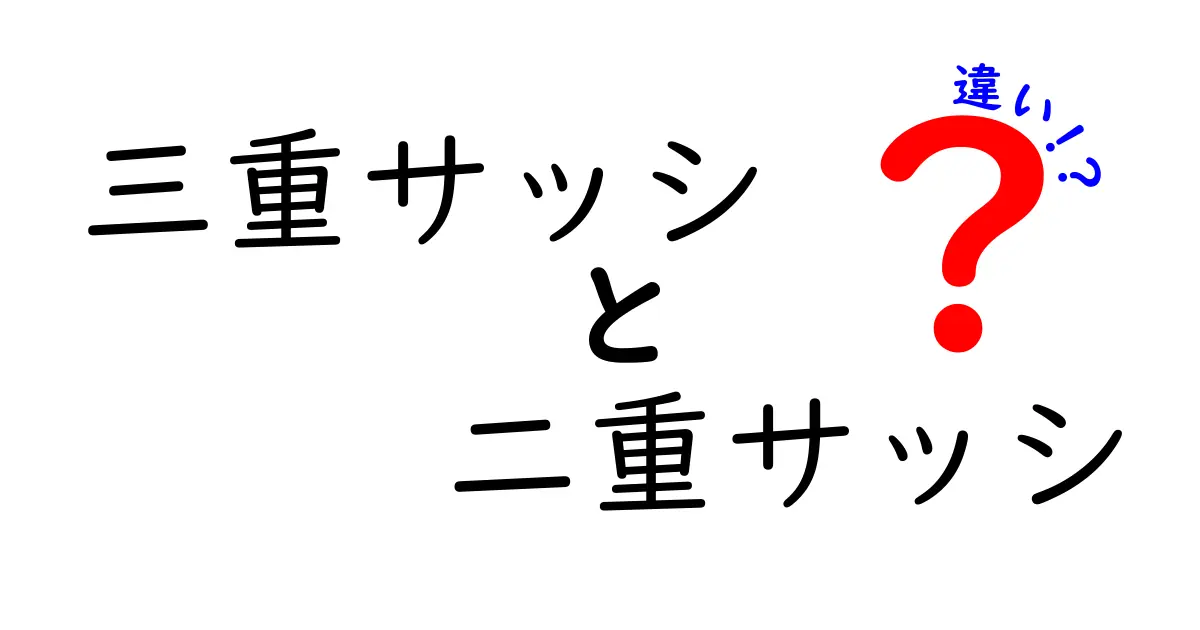

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
三重サッシと二重サッシの違いを理解するための基本
現代の住宅では窓の断熱性能を高める選択肢として三重サッシと二重サッシがよく比較されます。結論から言えば三重サッシはガラスが三枚、二重サッシはガラスが二枚という構造の違いですが、実際には枠の断熱材やスペーサーの材質、ガラスの厚さや中間空気層の幅などが大きく影響します。
つまり同じ「三重」と「二重」という言葉でも、メーカーやシリーズによって断熱性能の差は大きく変わるのです。
この章ではまず基本的な考え方を整理します。断熱性能は窓から逃げる熱量を抑える力のこと、実際にはU値や熱貫流率といった数値で表されます。
ただし家庭で実感するのは数値だけではなく、結露の有無、夏の熱に対する室内の涼しさ、朝の外気温の影響など複合的な要素です。
防音性能や結露対策、メンテナンスの難易度、そして初期投資と長期コストのバランスも大切です。
三重サッシとは何か
三重サッシは室内と外部を隔てるガラス層が三枚、間に空気層が二つある構造です。
中間の空気層は熱の伝わりを抑える役割を果たすため、冬の暖気を室内に逃がしにくくします。
実際にはガラスの厚さ、スペーサーの材質、枠の断熱性が結果としての断熱性能を決めます。
価格は二重サッシより高めになる傾向があり、重量が重くて窓枠自体の補強が必要になる場合もあります。
住まいの地域が極端な寒冷地であるほど効果を実感しやすい反面、設置工事が新築時に限られる場合もあるので計画段階での現地調査が重要です。
二重サッシとは何か
二重サッシはガラスが二枚、間に空気層が一つある構造です。
熱の伝わりを低減する力は三重と比べると劣る場合が多いですが、コストや施工の難易度では有利になることが多いです。
取り付け可能な枠の種類やサッシのグレードによっては、比較的短期間で交換が完了し、現場の影響も抑えられます。
二重サッシは結露抑制と防音のバランスが取りやすく、都市部の住宅や築年数の古い建物のリフォームにも適しているケースが多いです。
選ぶときには防音目的、結露の軽減、エネルギーコストの削減など、優先順位をはっきりさせることが大切です。
実際の選び方とポイント
窓の選択をする際には、まず自分の住まいの状況と生活スタイルを整理します。
寒い地域では断熱性の高い三重サッシの恩恵を受けやすいですが、比較的暖かい地域や換気を重視する家では二重サッシでも十分な場合があります。
ここからのポイントは以下のとおりです。
1 予算と長期コストのバランスを考える。
2 使用頻度の高い部屋や音が気になる場所は防音性能を重視。
3 結露対策は結露が多い季節に現れやすく、枠材の材質や通気性も影響します。
4 設置業者の経験と工事期間を確認。
5 実際の性能を現場のサンプルで確認することが大切です。
- U値の数値表示を確認する
- ガラスの厚さと中間膜
- 枠の断熱材と気密性
- 枠の取り付けられる重量
- 保証とアフターサービス
友達とリビングの窓リフォームの話をしていて、断熱性能の話題を深掘りしました。三重サッシと二重サッシの違いを理解するには、枚数だけで判断しないことが大事と伝えました。中間空気層の幅やガスの充填の有無、枠材の断熱性が体感温度を左右するからです。実際に私の家では予算の都合で二重サッシを選びましたが、冬の朝に感じる室温の違いは大きく、朝起きたときの寒さが和らぎました。色々なメーカーの比較表を見て、現場で見せてもらったサンプルの感触も選択に影響しました。





















