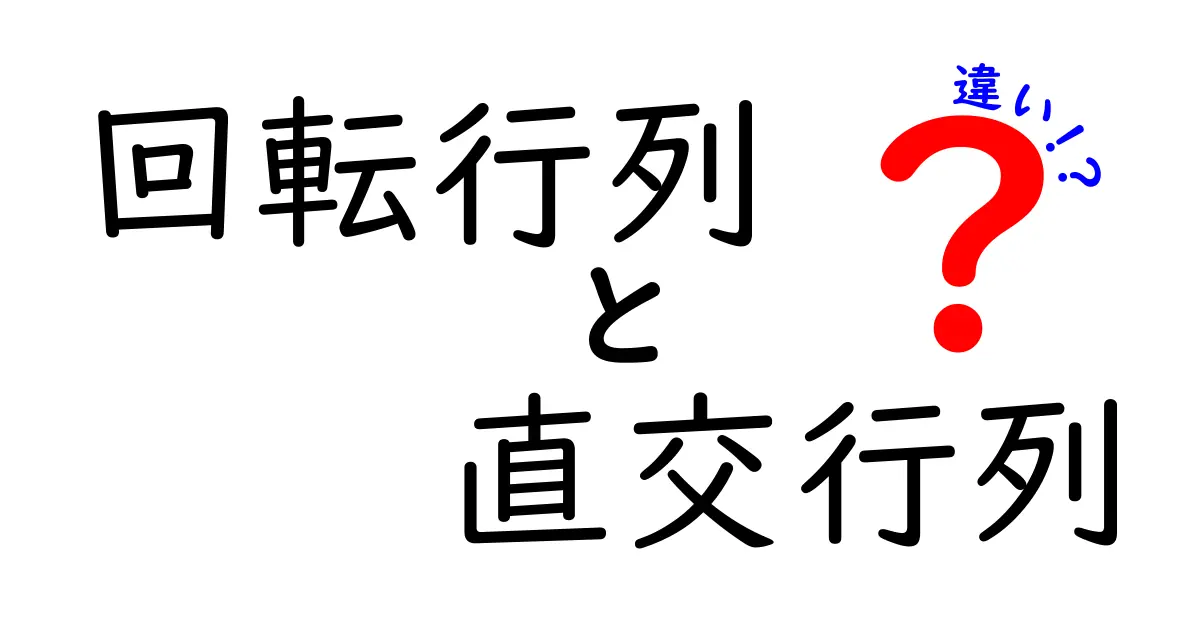

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに 回転行列と直交行列の違いをつかむコツ
回転行列と直交行列の違いを正しく理解するためにはまず用語をはっきりさせることが近道です。この記事では中学生でも分かるように優しく説明します。回転行列は文字どおり「回すための行列」です。ある角度θをとってベクトルをその角度だけ回転させる変換を数式で表すものです。2次元のときは cosθ -sinθ
sinθ cosθ の形をとります。この形が意味するのは、元の座標系に対して実際には x 成分と y 成分が cosθ と sinθ の組み合わせで新しい座標へと移るということです。回転は長さを変えず方向だけを変える変換です。ここで重要なのは 回転行列は直交行列のうち 特別なケースであり、通常は行列式が +1 になることです。これに対して直交行列は「転置と逆行列が同じになる」という性質をもつ変換の総称です。つまり長さを保つ変換であり、回転だけでなく鏡映しの反射を含む場合もあります。したがって 直交行列は回転行列を含む広い集合であり、回転以外に反射を含むものも存在します。これらの違いを押さえると、後でベクトルの変換を考えるときに迷うことが減ります。最後に、回転と直交の違いを一言でまとめると、回転行列は長さを保つ変換の中の特定の角度回転であり、直交行列は長さを保つ変換全体を表す集合だということです。
回転行列の基本と直交性の関係
回転行列の基本は、2次元では最も代表的な例が cosθ と sinθ を使った 2x2 行列です。この行列をベクトルに掛けると、ベクトルを角度 θ だけ回転させた新しい座標が得られます。具体的には同じ長さの点が円周上を動くように変換され、原点を中心とした回転です。2次元だけでなく3次元以上の空間でも回転を表すには特別正交行列としての性質が使われます。ここで回転行列と直交行列の深い関係が見えてきます。回転行列は常に 直交で、さらに 行列式が +1 です。これを満たすと、該当の変換は「鏡映しを伴わない回転」であると理解できます。逆に行列式が -1 になる場合、同じ変換で鏡映しが混ざっていることを意味します。こうした性質は、3次元の回転を扱うときにも適用できます。実際に手元で回転行列を作ってみると、角度を変えるたびに矩形の長さが同じであること、角度の和を足すと回転の合成が簡単にできることを体感できます。
直交行列の定義と回転行列の関係を整理する
直交行列は転置行列を掛けた結果が単位行列になる性質を持ちます。つまり A が直交行列なら A^T A = A A^T = I となります。ここで A の列ベクトルは互いに直交かつ長さが 1 になる正規直交基底として解釈できます。この性質のおかげで、長さが保たれる変換だと直感的にわかります。回転を表す行列はこの直交性を満たしますが、もう一歩進んで 行列式が +1 か -1 か で回転か反射かを区別します。直交行列の行列式が +1 の場合、鏡映しを伴わない回転であり、-1 の場合は鏡映しを含む反射を含む変換です。実務では 3次元空間での正の定数回転を想定するときはこの区別が特に重要になります。直交行列は回転だけでなく回転と反射の混在を表す場合もあり、それぞれの性質を分解して考えるとプログラムでの実装や数値計算が安定します。総じて、直交行列は長さを保つ変換の集合であり、その中の特例として 回転行列が存在します。
実例で比べる回転と直交の違い
ここまでの話を具体的な例で確かめていきましょう。2次元で θ = 90度の回転行列を考えると、回転行列は点 (1,0) を (0,1) に動かします。長さは 1 のままで x 軸方向が y 軸方向へと移動します。一方、直交行列の例として鏡映しを含む変換を考えると、同じ長さを保つことは保証されますが角度の扱いは回転だけに限らず、向きの反転が起きる可能性があります。行列式が +1 の直交行列は回転に対応し、-1 の直交行列は反射を含む変換を表します。今回の表によって違いがはっきり分かるはずです。最後に、実際に手で演習するなら、2×2 の回転行列と 2×2 の直交行列を紙に描いて長さと角度の変化を追ってみると理解が深まります。
この作業を通じて 回転と直交の違い が日常の数学や物理の問題解法にも役立つことがわかるでしょう。
今日は回転行列についての小ネタを一つ共有します。友達と迷路ゲームをしているとき、進む方向を表すベクトルを回す動作を思い出してみてください。回転行列はまさにその“向きを変える操作”を数式で表したものです。角度を変えるとき、長さはそのまま保たれるという直感がとても強く働きます。実は回転行列は直交行列の特例であり、転置と逆行列が同じになる性質の下に成り立っています。だから計算上は長さを失わず、角度だけを調整する感覚で使えるのです。プログラムで図形を動かすとき、回転を足し合わせると新しい角度が一気に求まるというのも便利ポイント。回転と直交の違いをひとつの模型として捉えると、抽象的な線形代数が身近な感覚で理解できるようになります。





















