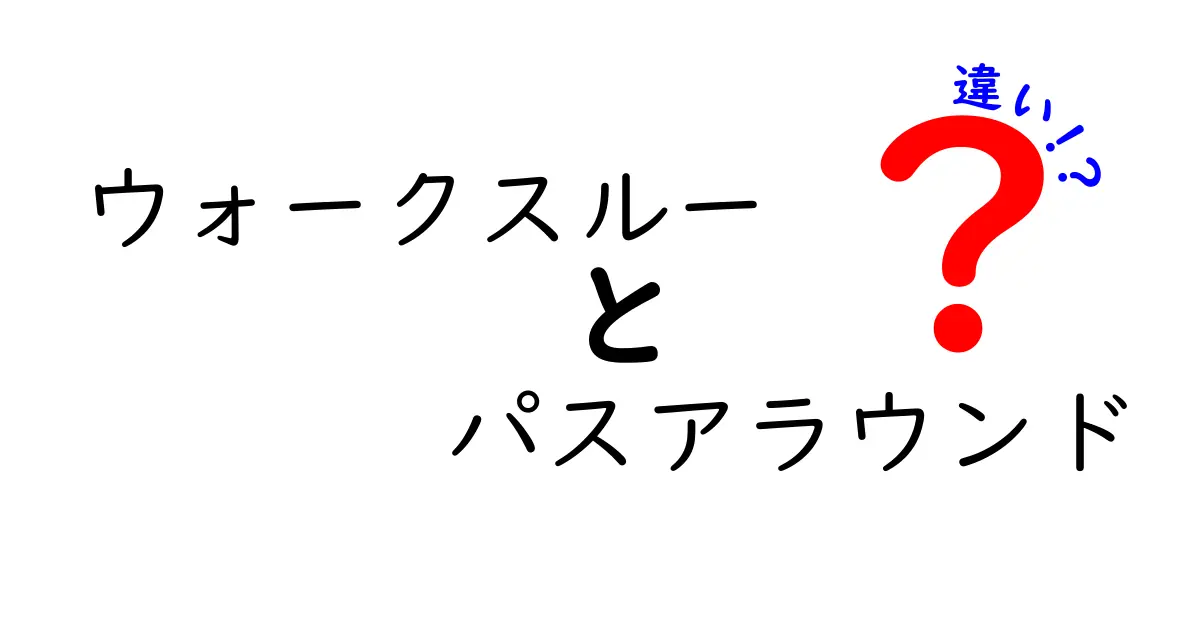

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ウォークスルーとパスアラウンドとは何か?基本の理解
皆さんは「ウォークスルー」と「パスアラウンド」という言葉を聞いたことがありますか?どちらもビジネスやプレゼンテーション、教育の場面でよく使われる言葉ですが、その意味や使い方が少し違います。
まずウォークスルーとは、あるプロセスや計画の詳細を一緒に段階を追って確認していく作業のことを指します。例えば、新しいソフトウェアの使い方をみんなで順番に確認していくのがウォークスルーです。
一方、パスアラウンドは、何か情報や資料、物を関係者に順番に回して共有する方法です。例えば、書類をスタッフに順番に回して目を通してもらうなどがパスアラウンドの例です。
ウォークスルーとパスアラウンドの具体的な違い
ウォークスルーとパスアラウンドは似ているように見えますが、実はその目的や進め方が異なります。
ウォークスルーは共同で内容を確認しながら進める方法で、参加者同士が疑問を出し合ったり、改善点を話し合ったりします。つまり、対話をしながら理解を深めていくプロセスです。
これに対してパスアラウンドは物理的またはデジタルで資料を順番に回して情報共有を行う方法で、参加者は自分のタイミングで資料を見て意見を求められたら答える形が多いです。対話の場が必ずしもあるとは限りません。
これらの違いは、会議やプロジェクトの効率化に大きく関わるため、状況によって適切な方法を選ぶことが重要です。
ウォークスルーとパスアラウンドの使い分けと活用例
どちらの方法もチームで情報を共有するときに役立ちますが、使い分けがポイントです。
ウォークスルーの活用例
・新しい業務フローの説明会で、担当者と一緒に確認しながら進める
・教育研修で講師が手順を実演し、参加者が質問しながら学ぶ
パスアラウンドの活用例
・議事録や報告書を参加者に順番に回してチェックしてもらう
・検討資料をステークホルダーに回覧し、フィードバックを集める
これにより、チームの理解度や効率的な進行が可能になります。
以下に簡単な違いをまとめた表を示します。ポイント ウォークスルー パスアラウンド 目的 一緒に内容を確認・理解を深める 資料や情報を順に回覧・共有する 進め方 会話や質問を交えながら進行 資料を回して個別にチェック 参加者の関わり方 積極的に対話しながら参加 受け取り順に確認し、必要に応じて回答 活用例 教育・研修、プレゼンの質疑応答 資料回覧、意見収集
このように両者にはっきりした違いがあるため、場面に合った方法を選ぶことが大切です。
ウォークスルーって、ただ説明を聞くよりも参加者みんなで一緒に確認し合うところがポイントなんです。
おかげで分からない部分がその場で解決できるし、理解が深まるんですよね。
逆にパスアラウンドは、資料を回してじっくり読んでもらう方法で、タイミングも人それぞれ。
どちらも目的に合わせて使い分けることが意外と仕事の効率を上げる秘訣かもしれません。
次の記事: 【初心者必見】3Dモデルと点群データの違いをわかりやすく解説! »





















