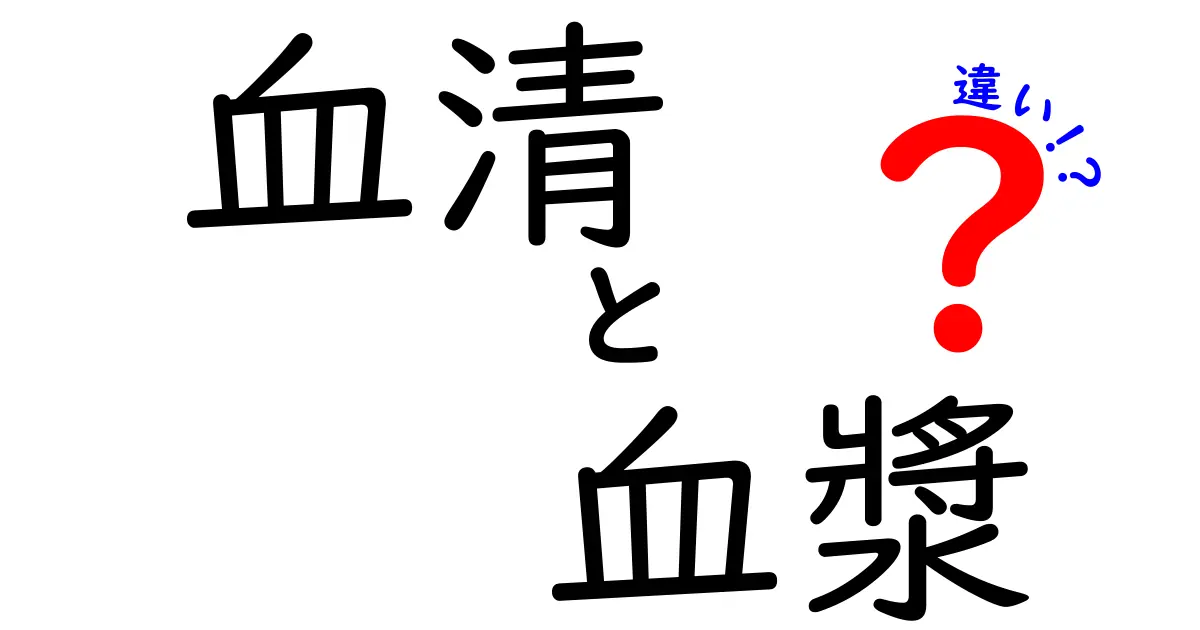

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
血清と血漿の基本を押さえよう
血液は私たちの体の中を流れる液体で、約7割が水分です。その中には赤血球、白血球、血小板のほかに液体成分である血漿が含まれます。血漿にはタンパク質や脂質、糖、電解質、そして凝固因子が含まれています。ここで重要なのは血清と血漿の違いを決めているのは「凝固因子が残っているかどうか」です。
血漿は抗凝固剤を使って血液を採取し、遠心分離の後に得られる液体です。凝固因子がそのまま含まれており、凝固経路が進む前の状態を保持します。これにより血漿は凝固因子に関わる検査や薬剤の挙動を正確に測るのに適しています。
一方、血清は血液を採取した後、自然に固まらせてから血餅を取り除いた液体です。血餅は血球とフィブリンの集合体で、血清にはこの凝固に関わる因子の多くが含まれていません。つまり血清は「凝固因子の影響を受けにくいサンプル」です。
この性質は抗体の測定や代謝物の分析など、凝固因子が結果を歪めるおそれがある検査に向いています。
現場ではサンプルを採取した後、どちらのサンプルを作るかを検査の目的で決めます。血漿は通常、抗凝固剤と混ぜて採血し、すぐに遠心して上澄みを使います。血清は採血後に血液を室温で固める待機時間を取り、固まった血塊を遠心して上澄みを取り出します。ここが実務での大きな違いです。
この作業工程の違いを理解しておくと、検査の再現性が高まり、結果の解釈もしやすくなります。
ポイントまとめ
・血漿は凝固因子を含む液体成分で抗凝固剤ありの採血から得る
・血清は凝固因子を失った液体で血餅除去後のサンプル
・用途の違いによって検査対象が変わるため、採取方法と処理が異なる
・保存条件も用途により異なるため、適切な取り扱いが重要
実際の検査例を挙げると、血清は抗体を測る免疫検査でよく使われます。感染症の診断やワクチンの反応を確かめるときに血清の抗体価が役立ちます。血漿は凝固因子の測定や一部のホルモン・代謝物の分析、薬物濃度の測定などで使われます。これらの使い分けは、検査結果の意味を正しく読み解くうえでとても重要です。
友だちと喫茶店で血清と血漿の話をしていたとき、私は意外と腑に落ちたんだ。血液を取って凝固させると、血餅ができて、上澄みの液体が血清。逆に抗凝固剤を加えてすぐ遠心分離すると、凝固因子を含む血漿が残る。検査の目的によって使い分ける、つまり『どの成分を測りたいか』が決め手になるってこと。免疫検査には血清、凝固因子を測るには血漿、という覚え方がいい。
次の記事: 細胞外液と血液の違いがわかる!体内の水の流れと役割をやさしく解説 »





















