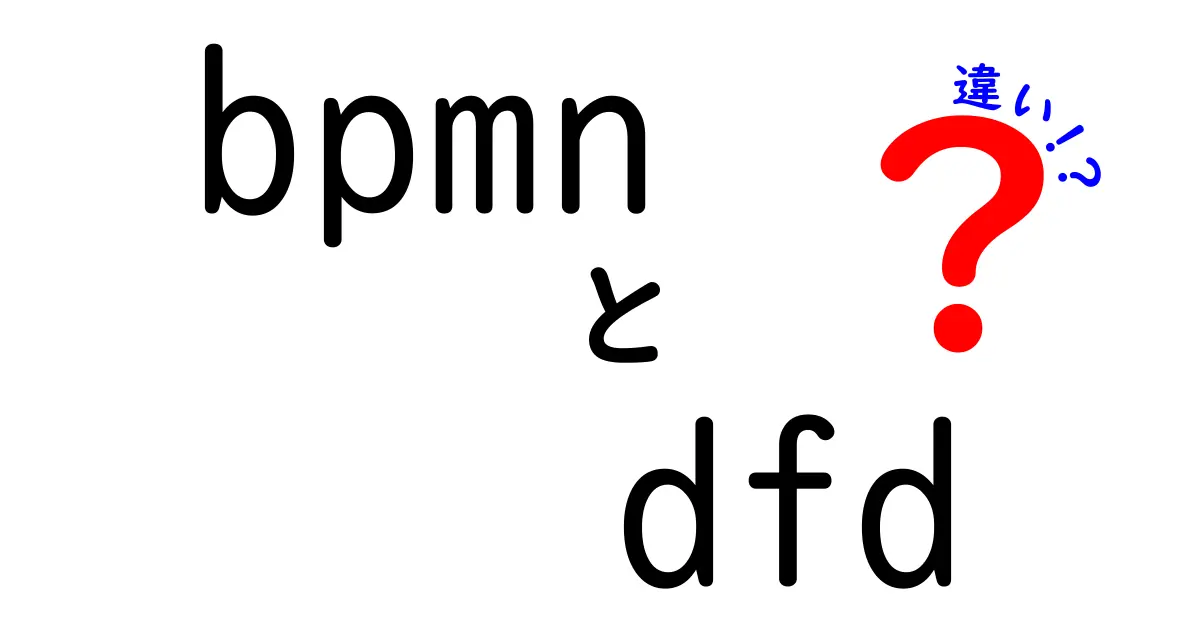

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:bpmnとdfdの違いを正しく理解する
BPMN はビジネス・プロセスを図で整理する標準的な記法です。業務の流れを“誰が・何を・いつ・どの順番で”進めるかを示すためのもので、企業の業務設計やシステム開発の前段階でよく使われます。BPMN の特徴は矢印と図形の組み合わせでプロセスの流れを直感的に伝えられる点です。開始イベントから処理を始め、分岐を示すゲートウェイ、並列処理、データの受け渡し、最終的な終了までの一連の動きを描けます。
このような要素を正しく組み合わせると、専門家だけでなく現場の人も“この作業はどの順番で進むのか”を共通理解として共有できます。BPMN は実務の現場でのコミュニケーションを円滑にするための言語のひとつとして機能します。
しかし記号が多く、理解には少し練習が必要です。最初は高レベルの全体像を把握し、次に各ステップの条件や例外を丁寧に追いかけると理解が深まります。これが BPMN の基本的な役割であり、現場での混乱を減らす第一歩になります。
一方で DFDData Flow Diagram はデータの流れと処理を中心に表現する図です。DFDは「データがどこから来て、どこへ行き、どんな処理を経て最終的にどんなデータになるのか」という視点で設計します。BPMN が“業務の手順と責任の分担”を強調するのに対し、DFD は“データの移動と変換”を重視します。DFD の主役はデータの流れであり、処理(加工)やデータストレージ、外部エンティティとのやり取りがセットとして描かれます。
この違いを理解すると、同じ現象を違う視点から説明できるようになり、問題点の特定や改善のヒントを複数の角度から探せるようになります。DFD は情報システムの設計やデータの流れの整理に強く、BPMN は組織の業務プロセスの可視化と改善に強い、というのが基本的な分野の分け方です。
この二つは混同されやすいですが、使う目的と対象が異なります。中学生にも伝えやすい言い方をすると、BPMNは「みんなで進む道順の地図」、DFDは「情報がどう動くかのルート地図」です。実務で活用する際には、まずどの視点から整理したいのかを決め、その視点に合った図記法を選ぶことが重要です。表現する対象が決まれば、図は自然と読み手に優しくなり、誤解が減ります。
このセクションではまだ抽象的な話でしたが、次のセクションからは実際の使い分けのコツと見分け方を、具体的な例と共に紹介します。現場で役立つポイントを押さえ、図解の力を日常の課題解決に結びつけていきましょう。
実務での使い分けと見分け方:どちらをいつ使うべきか
現場で Bpmn と DFD をどう使い分けるべきかを考えるとき、まず大きな違いを整理します。BPMN は業務プロセスの「実行可能な手順」を示すのが得意です。誰が、いつ、どの順番で動くのかを明確にし、業務の流れを可視化します。これにより、担当者間の認識のズレを減らし、業務改善のアイデア出しや新システムの要件定義をスムーズにします。
DFD は“データの流れ”と“データ処理の変換”を中心に置きます。データがどこから来て、どのように加工され、どこへ渡されるのかを追跡するのに向いています。特に情報システムの要件整理、データベースの構想、データの出所と利用先の関係を整理する場面で活躍します。
したがって、次のような使い分けが現場での鉄則になります。まず業務プロセス全体を共有して現場の人が実際の作業順序を理解する場面では BPMN を選ぶ。データの流れと処理を設計する段階では DFD を選ぶ。これが「誰が」「どこで」「何をしているのか」を明確にする基本の考え方です。
ただし現実は常に複雑で、1つの図だけで完結するケースは少ないです。実務では BPMN で大枠の流れを共有し、データの動きを別途 DFD で補足的に描くなど、2つを組み合わせて使う場面が多いです。これを可能にするのがドキュメントの整備と命名規則の統一です。どの図を使うにせよ、共通の語彙とルールを作ると、チーム全体の理解が格段に深まり、後からの修正や拡張も楽になります。
以下の表は両者の違いを視覚的に整理する小さなサマリーです。実務の現場ではこれをガイドとして活用してください。
bpmn vs dfd のポイント比較表
| 観点 | BPMN | DFD |
|---|---|---|
| 主な目的 | 業務プロセスの実行手順の可視化と最適化 | データの流れとデータ処理の変換の可視化 |
| 主役となる対象 | 作業者と作業順序 | |
| 表現の焦点 | 手順の流れと決定条件 | データの流入経路と加工過程 |
| 適用場面 | 業務改善要件定義、システム要件の整理 | データ設計、情報システムのデータ動線の整理 |
| 難易度と学習曲線 | 比較的難しく、記号が多い | データ視点に慣れれば理解は比較的取りやすい |
この表は要点だけを並べたものです。実務では各図の要素名を統一し、記述ルールを決めることで混乱を防げます。実務経験の少ない人には、まず BPMN で全体の流れを掴み、必要に応じて DFD を補完してデータの動きを整理する2段構えのアプローチをおすすめします。
最後に、実際に図を描くときのコツを一つ紹介します。複雑な図は最初から完璧を狙わず、まずは“Begin to End”の大枠を描き、次に分岐やデータの動きを追加していく方法です。こうすることで頭の中の情報の断片を順番に結びつけられ、後続の修正も容易になります。図解は言葉と同じく伝える力を持つツールなので、読み手の理解を最短で深めるための工夫を重ねていくことが大切です。
具体的な使い方と理解を深める例
ここでは日常的な例を使い BPMN と DFD の違いをさらに深く理解します。想像してみてください。あなたが学校の図書室で本を借りるとします。BPMN 的には借りるまでの手順を“開始”から“終了”まで順序立てて描き、誰が手続きのどの段階を担当するかを明確化します。例えば受付の人が身分証を確認し、図書の貸出処理を行い、最終的に返却日を登録する、という流れです。これを BPMN で描くと各ステップの接続や分岐が明確になり、誰が何をするのかを共通認識として持てます。一方で DFD 的に見ると、借りるというデータは「借りる申請」「図書情報」「身分情報」といったデータの流れと変換によって動くことになります。データはどこから来て、どのように処理され、誰が受け取るのか。データ主導の視点で整理することで、情報の流れが分かりやすくなり、後でデータベース設計やシステム連携を考える際の土台になります。
この例から分かるのは、BPMN は作業の“実行可能な順序”を、DFD は“データの動きと処理の連携”を主役にするという点です。いずれも現場での意思決定を助けるための図解ですが、目的が違えば描き方も異なります。学習を進める際には、まず自分が何を可視化したいのかを明確にしてから図の記法を選ぶと、理解が早く進みます。
このセクションの総括として、BPMN と DFD は互いに補完し合うツールです。業務の流れとデータの動きを同時に把握したいときには、2つを組み合わせて使うのが効果的です。図解の目的が「共有」「修正」「改善」にあることを忘れず、チームでの読み合わせを重ねていきましょう。
最後に、図解はあくまで伝えるための道具です。分かりやすさを第一に、読み手の立場に立って言葉だけでは伝えきれないニュアンスを図として補完していくと良いでしょう。
今日は BPMN と DFD の違いを雑談風に深掘りしました。キーワードはシンプルに、目的を明確にすることです。BPMN は作業の順序と責任の分担を示す道具、DFD はデータの流れと加工を追う道具。どちらを選ぶかは何を解決したいかで決まります。実務では両方を併用するケースも多く、視点を切り替えられる人ほど設計の幅が広がります。図解は難しく考えすぎず、まずは大枠から始めて徐々に細部を詰めるのがコツです。あなたの身近な課題を一つ取り上げて、BPMN と DFD のどちらを先に描くべきかを考えてみてください。
前の記事: « アラームと時報の違いを徹底解説!毎朝の準備が変わる使い分けガイド
次の記事: アラームとブザーの違いを徹底解説!中学生にもわかる使い分けと実例 »





















