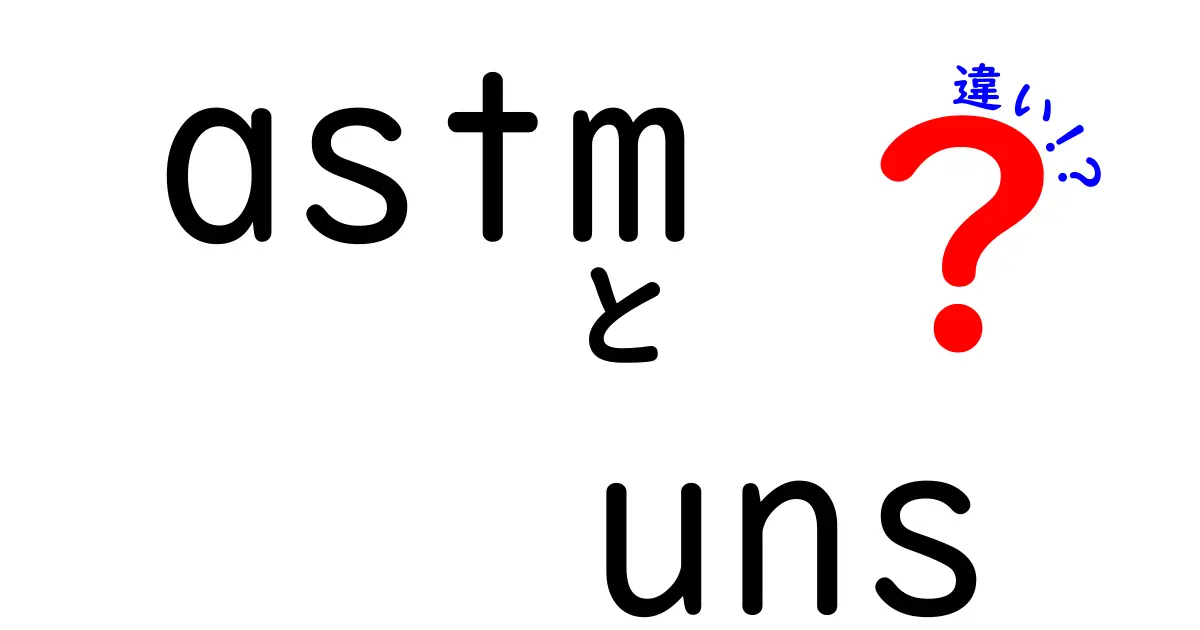

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ASTMとUNSの違いを徹底解説!金属規格の基礎を正しく理解するためのガイド
金属材料の品質を考えるとき、ASTMとUNSの2つの語をよく目にします。それぞれ役割が異なり、混同すると設計ミスや納入トラブルの原因になります。本記事では「ASTM」と「UNS」の意味を、身近な例とともにじっくり解説します。まずは概要を整理し、その後で実務での使い分け方を具体的に示します。
ASTMは材料や部品、試験方法の標準を定める団体として世界的に知られており、強度、耐食性、加工性といった性質をどう評価するかを定めます。対してUNSは“この材料はどのコードで表されているか”を示す識別番号の体系です。UNSを使えば、国や規格体系が異なる場面でも同じ材料を指すことができます。
この違いを理解しておくと、図面や仕様書を読んだときの誤解を減らし、材料選択や購買・検査の際のやりとりがスムーズになります。以下では具体的な違いと、現場での正しい扱い方を詳しく整理します。
ASTMとは何か
ASTMは「American Society for Testing and Materials」の略で、材料や部品、試験方法の標準を作る世界的な組織です。
正式名称よりも“規格番号”で呼ばれることが多く、例としてASTM A36やASTM A53などが有名です。A36は構造用鋼材の機械的性質、A53は鋼管の溶接と耐圧性に関する規格です。
ASTMの規格は設計者にとっての参照基準であり、製造ラインでは検査方法や受入基準として日常的に使われます。
また、ASTM規格は世界各地の企業が共通の品質基準として使用できるように設けられており、国際貿易における技術的障壁を低くする役割も果たします。
このようにASTMは「何を作るか」を決めるルールと、それを検査する手順を提供する、材料業界の中核的な規格機関です。
覚えておきたいのは、ASTM規格は材料の“仕様”そのものであり、製品の品質保証に直結する要素を含むという点です。
UNSとは何か
UNSは「Unified Numbering System」の略で、材料を識別するための統一番号です。
この番号は主に鉄や鋼、合金の組成や用途を表し、同じ材料を指す複数の規格体系を結びつける役割を果たします。たとえば、304ステンレス鋼はUNSでS30400、316ステンレス鋼はS31600と表されます。さらに904LはN08904、銅やアルミニウム系の UNS番号も存在します。
UNSを使う利点は、部材の購買や在庫管理、設計者間のコミュニケーションを円滑にする点です。AISI番号やISO番号、規格番号が混在する場面でも「この材料はUNS番号で指定されている」と確認すれば、誤解を減らせます。
ただしUNS自体は「規格を作る団体」ではなく、材料を一意に指すコードである点を覚えておくと混乱を避けられます。
設計資料や購買仕様書を作成する際には、ASTM規格とともにUNS番号を併記するのが一般的です。これにより世界中の設計者・製造者が同じ材料を同じコードで参照できるようになります。
主な違いと使い分け
前述の内容を踏まえ、実務的な使い分けと注意点を整理します。
POINT 1: 役割の違いASTMは規格と試験方法を定義する団体およびその規格自体を指すのに対し、UNSは材料を識別するコードです。
POINT 2: 情報の出力先設計書や品質保証資料にはASTM規格が記載され、在庫管理や購買にはUNS番号が使われることが多いです。
POINT 3: 相互関係多くの場合、ASTM規格とUNS番号は併記され、同じ材料を複数の形式で参照します。
さらに、以下の表を見れば具体的な違いが分かりやすくなります。
表のポイントだけをまとめると、ASTMは規格・試験方法を決める団体とその仕様自体、UNSは材料を特定するためのコードです。
現場では、設計者が「この部材はASTM A36準拠の強度を持つ」と記載する一方で、購買や品質保証の文書には「UNS番号で参照される304ステンレスS30400」と併記されることが普通です。こうした併記は、国やメーカーが違っても材料の識別を確実にするための工夫です。最後に、知っておくと便利なポイントをいくつか挙げます。
・ASTMはアメリカ中心の規格体系ですが、国際的にも広く参照されます。
・UNSは分野をまたいだ材料名の一意識別子として機能します。
・同じ材料でもASME、SAE、ISOなど他の規格体系と併用される場面が多く、混乱を避けるには文書内の表記を統一することが肝心です。
友達と雑談している雰囲気で深掘りします。ASTMとUNSは似た名前だけど役割が違うんだよ。ASTMは材料の規格を作る団体で、規格番号に基づく“何をどう評価するか”を教えてくれる。一方UNSは材料を一意に識別するコードで、同じ304ステンレスでも国や規格が変わってもS30400と表せば同じ材料だと分かる。だから設計資料には二つの情報を併記するのが多いんだ。意識して使い分ければ、混乱も減るよ。





















