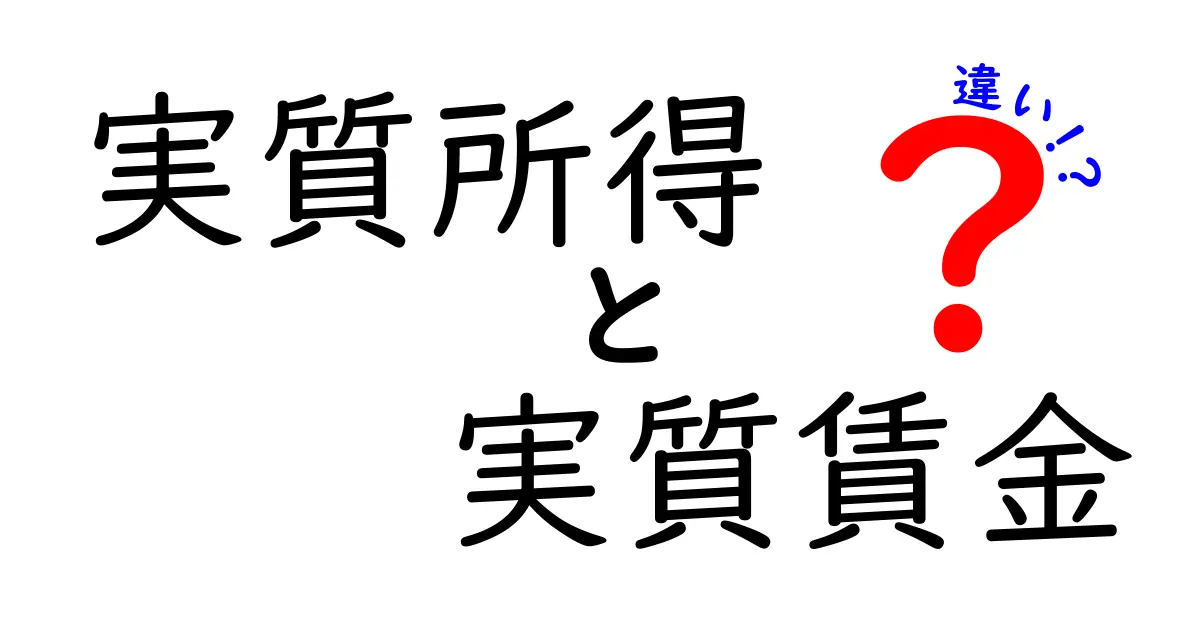

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
実質所得と実質賃金の違いを徹底理解しよう 中学生にも伝わるやさしい解説
この話は日常生活の中でとても身近に感じられる話題ですが 実は少しの考え方の違いで意味が大きく変わってきます ここでは 実質所得 と 実質賃金 の違いを 丁寧に分かりやすく説明します 物価が上がるとお金の力がどう変わるのか そして私たちの生活にどんな影響が出るのかを 一つずつ噛み砕いていきます なお 紙の教科書だけでは見えづらい点を 具体的な例と比喩を使って解説します 未来の計画を立てるときにも役立つ考え方なので ぜひこの機会に理解を深めてください
定義を押さえる 実質所得と実質賃金とは何か
まずは基本の定義です 実質所得 とは 物価の変化を考慮した後の所得の価値を表す考え方です つまり 同じ金額の所得でも 物価が高くなるとその所得の実際の購買力は下がります 逆に物価が下がれば購買力は上がります このように相対的な購買力の強さを見える化するのが 実質所得 です 一方 実質賃金 は 役割を少しだけ変えて同じ考え方を労働者の立場から見たものです 労働者が手にする賃金の「購買力」を 現在の物価水準で評価したものが 実質賃金 です 名目の賃金額だけを見ても生活が豊かかどうかはすぐには分かりません 物価の変動を取り除いた本当の価値を知ることが大切です
ここで重要なポイントを いくつか覚えておくと理解が深まります 1つ目は 名目と実質の違い です 名目はそのままの金額です 実質は物価を加味して計算した価値 2つ目は 物価上昇と購買力の関係 です 物価が上がると同じ金額でも買えるものが少なくなり 購買力は低下します 3つ目は 家計の実感は名目だけでは測れない ということです 収入が増えても物価も上がると 実質的な生活水準は変わらないか 下がることもあるのです
計算の仕方と違いが生まれる理由 どんな場面で差が出るのか
実質所得と実質賃金を正しく比較するには 物価の影響を取り除く必要があります そのために用いられるのが 価格指数 です 多くの場合 消費者物価指数 CPI が使われます 名目所得を CPI で割って 100 を掛けると 実質所得の目安が出ます 同じ考え方を実質賃金にも適用します これにより 生活費の変動を考慮した賃金の実力 を測ることができます
例えば ある年の名目所得が 100 万円 で CPI が 105 だったとします このとき 実質所得は約 95.2 万円になります 物価が上がるときには こうした計算をして 実際の購買力を見直す必要があります
実生活への影響と見方 どう考えるとよいか
実質所得と実質賃金を知ることは 将来の備えを立てるうえでとても役立ちます 家計の計画 を立てるときには まず今年の物価上昇率を把握し 来年以降の収入がその上昇率を上回るかをチェックします 教育費や光熱費 などの支出項目ごとに実質の変化を見ておくと 安心して貯蓄や投資の計画を作ることができます また 家族の生活の質 を維持するためには 賃金だけでなく 物価の動向にも敏感になることが大切です
今日は 実質賃金という言葉が友だちとの会話で出てきたとき 何のことか分かるように話をしてみる という雑談を思い出してみよう 実質賃金は 表面的な給料の額名目の金額だけを見て判断するのではなく 物価の変動を考慮した“本当の買える力”を考える考え方だよ 例えば 夏のボーナスが 増えたと言われても そのときの物価がぐんと上がっていたら 結局のところ生活は楽になっていないかもしれない そんなとき 実質賃金の話題が出ると 生活の質を守るためには 「給料だけではなく 支出と物価の動きもセットで見る」という発想につながるんだ 友だちと お互いの家庭の生活費を例に どれくらいの購買力があるかを比べ合うと とても楽しく 役に立つ雑談になるよ





















