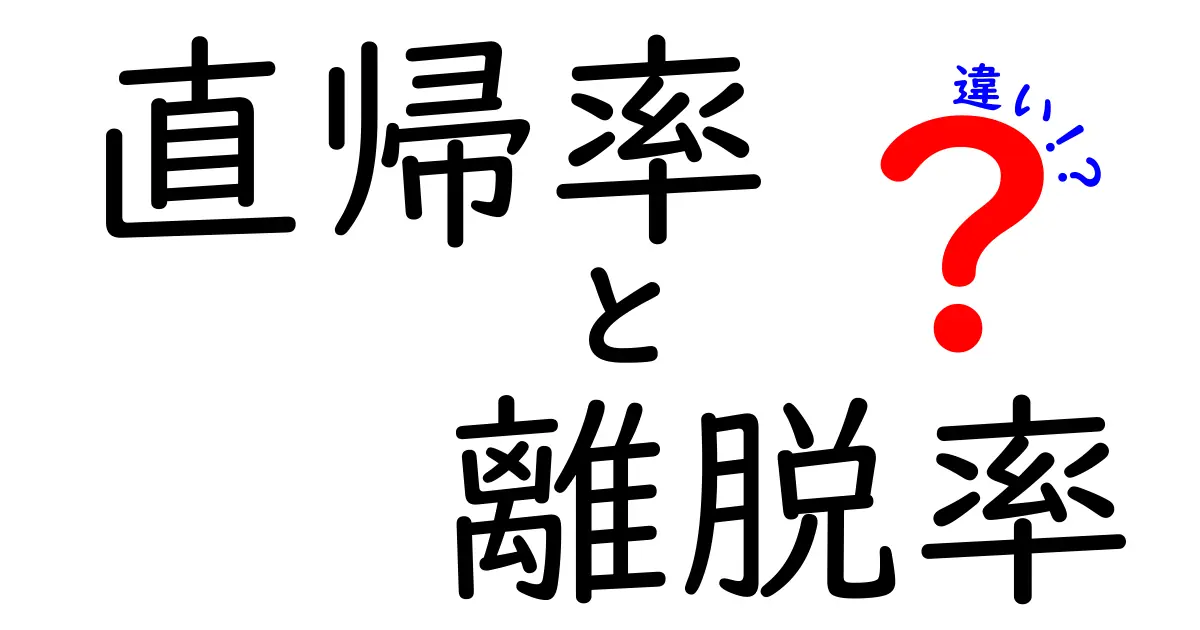

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
直帰率と離脱率の基本を知ろう
直帰率は、訪問者が最初のページだけを見てサイトを離れる割合です。多くのケースでは、ランディングページの魅力や導線の良さを示す指標として使われます。逆に、訪問者が別のページへ移動せずに離脱するということはこのページが訪問の目的に合っているかを疑うサインにもなります。
一方、離脱率は、セッションの途中でそのページを最後のページとして離脱した割合を指します。特定のページがセッションの最後になる頻度を示しており、単体のページの完成度や次のページへの導線の強さを測る目安として活用します。
ここから重要なのは、直帰率は“セッション全体の性質”を、離脱率は“そのページの終わり方”を示す指標だという点です。たとえば、ブログの記事トップページの直帰率が高くても、読者が長い記事をはしごして別のページへ行くケースが多い場合、直帰率だけで全体を判断するのは危険です。逆に、ECサイトの特定の商品ページの離脱率が高い場合、商品説明の不足や価格表示の不明瞭さ、カート画面への導線の弱さを示唆します。
この章の要点は次のとおりです。直帰率はランディングページの入口の質を、離脱率はページの出口の質を表す。数値が高いと必ずしも悪いとは限りませんが、原因を特定して改善に結びつけることが大切です。
実務での使い分けと注意点
現場で直帰率と離脱率をどう使い分けるかが、データの解釈を大きく変えます。直帰率は新規訪問者の入口の状態を見極める際に有効で、広告のランディングページやSEOの入口ページの改善に直結します。高い直帰率が出た場合には、見出し・ファーストビュー・読みやすさ・読み進める動線などを点検します。
離脱率は、特定のページがどこで閲覧を止められているかを示すヒントになります。たとえば「商品詳細ページの離脱率が高い」なら、画像の見せ方、要約のボリューム、次のアクション(カートへ、関連商品表示、レビューの提示)を再配置する必要があるかもしれません。
注意点として、データはセグメントで分けて解釈することをおすすめします。デバイス、地域、流入経路、時期などを分けて比較すると、直感的な結論を避けられます。さらに、「ツールごとに定義が異なる場合がある」点にも注意が必要です。Google Analyticsと他のツールで数値が微妙に違うことがあります。
最後に、改善のヒントを実務的なアクションとして整理します。CTAの位置を見直す、ページの読み込み速度を速くする、関連コンテンツへ導線を追加する、そしてA/Bテストを実施して、どの変更が実際に改善をもたらすかを検証します。
ねえ、友だちと文化祭の準備をしていたときウェブの話題が出てきて『直帰率と離脱率って何が違うの?』って話題になったんだ。僕は直帰率を入口の第一印象がそのまま結果になる指標と考え、読者が求める情報と見出しが一致していれば直帰率は必ずしも悪い数値ではないと伝えたんだ。離脱率はページが終わる瞬間を測る指標で、次に何をしてほしいかを設計できていれば改善できる。要はデータの意味は使い方次第。そんな雑談だった。





















