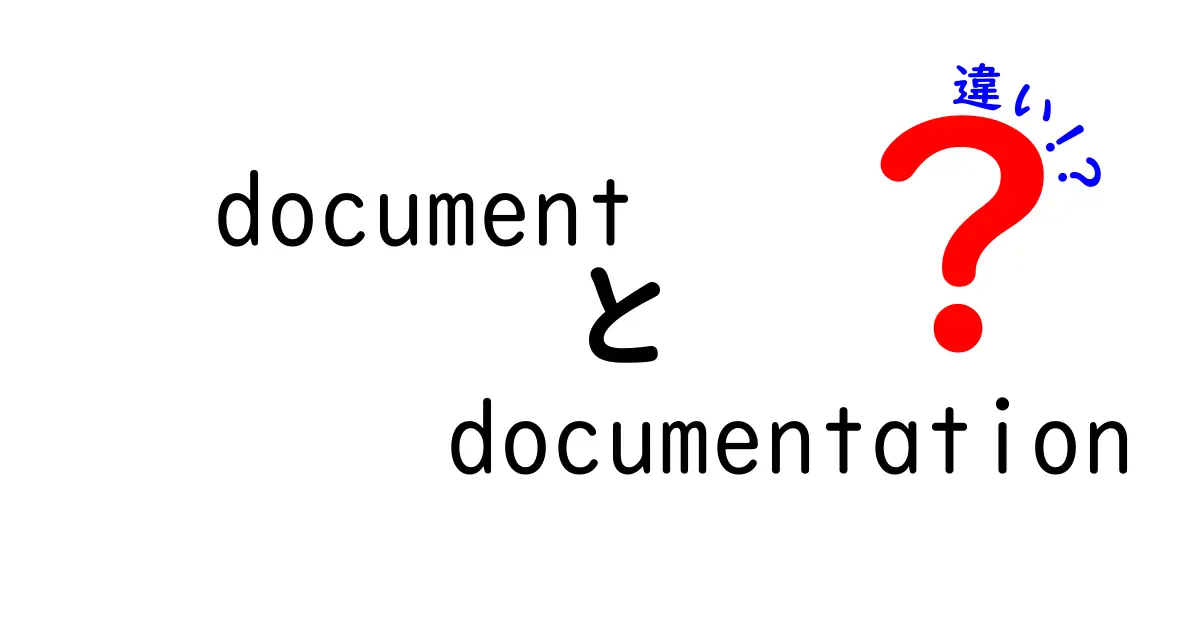

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
documentとdocumentationの違いを知っておくべき理由
この2つの英語は、見た目は似ているけれど使い方がまったく違います。documentは「文書・ファイルそのもの」を指す名詞で、紙の文書からPDF、テキストファイルまで幅広く使われます。一方、documentationは「文書で整理された情報の集合・体系」を指す名詞で、主に製品やサービスの使い方を説明するガイドやリファレンスをまとめたものを指します。日本語の訳としては、documentは「文書」や「文書ファイル」、documentationは「公式ドキュメント・マニュアル・リファレンス」と訳されることが多いです。
この違いを正しく理解していないと、文章を読んだり書いたりする場面で意味が伝わらず、相手に混乱を与えることがあります。例えば、ソフトウェア開発の場面ではdocumentは実際のコードや仕様を指すことが多く、documentationはAPIの使い方や設計意図を説明するガイド群を指します。これを混同すると、読者が「このファイルは何のためのものか」「この説明はどの情報を指しているのか」を判別できなくなってしまいます。
以下の表は、documentとdocumentationの基本的な違いを端的に整理したものです。これを覚えておくと、文章を書くときにも言い換えが自然になります。
この違いは英語圏の技術文書でも頻繁に見られ、公式ドキュメントや仕様書といった日本語訳にも直結します。覚え方としては、documentは“個別の文書”を指す名詞、documentationは“文書の集まり・体系”を指す名詞と捉えると混乱が減ります。
さらに、単数形と不可算名詞の使い方にも注目してください。documentは数えられる名詞で数えられる「a document」「two documents」と表現します。対してdocumentationは不可算名詞として扱われることが多く、“the documentation”として一つのまとまりを指す場合が多いです。
この点も使い分けのポイントになります。
最後に、使い分けを実務にどう活かすかを短くまとめます。
実務のコツ
1) 実際のファイルを指すときはdocument、
2) 使い方をまとめたガイド・マニュアルを指すときはdocumentation、
3) 日本語訳は文脈で使い分ける。
4) APIやソフトウェアの説明で迷ったときは、公式のdocumentationを参照するのが安全です。
日常での使い分けと誤解を解くポイント
ここからは、より実践的な使い分けのコツを詳しく見ていきます。まず大切なのは、文脈と対象を意識することです。たとえば、紙の契約書や写真付きのPDFを指す場合はdocumentを使います。対して、ソフトウェアのインストール手順やAPIの仕様、使い方がまとまった資料群を指す場合はdocumentationを使います。
次に、単語の性質にも注目です。documentは可算名詞で、documentationは不可算名詞として扱われるケースが多いです。英語の会話やメールでも、documentationを「この製品の使い方の集合」として扱うと自然です。
また、日本語の言い換えを統一すると読み手に優しくなります。例として、documentを「文書ファイル」「資料」、documentationを「公式ドキュメント」「マニュアル・ガイド・リファレンス」と置き換えると、意味が伝わりやすくなります。
正確さを保ちながら親しみやすい表現を心掛けると、読み手に誤解を与えず理解を深められます。
要点をもう一度まとめます。
documentは「実際の文書・ファイルそのもの」
documentationは「文書化された情報の体系・ガイド群」
使い分けの基本はこの2点です。以下の短い練習問題で確認してみましょう。
1) このメーカーの公式サイトにはどの文書があり、どのガイドがあるのかを区別して読んでみる。
2) 文章を書く前に、documentとdocumentationのどちらを指すのかを決めておくと、表現が整理されます。
このような意識を持つだけで、読み手に伝わる情報の質がぐんと上がります。
ある日、友だちのケンと僕は学校の課題について話していました。
僕が「このソフトのdocumentationを読んでAPIの使い方をまとめておくね」と言うと、ケンは少し困った顔をしました。
「え、documentとdocumentation、どう違うの? どっちを使えばいいの?」と。
僕はゆっくり手元のノートを開き、整理して説明しました。
「documentは“個別の文書”だよ。例えばこの課題のPDF、参考資料のファイル、写真付きのレポートなど。
一方、documentationは“文書の集合”だよ。APIの使い方ガイド、リファレンス、クイックスタートなど、何冊もの説明がまとまっているものを指すんだ。
この違いを意識すれば、相手に伝わりやすい書き方になるんだ。今日はこの“違い”を意識して文章を組み立てる練習をしてみよう。
その後、僕らは同じ課題でも情報の粒度を変える練習をしました。
難しい言葉を使わず、まずはdocumentとしての「ファイル名・ファイルの内容」を示し、続けてdocumentationとしての「使い方・手順・注意点」を書き足す。そんな順序で説明すると、読み手は混乱せず、必要な情報にすぐたどり着けます。
結局、二つの言葉は友達の関係みたいなもの。役割が違うだけで、同じ場面をより良くする手段をくれるのです。





















