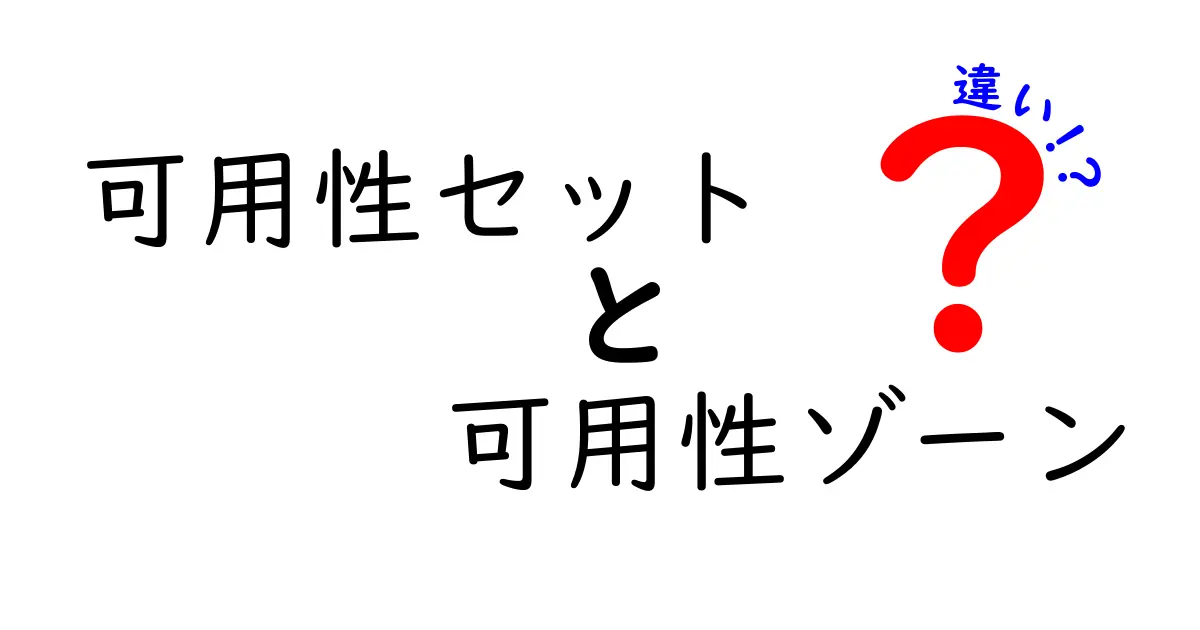

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:可用性セットと可用性ゾーンの基本を知ろう
現代のクラウドサービスは「壊れにくさ」がとても大事です。サービスが止まらないように、裏側でいろいろな工夫がされています。そのひとつが「可用性セット」と「可用性ゾーン」です。この2つは似ているようで、守る範囲や置かれた場所が違います。この記事では、わかりやすい言葉でその違いを解説します。まずは、それぞれが何を指すのかを押さえましょう。
可用性セットは「同じデータセンター内での冗長化」を、可用性ゾーンは「地域内で分散させる冗長性」を指します。
この違いを知っておくと、どんな時にどちらを使うべきか、選択のヒントになります。
では、次の章で可用性セットの意味を詳しく見ていきましょう。
可用性セットとは何か
可用性セットは、仮想マシンを同じデータセンター内で「複数の場所に分散して配置する」仕組みです。具体的には、フォールトドメインと呼ばれる電源やネットワークの故障が起きても影響を減らすための区分と、アップデードドメインと呼ばれるメンテナンス時の影響を最小化する区分に、VMを割り当てます。これにより、1台のVMが落ちても他のVMが動いてサービスを続けられる可能性が高くなります。
注意点としては、可用性セット内のVMは同じ物理ロケーション(データセンター内)に存在していることが多く、地理的な隔離は提供されません。
つまり「同じ建物・同じ棟内での故障にも耐えられる設計」と覚えるとよいでしょう。
また、可用性セットを使うと自動的にリソースが分散されるため、運用も比較的シンプルです。
可用性ゾーンとは何か
可用性ゾーンは、地域内にある複数のデータセンターを指します。通常は3つ以上のゾーン(例:ゾーン1・ゾーン2・ゾーン3)に分かれており、それぞれが独立した電源・冷却・ネットワークを備えています。ゾーン間での分散は、地域全体の障害にも耐えられる設計となり、可用性がさらに高まります。可用性ゾーンを使うと、同じアプリケーションを複数のゾーンに跨って配置することができ、ゾーンの一部が落ちてもサービスを継続できます。
ただし、ゾーン間の通信コストやデータ同期の遅延、設定の複雑さが増す場合があるため、設計段階で計画を立てることが重要です。
違いを比較する表と実践例
まとめと選び方
選択のコツは、「どこまでの障害を想定するか」を考えることです。もしあなたのアプリが地域全体に影響されるリスクを減らしたいなら可用性ゾーン、同じデータセンター内でのコストを抑えつつ安定性を高めたい場合は可用性セットを選ぶのが基本です。
実際には両方を併用するケースもあり、設計段階で要件と予算を整理することが大切です。
ある日の放課後、僕と友だちのミキはクラウドの話題で盛り上がっていた。ミキが「可用性ゾーンって何だろう?」と素朴な疑問を投げかける。僕は教室の黒板を思い浮かべながら答えた。「ゾーンは地域内の独立したデータセンターの集まりで、1つのゾーンが落ちても他のゾーンが動いてくれる仕組みなんだ」。ミキは「へえ、それって学校の教室みたいに、教室ごとに電気や机が独立している感じ?」と例えを返してきた。僕はさらに深掘りして、「可用性セットは同じ建物の中での冗長化。例えば、理科室と体育館の機材を別々の場所に置くようなイメージ。ゾーンは地域全体に伸ばすので、地震や停電といった大きな障害にも備えられる」と説明した。話が進むにつれて、現実世界の例とクラウドの設計が結びつく。最後にミキは「じゃあ、学校の運営を想定したら、どちらを先に考えるべき?」と尋ね、僕は「まず要件と予算、そして回復目標を決め、それからセットとゾーンを組み合わせる計画を立てよう」と締めくくった。雑談はいつしか、実務的な設計のヒント探しへと変わっていた。





















