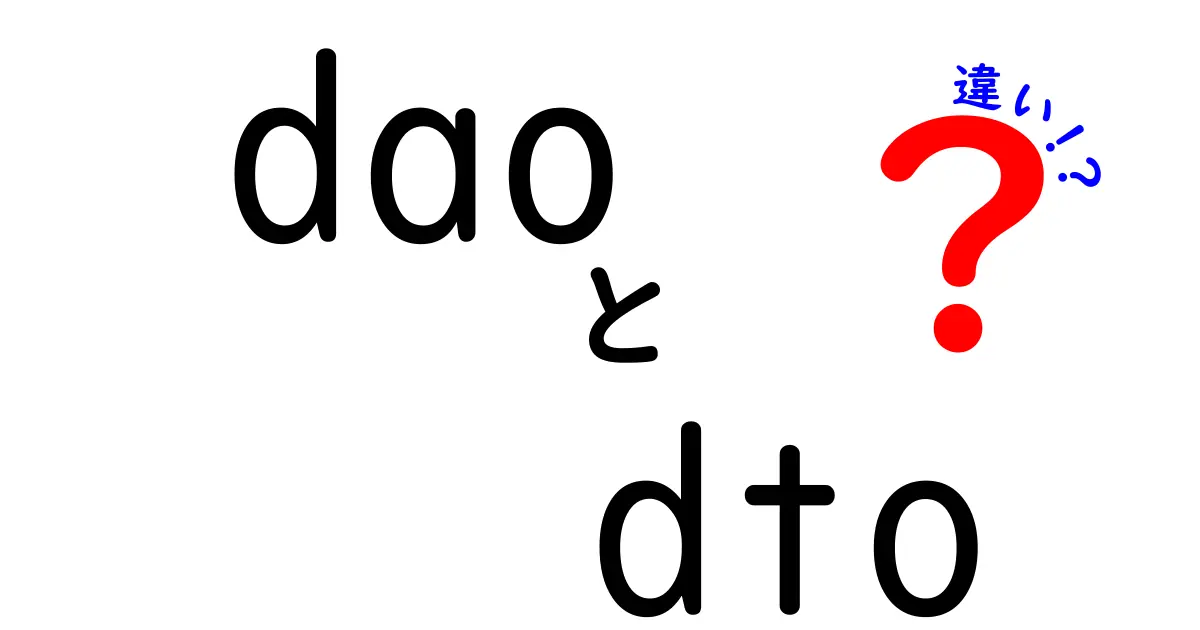

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
DAOとDTOの違いを理解する基本ガイド
DAOとはデータアクセスオブジェクトの略で、データベースとのやり取りを一手に引き受ける役割をもつ設計パターンです。具体的にはデータの取得、更新、削除といった操作をまとめ、ビジネスロジックの上流にあるコードからはデータの取り出し方を隠蔽します。これによりデータベースの変更や接続方法の見直しがあっても、他の部分の実装を崩さずに済みます。
一方DTOとはデータ転送オブジェクトの略で、データを層間で運ぶための箱のような存在です。DTOは通常属性だけを持ち、ビジネスロジックを含みません。サーバーとクライアント、またはビジネス層とプレゼンテーション層の間で必要な情報だけをまとめて送ることで、通信量を減らしコードを分かりやすくします。
DAOとDTOは互いに補完的な役割を果たします。実務ではデータベースから情報を取り出す際にDAOを使い、取得したデータをDTOに詰め替えて別の層へ渡すという流れが一般的です。つまりDAOはデータの取得保存の窓口、DTOはデータを次の窓口へ渡す入れ物なのです。これにより設計がシンプルになり保守性が高まります。
実務での使い分けと実例
現場ではデータの性質と通信量のバランスを考えて設計します。例えばウェブアプリのユーザー情報を扱う場合データベースには多くの関連情報が格納されていますがUIに送る必要があるのはその一部だけです。ここでDTOが活躍します。サーバーはDAOを使ってデータベースから情報を取り出しUIに渡す前にDTOに整理します。DTOは必要な情報だけ軽量化された構造にするのがコツです。これにより通信量が減り画面表示のスピードが向上します。
別の観点としてテストやリファクタリングにもDAOとDTOの役割分担は役立ちます。DAOのインターフェイスを変更してもDTOの形を揃えておけば他の部分へ影響を最小化できます。もちろんDTOの設計ではデータの整合性と将来の拡張性を意識することが大切です。さらに表現の違いをわかりやすくするための小さなポイントとしてDAOは実データの取得保存、DTOはデータを渡す形に焦点を当てると覚えやすくなります。このような認識を持つと設計の議論がスムーズになり後でチーム内で共通言語として使えるようになります。
この koneta ではDTOの深掘りを雑談風に語ります。DTO はデータ転送の箱のような比喩がよく使われますが、なぜこの箱が現代のソフト開発で重要なのかを友だちと気軽に話してみます。箱には必要な情報だけを詰め、不要な情報をそぎ落とす工夫があるため、UI とサーバーの間のやり取りが速くなります。私たちが授業で配布されたワークシートを思い浮かべると分かりやすいかもしれません。箱を軽くすると移動が楽になるのと同じように、DTO を適切に設計するとデータの流れがスムーズになり、全体の仕組みが理解しやすくなります。そんな話題を友だちと雑談することで、設計の楽しさが伝わってくるはずです。





















