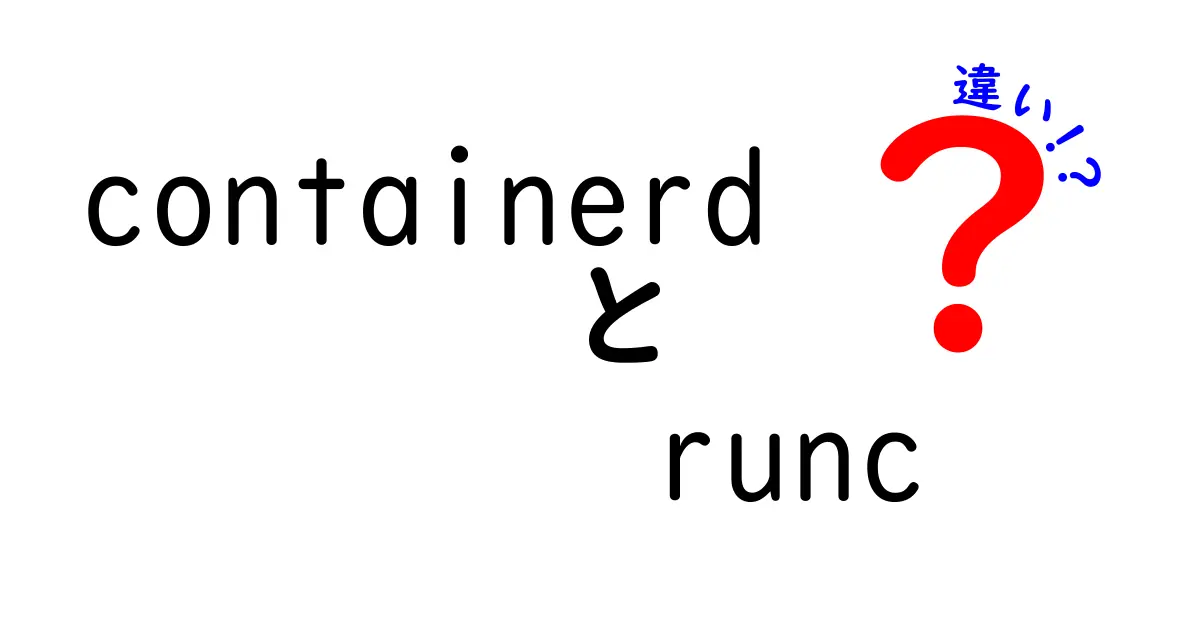

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:containerdとruncの違いを知る意味
現代のソフトウェアは複数の小さな部品で成り立っています。特に「コンテナ」と呼ばれる技法は、同じマシン上で複数のアプリを同時に独立して動かすのに便利です。コンテナを実際に動かすには、まず下にある仕組みを理解する必要があります。キーワードとして containerd と runc があります。
結論から言うと、containerd は「管理者」的な役割を担い、複数のランタイムをまとめて動かします。一方で runc は「実際にコンテナを動かすエンジン」で、コンテナ内のプロセスを起動します。
この二つは別物ですが、協力して安定した動作を作り出しています。もしあなたがクラウドやサーバーの運用を学ぶなら、まずこの役割分担を覚えると道筋が見えやすくなります。
なお、混同しやすいポイントとして「誰が何を決めるのか」という観点があります。containerd が指揮を取り、runc が実際の演算を実行する、というイメージを持つと理解しやすいです。
containerdとruncの基本的な違いをやさしく解説
まず、containerdとruncが役割分担をしている点を押さえましょう。
runc は、Linuxの名前空間やcgroupsを使って新しいプロセスを作り起動します。つまり“実際の動作”を担う部品です。対してcontainerdは、複数のランタイムを統合し、コンテナのライフサイクル全体を管理します。起動・停止・再起動・監視・ログの集約といったタスクを、背後でコーディネートします。ここで覚えておきたいのは、containerdは“派生ツールの集合体”であり、runcはその中の一つの実装に過ぎない、という点です。
この二つの関係性を混同すると、トラブル時の原因特定が難しくなります。例えば、「コンテナは動くのに、監視ツールが反応しない」「リソース制限が効かない」などの状況は、実行部と管理部の責任範囲が混ざっているかどうかで解釈が変わります。
正しく理解するには、実例として Kubernetes の動作を思い浮かべると分かりやすいです。Kubernetes はコンテナを起動するための命令を出しますが、その命令を実現するのが containerd であり、実際の起動は runc が担います。この組み合わせが、現代の多くのクラウド環境で標準になっています。
実務での使い分けとポイント
実務における使い分けのポイントは、次の三点です。第一に、環境の安定性を最優先で考えるときは、containerdの安定版を基盤に置くことが多いです。なぜなら containerd は複数のランタイムを統括するため、将来の移行がしやすいからです。第二に、特定の高機能を要する場合、または独自のカスタムランタイムを使う場合は、runc の挙動を直接理解しておくと役に立ちます。第三に、「トラブル解決の視点」を持つこと。エラーメッセージが出たとき、どの部品が原因かを切り分けるには、実行と管理の責任範囲を分けて考えると見通しが立ちやすくなります。
ここからは、実務の現場での使い分けの具体的なヒントです。例えば、CI/CD パイプラインを設計する際には、containerd のプラグイン構成を活用して、再起動時の挙動を安定させると良いでしょう。さらに、監視ツールやロギングの連携を意識して設定することで、トラブルが起きても原因を特定しやすくなります。以下の要点は実務で役立つ指針です。
・安定性重視なら containerd を選択する
・特定の機能や拡張を求める場合は runc の挙動を理解する
・トラブル時は責任範囲を分けて原因を絞る
・CI/CD での再起動挙動を安定化させる設定を検討する
・監視とロギングの連携を強化する
ねえ、containerd の話をしていたとき、友達がこう言ったんだ。『containerd は指揮者、runc は演奏者』だと。つまり指揮者がどう動くかを決めると、演奏者が正しく動く。実務でこれを思い出すと、トラブル時に『誰が原因を決めるのか』がすぐ分かる。例えば、リソース制限が効かないとき、まずは指揮者の設定を疑い、次に実行エンジンの挙動を観察する――そんな順序で問題解決を進めれば、難解なエラーも整理しやすい。日常の学習にも、こうした“役割の分担”の視点を取り入れると、機能の理解が深まる。
次の記事: kindとniceの違いを正しく使い分けるコツと例文集 »





















