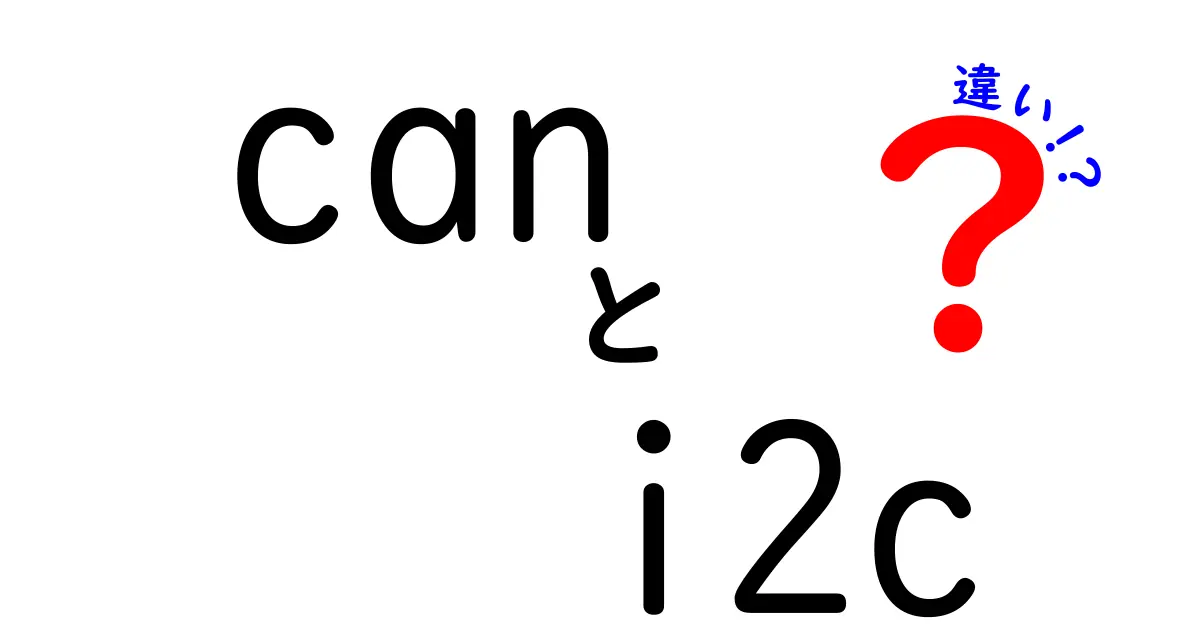

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CANとI2Cの基本を押さえよう
CANとは車載ネットワークや産業機器でよく使われる長距離のシリアル通信規格です。差動信号と呼ばれる2本の線でデータを送るため、ノイズに強く距離が長くても安定します。I2Cとは対照的に、2本の線だけの近距離用データ伝送を前提とした周辺機器の接続規格です。I2Cは主にマスターと複数のスレーブが共用ラインでやり取りします。CANは通常多点通信を前提としたバス型構造で、車のブレーキECUやエンジンコントロールなどの信頼性が重要な場面で活躍します。一方I2Cはセンサーや温度計、RTCなどの周辺機器を少数でつなぐのに向いています。
仕組みの違いだけでなく現場の使い方も大きく異なり、距離とノイズ耐性が求められるならCAN、回路のシンプルさとコスト削減が優先されるならI2Cを選ぶのが基本です。ここからは具体的な違いを、技術的な細部に踏み込みすぎず、日常の例えを使って見ていきます。
次の表と段落で、ポイントを整理します。
仕組みと用途の違いをひとつずつ比べてみよう
CANの仕組みは主に差動信号による長距離伝送と、ノイズに強い設計思想です。複数ノードが同じバスに接続される構造による多点通信、そしてエラーハンドリングを含む信頼性の高い設計が特徴です。I2Cはマスターと複数のスレーブの対話を前提に、アドレスで機器を識別します。速度はCANが1Mbps程度を標準とすることが多く、長距離・高信頼性の場面に適しています。一方I2Cは標準で100kHz、Fastモードで400kHz、最近では3.4MHz級の高速モードも登場していますが、距離が短くノイズの影響を受けやすい環境では信号の設計が難しくなる場合があります。 表の情報をもとに自分の回路や製品の条件を思い浮かべ、どちらを選ぶべきか判断しましょう。 この知識があれば、学校の課題や趣味の回路作りでも「どういう場面でどちらを使うべきか」を自分で判断できるようになります。次のセクションでは、現場での使い分けのコツを、より現実的な視点で見ていきます。 ある日の授業中、I2Cの話題を友達と深掘りしていた。私はI2Cを『2本の線だけで動く小さな王道システム』みたいだと説明した。マスターがすべてを指示して、スレーブは住所で応える仕組み。距離が短く、配線が少ない分、コストも回路の複雑さも抑えられる。けれど長距離やノイズの多い環境になると I2C は苦しくなる。そこでCANの登場だ。CANは差動信号という強い武装で長距離を安全に走れる。私は友達に『用途次第で使い分けるのが最適解だよ』と伝え、2つの規格の現場での使い分けのコツを一緒に考えた。こうした話を通して、教科書の定義だけでは見えない“現場の判断基準”を身につけることができた。
このように両者は設計思想が異なり、選択は用途と環境に大きく左右されます。以下の表で、主要な違いを見やすく整理します。特徴 CAN I2C 信号の種類 差動信号 単一信号でデータとクロックを伝える トポロジ バス型 マルチマスター型のバス 通信速度 一般的に1 Mbps稼働が多い 標準100kHz、Fast 400kHz、場合により1MHz以上 用途 自動車・産業機器の長距離通信 マイコン周辺機器・センサーネットワーク 利点 ノイズ耐性が高く長距離向き 構成が簡易で低コスト 欠点 実装が複雑で設計難易度が高い 距離が短くノイズ対策が必要になることがある
読者の疑問としてよくあるのは、距離や回路の難易度だけでなく実際の部品選定やエラー対策の話です。これらを踏まえると、CANとI2Cの違いは単なる仕様の違いだけでなく、設計者の「現実にどう機能させるか」という考え方の違いにもつながります。
最後に、実務で役立つ判断材料をまとめた表をもう一度確認しておきましょう。
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事





















