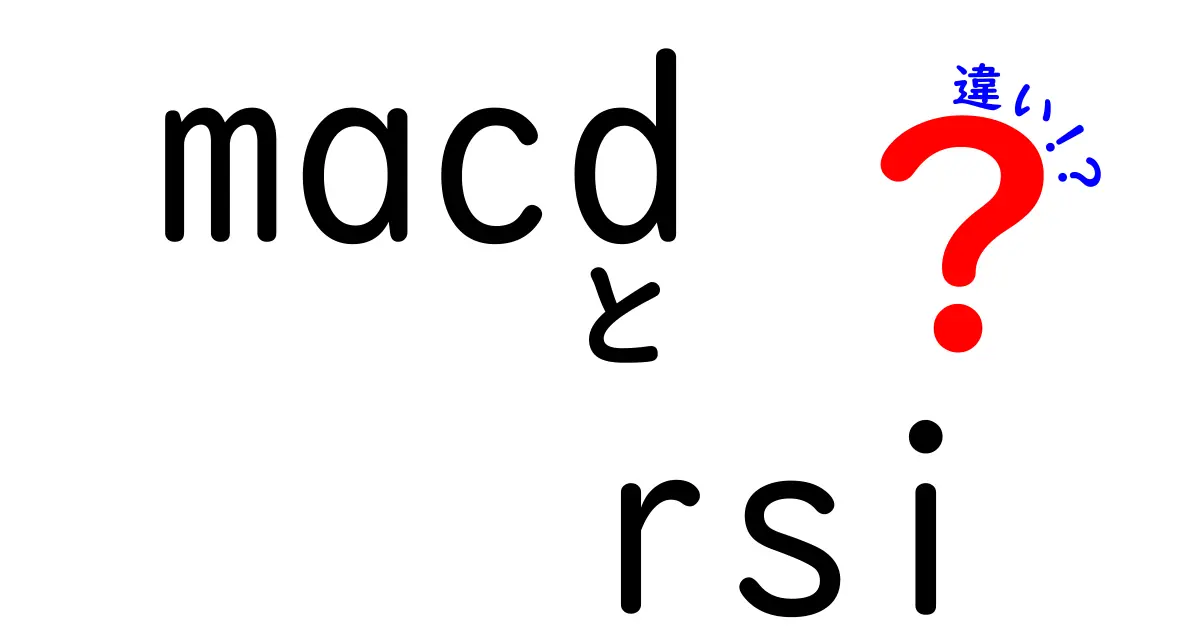

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
MACDとRSIの違いを徹底解説!初心者にも分かる投資指標の見分け方
MACDとRSIは株式や仮想通貨の投資でよく使われる指標です。どちらも「買い時/売り時」を判断するのに役立ちますが、性格がちがいます。まずMACDはトレンドの方向性と勢いを同時に見る指標であり、二つの平滑移動平均の差を用います。この差をさらに平滑化して線として表示するのがMACD線です。さらにそのMACD線と信号線の交差を売買のシグナルとして解釈します。ゼロラインを越えるか否かも筋の強さを示します。RSIは別の考え方で、株価が「上がりやすいか下がりやすいか」を相対的に判断する力を持ちます。過去一定期間の上昇日と下落日を比較して相対的な強さを数値化し0から100の範囲に収めます。高すぎると買われすぎ、低すぎると売られ過ぎと判断されます。これらの違いを理解するとき、二つを組み合わせて使うのが効果的です。
例えば強いトレンドが続く場面ではMACDが有効で、トレンドの初動を捕まえるのに向いています。逆にレンジ相場ではRSIのオーバーソル・オーバーボードの水準で反転の兆候を読み取りやすいことがあります。
これらのポイントを押さえるだけで、初めての人でも「何を見てどう判断するのか」がぐっと明確になります。この2つの指標を正しく理解することが、投資判断の精度を高める第一歩です。
MACDとは何か
MACDはMoving Average Convergence Divergence の略で、英語名そのままの指標です。計算の基本は短期のEMAと長期のEMAの差を取り、それをさらに9日間のEMAで平滑化してMACD線を作ります。一般にはMACD線とシグナル線の交差を売買のシグナルとして解釈します。MACDのヒストグラムはMACD線とシグナル線の差を棒グラフで表示するもので、勢いの変化を視覚的にとらえやすくします。
この指標の特徴は「トレンドの方向と勢いを同時に把握できる」点にあります。短期線が長期線を上回ると買いのサインが出やすく、下回ると売りのサインが出やすいです。さらにゼロラインを越える瞬間にも意味があり、ゼロを越えるとトレンドの転換を示唆することがあります。
初心者がつまずきやすいのは「どのEMAを使うか」「どの期間を選ぶべきか」です。実践ではデフォルトの12日と26日、9日を基準に始める人が多いですが、銘柄や相場環境によって最適な設定は変わります。設定を変えると信号の遅延や早さが変化しますが、目的は一貫して「トレンドの強さと転換のサインを読み解くこと」です。
RSIとは何か
RSIはRelative Strength Index の略で、過去一定期間の価格の上げ幅と下げ幅を比較して相対的な強さを数値化します。算出方法は期間中の上昇日平均値と下落日平均値を使い、0から100の範囲に収まるように正規化します。一般には70以上を「買われすぎ」、30以下を「売られすぎ」と解釈して、反転の可能性を探ります。
RSIはトレンドの方向だけでなく反転ポイントにも敏感で、ダイバージェンスと呼ばれる価格の高値更新とRSIのピークの不一致を手掛かりに売買判断を補完します。反面、強いトレンドが続くとRSIが高止まりしてしまい「遅れて反応する」ことがあります。そうしたときは別の指標と組み合わせて使うのがよいとされています。
このように RSI は「相対的な力のバランス」を見抜く力に優れており、レンジ相場や逆張りのヒントを探す場面で特に力を発揮します。
MACDとRSIの違いと使い分け
この節では二つの指標がどう違い、どう使い分けるのが有効かを比べます。根本的な違いはMACDが「トレンドの方向と勢いを同時に捉える指標」であるのに対し、RSIは「現在の価格の力関係を数値化して過熱感や反転の可能性を探る指標」である点です。
具体的な使い分けのコツとしては、トレンドが明確な局面ではMACDのクロスを優先してエントリーを検討します。レンジ相場や反転を狙う場面ではRSIのオーバーボート/オーバーソルの水準とダイバージェンスを確認します。
表で要点を整理すると以下のようになります。指標 主な目的 得意な相場 反応の速さ MACD トレンドの方向と勢い トレンド相場 中〜遅め RSI 買われ過ぎ/売られ過ぎの判断 レンジ相場や反転局面 速い
これらを組み合わせると、エントリーポイントの信頼性が高まります。
ただし、いずれも完璧な予測手段ではなく、取引ルールと資金管理をセットで使うことが大切です。
今日は友達とふだんの部活後に MACDと RSI の話題を雑談風に深掘りしてみた。 RSI は相場の力関係を数値化して過熱感を教える友だち思いの指標だと説明したが、実際は「上がりやすいかどうか」を相対的に判断してくれる。私は RSI の70や30のラインを目安にすることが多いが、それだけに頼ると騙されることもある。そこで私はMACDと組み合わせる利点を紹介した。MACDはトレンドの方向と勢いを同時に示してくれるので、相場が上昇トレンドか下降トレンドかを把握する手助けになる。二つを同時に見れば、信号の遅延を減らしエントリーポイントの判断を安定させられることが多い。具体的にはレンジ相場では RSI の反転やオーバーソルのサインを先に確認し、トレンドが強くなるときには MACD のクロスを待つのが私たちの基本ルールだ。もちろん市場は生き物なので、過去のパターンが必ず通じるとは限らない。だから資金管理と自分のルールを最優先に、指標は道具として活用するのが大切だと再認識した。





















