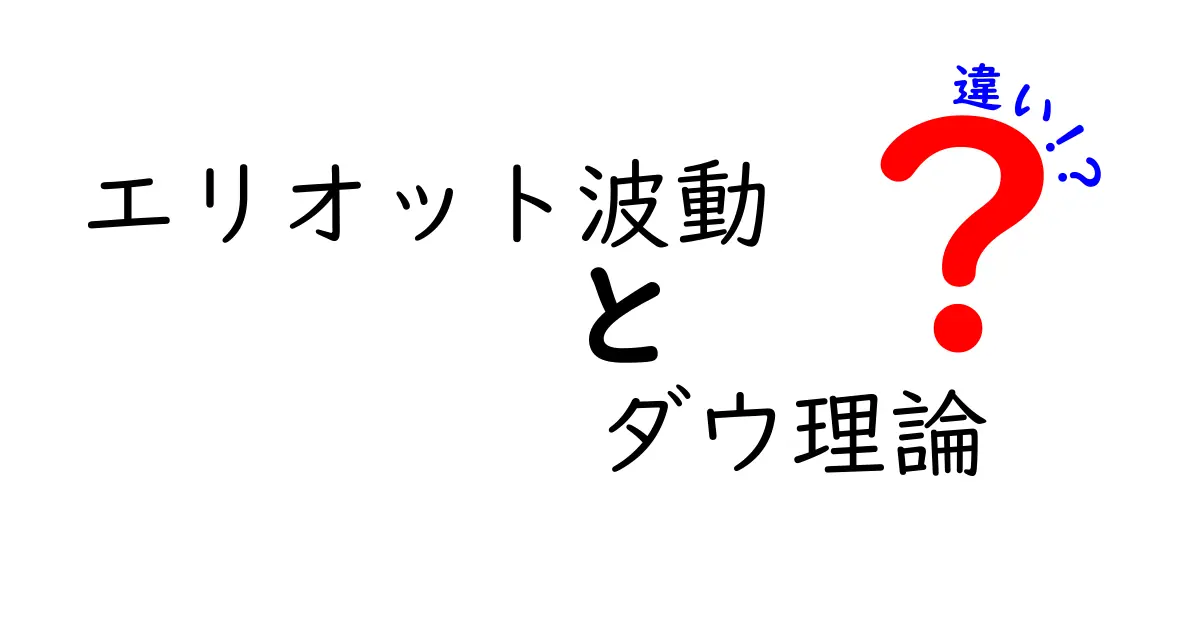

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
エリオット波動とダウ理論の基本概念の違い
エリオット波動とダウ理論は、どちらも株式市場の動きを説明しようとする「理論系」の考え方です。エリオット波動は価格の動きを「波」という形で捉え、5波の上昇のあとに3波の下降が繰り返されると考えます。数えることが重要ですが、波の数え方には主観が入りやすく、経験や判断力が影響します。
一方、ダウ理論は市場全体の動きを中心に見て、株価は主要なトレンドに沿って動くと考えます。ダウ理論は「平均の動きは全体の経済状況を反映する」「市場は強気トレンド・弱気トレンド・横ばいの三段階の動きを経由する」など、比較的シンプルな原理を使います。
この二つの違いを端的に言うと、エリオットは「局所的な波のパターンと心理の流れ」を重視し、ダウ理論は「全体の動きと長い時間の流れ」を重視します。エリオットは波の中の小さな動きを分析することで短期の動きを見抜くことを目指すことが多く、ダウ理論は長期の流れを見て大局を判断することが多いのです。
ただし、どちらの理論も「完璧な予測法」ではなく、相場の性質として「確率論的に動く」という点を理解して使う必要があります。主観と検証のバランスが重要で、経験を積むほど解釈が安定してくる関係があります。
実践での使い方の違いと適用場面
実践の場面で考えると、エリオット波動は短期〜中期のトレードで使われることが多く、数え方の指針をもとに「次に来る波はどの方向か」を推測します。波動の塊がどの段階にあるかを読み取り、そこからポジションの入り時期を検討します。波動のカウントは人によって解釈が変わりやすい点が難点ですが、複数の時間足を重ねて確認することで精度を高める工夫が行われます。
ダウ理論は長期の視点で用いられることが多く、主要なトレンドが発生してからのエントリー・エグジットを検討します。たとえば、株価が新しい高値を更新し続けるなら上昇トレンドが継続中と判断し、反対に高値が切り下がる局面では下降トレンドの可能性を意識します。ダウ理論は市場全体の方向性を大きく見て、複数の市場指標の確認を重視します。
このように、エリオット波動は「波のパターンと心理の連続性」を手掛かりに短期の判断を、ダウ理論は「全体の動きと長期の流れ」を手掛かりに長期の判断をする、というのが特徴です。
実務ではこの二つを組み合わせるトレーダーもいます。具体的には、ダウ理論でまず長期の方向性を決め、エリオット波動で短期の入場タイミングを探る方法です。これにより「大きな流れはこう、細かな動きはこう」という二つの視点を同時に持つことができます。
とはいえ、どちらの理論も完ぺきではありません。相場にはニュースやイベント、投資家心理の影響が強く、波は崩れやすいのです。リスク管理と柔軟な判断を忘れず、バックテストやデモ口座で試してから実戦に臨みましょう。
似ている点と混同しやすいポイント
エリオット波動とダウ理論は、どちらも「市場は何かしらのリズムで動く」という発想に根差しています。どちらもトレンドの存在を前提にしている点や、反転のサインを探すことが共通しています。しかし、何を根拠にサインを探すかには大きな違いがあります。
エリオット波動は波の形と階層を数えることで「次に来る動き」を想定します。階層が深くなるほど、長期の展望と短期の動きを結びつける作業が増え、判断が複雑化します。ダウ理論は市場の分割された指標を横断して比較する方式を取り、転換点は複数の市場で同時に確認されることが多いとされます。
混同しやすい点としては、いずれも「トレンドを見抜く手掛かりを探す」という点と、「過去の動きが未来へ影響を与える」という信念を共有していることです。実践では、エリオット波動のカウントが乱れたと感じても、ダウ理論の長期の方向性を見直すことで、見落としを減らすのに役立つ場合があります。
最後に覚えておきたいのは、これらの理論は道具であって、予測の唯一の方法ではないということです。自分の判断力を育て、複数の視点を組み合わせる練習を続けることが、長く安定して市場と向き合うコツになります。
友達との雑談風にダウ理論を深掘りする。友人が『ダウ理論って結局、どういう意味なの?』と尋ねる。私は『ダウ理論は市場が大きな方向性を持って動くという考え方だよ』と答える。『長期のトレンドと短期の反転をどう結びつけるの?』と聞かれ、私は『一次トレンドが出てくると、それに対する二次・三次の動きが現れると考える。ニュースが出ても、全体の流れが崩れない限りはトレンドが続くことが多い』と説明する。さらに『ダウ理論は複数の市場指標の一致を重視する』と補足する。私たちは実際の株価チャートを見ながら、長期の上昇局面で金額が増えると同時に、短期の調整で一時的に下がる場面をどう扱うかを話し合う。結局、ダウ理論は「市場全体の体温計のようなもの」だと感じ、日常の生活のリズムにも似た部分があると感じた。
前の記事: « 担保と証拠金の違いを徹底比較|資金を守る基本と使い分けのコツ





















