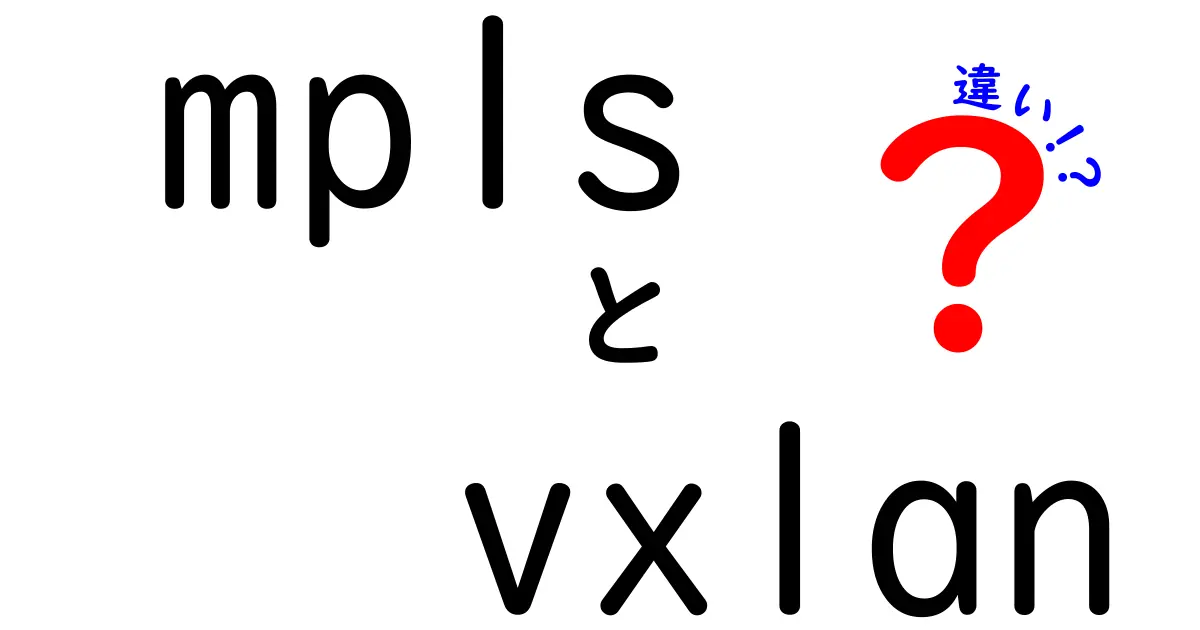

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
MPLSとVXLANの違いを解説します:初心者にも分かる基礎ガイド
この二つの技術はデータをどのように運ぶかを決める仕組みです。MPLSは長い距離を安定して走るバス路線のように、データにラベルという名札を付けて次の目的地へ直接届けます。VXLANは仮想化されたネットワークの世界で新しい部屋をどんどん作る力を持つトンネルのような存在です。両者は目的や動かし方が少し違いますが、現場では別々に使われることが多く、それぞれの強みを理解することが大切です。MPLSが得意とするのは "広域の安定性と品質保証" 、VXLANが得意とするのは "データセンター内の柔軟な仮想ネットワークの拡張性" です。子どもに例えるなら、MPLSは長距離の観光バス、VXLANは遊園地の新しいアトラクションのようなイメージです。
この説明だけでも、二つが同じ目的(データを届けること)を持ちながら、現場の課題に合わせて使い分けられていることが伝わります。
MPLSの仕組みは「ラベル」と呼ばれる短い識別子を使ってパケットの届け先を決めます。ルータはパケットの中身を詳しく見ずに、ラベルを見て次のノードへ導きます。これにより、複雑な経路計算を軽くして転送速度を安定させる効果があります。MPLSは コントロールプレーンとデータプレーンの分離 を前提とし、品質保証の機能や優先制御を組み込みやすい点が魅力です。一方VXLANは仮想マシンのネットワークを自由に拡張するための技術で、物理的なネットワークの上に仮想のネットワークを重ねます。VXLANはUDPやIPなどのトンネルを使い、データの転送を「仮想の部屋と通路のセット」で表現します。これにより複数のテナントを同じ物理網の上で安全に分離して動かすことができます。
つまりMPLSは外部接続を安定させるための道具、VXLANは内部の仮想空間を作るための道具、というイメージです。
現場での使い分けを考えるときには、コストや運用の現実を忘れないことが大切です。例えば広域に複数拠点を結ぶ場合はMPLSの導入や運用の実績があるベンダーの方が安心感があります。逆にデータセンター内で多くの仮想機能を動かす必要があるときはVXLANの方が柔軟性を発揮します。さらに近年はVXLANの制御 plane の手段としてEVPNとセットで使われることが多く、これが進むとMACアドレスの管理がスムーズになり、仮想マシンの移動にも強くなります。表を使って特徴を整理すると理解が深まります。以下は簡易比較表です。
結論として、MPLSとVXLANはそれぞれ得意分野が異なるため、使い分けは「何を作りたいか」 「拠点の数と規模」 「運用の体制」で決まります。現場では両方を組み合わせるケースも多く、設計時には将来の拡張性と運用負荷のバランスを意識しましょう。
なぜこの二つを組み合わせると強いのか
組み合わせの考え方は、外部の通信を安定させつつ内部の仮想化を自由に管理したいという現場の要望から生まれました。MPLSは広域の接続性と信頼性を提供し、VXLANはデータセンター内のテナント間の分離と拡張性を実現します。実務では、WANをMPLSで確保し、DC内をVXLANで仮想化する構成がよく見られます。こうすることで、拠点間の通信は確実に伝わりつつ、各部門が自分の仮想ネットワークを安全に作れます。
また、EVPNを使うことでVXLANとMPLSを組み合わせたときの運用が楽になります。EVPNはMACアドレスの情報を分散して管理する仕組みで、仮想マシンの移動や拡張が起きても接続が崩れにくくなります。つまり現場では、安定性と柔軟性の両方を同時に手に入れることが可能になるのです。技術の理解を深めると、設計時の迷いも減り、将来の変更にも強いネットワークを作ることができます。
最後に、選択のポイントを再確認します。まず自社のネットワークがどの程度の規模か、どれくらいの拠点を結ぶのかを把握します。次に運用者の技術レベルと学習コストを評価します。さらに将来的な拡張性とコストのバランスを検討します。これらを満たす選択肢として、MPLSとVXLANは互いに補完し合う関係にあると理解すると、設計がスムーズになります。
放課後の雑談で友達とネットワークの話をしていたとき、MPLSとVXLANの違いをどう説明するかで盛り上がりました。私はこう例えました。MPLSは広い道を走る信頼のバス路線、目的地までの経路があらかじめ決まっているので混雑が起きにくいという強みがあります。一方VXLANはデータセンターの中で部屋をどんどん増やせる“仮想の部屋作り”の仕組み。仮想マシン同士を多様なグループに分け、互いの影響を抑えつつ新しいサービスを追加できるのが魅力です。二つを組み合わせれば、拠点間の安定した通信とデータセンター内の柔軟な仮想化を同時に実現できるのです。授業ノートにもこの比喩を描けば、友達にも理解が深まると私は思いました。





















