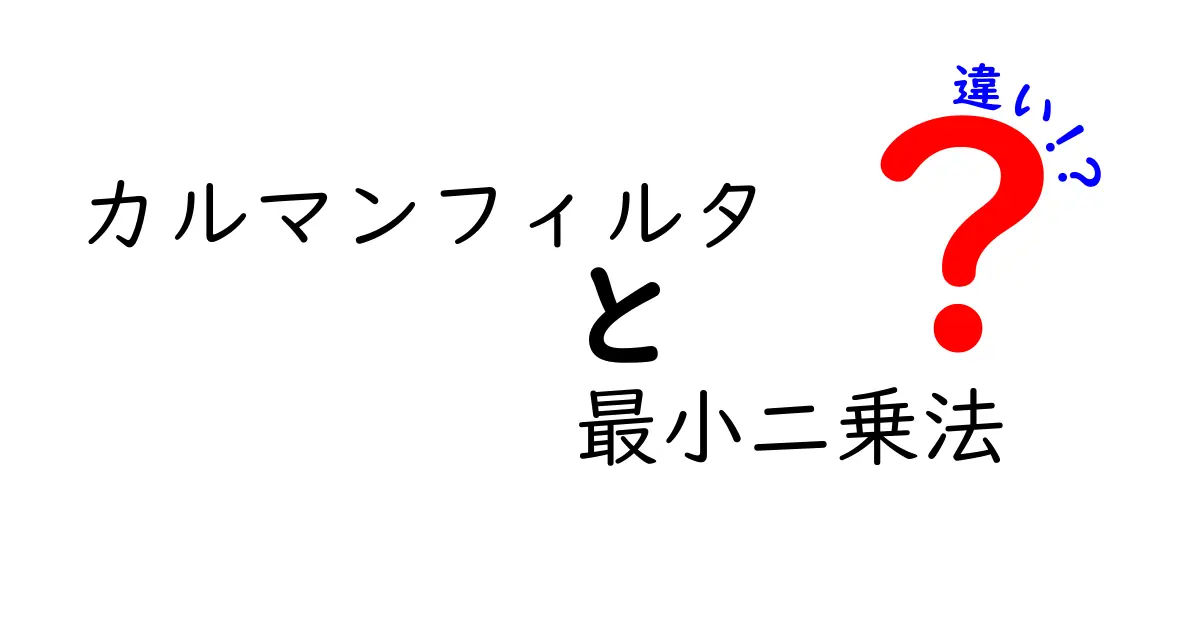

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カルマンフィルタと最小二乗法の違いをわかりやすく解説:データ処理の基本を押さえる
はじめに:なぜこの二つが混同されやすいのか
私たちはデータを使って「未知の状態」を推定する作業を日常や学校の実験で繰り返します。
カルマンフィルタと最小二乗法は、どちらも誤差を減らして正しい答えに近づけるという点は同じですが、どの場面で使うか、どう推定するかという基本設計が大きく異なります。
カルマンフィルタは「時間とともに変化する状態」を想定し、次の瞬間の状況を予測してから観測データで修正します。
最小二乗法は「過去のデータ全体を使って1つのモデルを決定する」方法で、時間的連続性を前提とせずデータ全体を一度に扱います。
この違いは計算量やデータの性質、ノイズの扱い方、解釈のしやすさに直結します。
この章では双方の共通点と相違点を丁寧に整理し、どちらを選ぶべきか判断するための指針を提案します。
カルマンフィルタとは何か:逐次推定と確率的な考え方
カルマンフィルタは線形ダイナミックシステムの最適推定器として知られ、状態xkと観測zkをモデル化します。
モデルは一般に xk = A xk−1 + w k、zk = H xk + v k の形で表され、w k と v k はガウスノイズと仮定されます。
予測ステップでは前の状態から次の状態を推定し、観測が入るとその推定を更新します。
このとき確率分布を用いて不確実性を表現します。
結果として、カルマンフィルタは“今あるデータだけ”で次の推定を出す能力があり、連続的なデータ処理に向いています。
重要な点として、カルマンフィルタは「線形モデルと正規分布のノイズ」を前提にするときに最適で、これを満たすケースで平均二乗誤差が最小になるよう設計されています。
現実のデータは必ずしも完璧な仮定には合わないので、拡張カルマンフィルタなどの工夫が生まれました。
この特徴は、ロボット工学や航空機の姿勢推定、センサフュージョンなど実務で広く使われる理由の一つです。
最小二乗法とは何か:誤差を最小化する考え方
最小二乗法はデータ全体を対象に、観測値とモデルの予測値の差の二乗和を最小にするパラメータを求める方法です。
例えば y = Xβ + ε のような線形モデルでは、βを解くときに「X の転置 X」行列を用いて正規方程式を作り、解を出します。
この手法は過去のデータから「最も適した回帰線」や回帰モデルを作るのに適していますが、データが連続的に変化する場面には適していない場合があります。
データ全体を一度に処理するバッチ処理であり、外れ値に敏感になることがある点や、ノイズがガウス分布であるという仮定があると解釈が楽になります。
一方で、計算量はデータサイズに依存し、高速化や正則化を組み合わせることで現代的な問題にも対応できます。
日常的な問題設定としては、センサのキャリブレーション、マーケティングの回帰分析、科学実験のフィットなど、多様な場面で活躍します。
両者の違いを整理するポイント
この節では、両者の基本的な違いを「時間軸の扱い」「モデルの前提」「推定の性格」「計算の流れ」の4つの観点で整理します。
時間軸の扱い:カルマンフィルタは逐次更新で、時刻kごとに新しいデータを取り込みながら推定を修正します。最小二乗法は基本的にはデータ全体を一度に見てパラメータを決定するバッチ法です。
前提となるノイズ:カルマンはノイズを正規分布と共分散で扱い、推定の不確実性を確率的に表現します。最小二乗法は外れ値に敏感な場合があり、ロバスト性を確保するには別の手法が必要になることもあります。
推定の性格:カルマンは未知の状態を追跡する「状態推定」寄りで、現在と過去の情報を統合して次を予測します。最小二乗法はモデルのパラメータを決定する「回帰推定」寄りです。
計算の流れと用途:カルマンはリアルタイム性の高いデータ処理に向き、センサ融合法やロボットの制御に適します。最小二乗法はデータが揃うまで待つバッチ処理や回帰分析、統計的モデリングに適します。
最後に、実務では状況に応じてこれらを組み合わせることもあります。例えば、カルマンフィルタの予測モデルを最小二乗法で学習するなど。
実務での使い分けと活用例
実務では、二つの手法を使い分けるだけでなく、互いを補完する形で使われることが多いです。
例えば自動運転車のセンサ融合では、カルマンフィルタを使って現在の状態を連続的に推定しつつ、過去の大量データから得られたモデルを最小二乗法で更新することでモデルの妥当性を保ちます。
また、金融の分野では最小二乗法の回帰モデルを使って市場のトレンドを捉える基礎を作り、カルマンフィルタを使って時系列データのノイズを抑えつつリアルタイムでのステータス推定を行うといった組み合わせが現場で役立ちます。
初学者には、まず最小二乗法の基本を固め、次にカルマンフィルタの思想とアルゴリズムの流れを学ぶ順序を推奨します。
まとめ
本記事では、カルマンフィルタと最小二乗法の違いを中学生にも理解できるように解説しました。
カルマンフィルタは「時系列データを連続的に推定する方法」であり、確率的な考え方で不確実性を扱います。最小二乗法は「データ全体を使ってパラメータを最適化する方法」であり、回帰分析の基本です。
状況に応じて使い分けることで、データのノイズを抑え、現象をより正確に理解できます。
この違いを押さえておくと、研究や実務の現場で適切な手法を選ぶ判断力が高まります。
友達Aと私は放課後にカルマンフィルタと最小二乗法の話をしていた。友達Aは「連続してデータが来るときはカルマン、データが揃ってからモデルを作るときは最小二乗」という言い方をしてくれた。私は「でも現実には両方が役に立つ場面が多いよね」と続けた。話を深めるうちに、カルマンは“今の姿”を狙い、最小二乗法は“過去の傾向”を掴む道具だと分かった。結局、現場ではその場のデータの性質を見て使い分け、時には組み合わせて使うことが最も強力だと感じた。
次の記事: 月次総平均と移動平均の違いを徹底解説|データ読み解きの3ポイント »





















