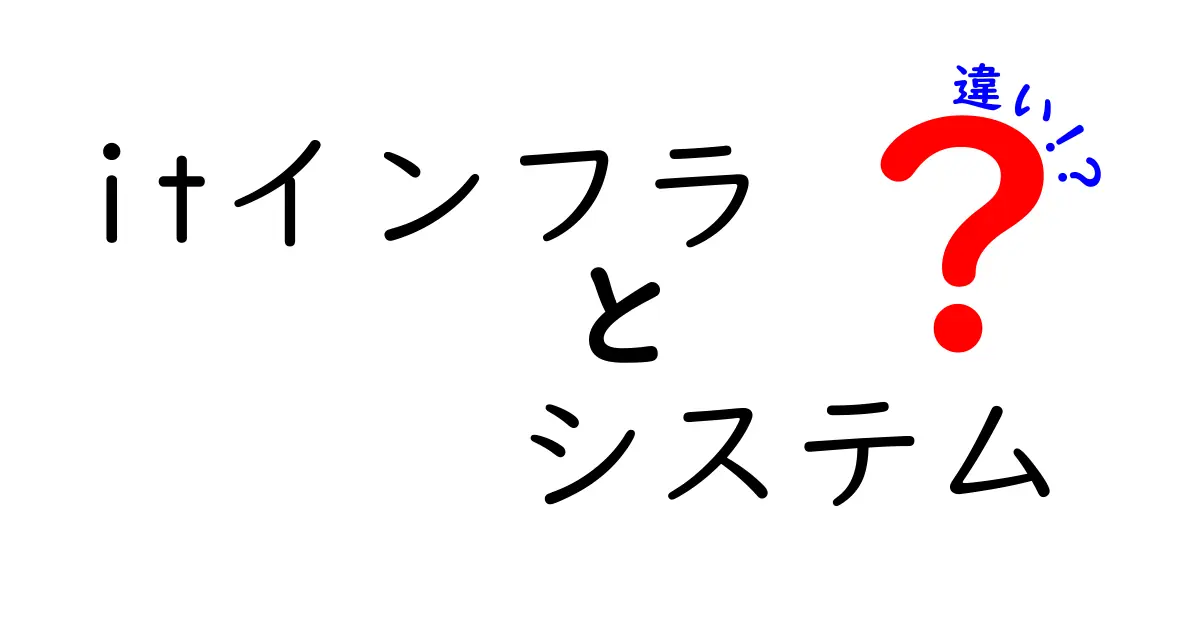

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ITインフラとは何か?基本からわかりやすく解説
まずはITインフラとは何かを理解しましょう。ITインフラとは、コンピューターシステムやネットワークを動かすための土台となる設備や技術のことを言います。たとえば、サーバーやルーター、ケーブル、電源設備、そしてデータを保存するためのハードディスクなどが含まれます。
簡単に言うと、建物で例えると、ITインフラはその建物の「基礎」や「配線」、「水道管」のようなもので、見えない部分でシステムを支えています。
このインフラがしっかりしていないと、システムが正常に動作しなかったり、速度が遅くなったりする可能性があります。だからITインフラは情報技術の基盤としてとても重要です。
システムとは?ITインフラとの関係を理解しよう
次にシステムについて説明します。システムは、特定の目的を達成するために組み合わされたソフトウェアやハードウェア、ユーザーの利用形態などの総称です。
たとえば、会社で使う販売管理システムや会計システムがこれに当たります。これらのシステムは、ITインフラの上に構築されていて、必要なソフトウェアやプログラム、データベースといったものから成り立っています。
つまり、ITインフラが土台となり、その上で動くのがシステムと考えればわかりやすいです。
ITインフラとシステムの違いを表で比較!
なぜ違いを理解することが大事なのか?
ITインフラとシステムがどう違うのかを理解することは、仕事を円滑に進めるうえでとても重要です。
多くの人が「システムが動かない」と言った時に、それはインフラの問題の場合もあれば、ソフトウェア自体の問題の場合もあります。どっちが原因かをきちんと理解することで、トラブルを素早く解決できます。
例えば、ネットワークケーブルが抜けている(インフラの問題)ときに、システムの設定をいじっても解決しませんよね。このように、把握しておくと無駄な作業を減らせます。
ITインフラの中でも特に重要なのが「サーバー」です。サーバーとは、データを保存したり、他のコンピューターにサービスを提供するコンピューターのことです。面白いのは、サーバーは24時間365日休まず動き続ける必要があるため、冷却や電源管理がとても重要だということ。まるで巨大な冷蔵庫のように熱を冷やす設備が備わっているところもあります。こうした裏側の配慮のおかげで、私たちはインターネットやクラウドサービスを快適に利用できているんですよ。
前の記事: « 初心者にもわかる!本番環境と開発環境の違いを詳しく解説
次の記事: ライセンス費用と保守費用の違いとは?初心者にもわかりやすく解説! »





















