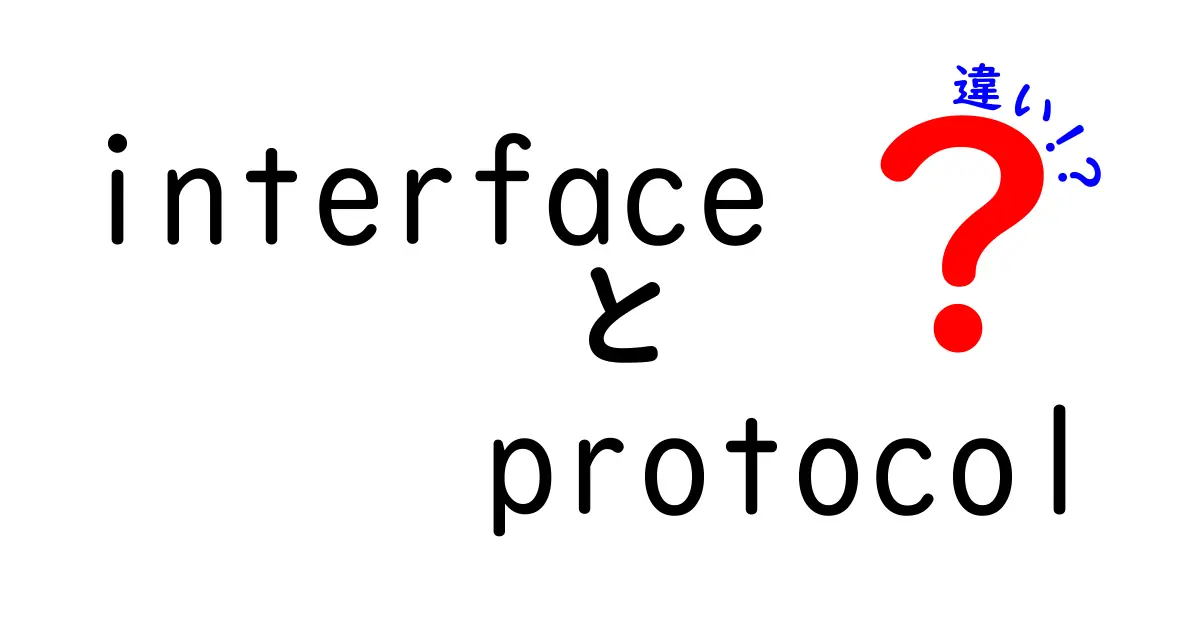

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
interfaceとprotocolの違いをやさしく解く!中学生にもわかるプログラミング入門
はじめに、interfaceとprotocolはどちらも“約束ごと”のような役割を持つ言葉です。日常生活の例で考えると、友だちにお願いごとをするときのルールのようなものです。プログラミングの世界では、interfaceとprotocolは似ている部分と違う部分があり、使う場所や言語によって意味が少し変わります。まず大切な点は、interfaceは“型が満たすべき機能の集合を定義する枠組み”であり、protocolは“ある機能を提供するためのルールそのものを表す枠組み”だということです。言語によってこの役割がどう分かれるかを覚えると、コードの読み書きがぐっと楽になります。例えばJavaやC#ではinterfaceをクラスが実装します。一方SwiftやObjective-Cではprotocolを使って同様の契約を表現します。ここでは、両者の基本的な考え方、使い分けの目安、そして実際の利用例を、中学生にも分かるように段階的に紹介します。
重要なポイントを整理すると、第一にinterfaceは“約束の形”を定義する枠組みであり、第二にprotocolは“約束された動作の集合”を表す枠組みである、という点です。
interfaceとは何か
まずinterfaceとは何かをはっきりさせましょう。interfaceは“この型が必ず提供するべき機能の一覧”を定義するものです。実装クラスはその一覧を満たすために、各メソッドの具体的な処理を実装します。実装のコードが異なっても、同じinterfaceを使うことで外部からは同じ使い方に見えるため、部品の組み換えが容易になります。Javaでの例を思い浮かべると、例えば“動物アクション”というインターフェースを作っておけば、犬や猫はそれを実装します。犬は吠える、猫は鳴くといった個別の処理を持ちながら、外部からは同じ方法で“音を出す”といった操作を呼び出せます。
このようにinterfaceは「約束の形」を決める道具であり、抽象的な設計を現実のコードと結びつける橋渡しの役割を果たします。注意点としては、interfaceそのものにはデータの状態を持たせません。実装は別の場所に任せ、機能の名前とシグネチャだけを定義するのが基本です。プログラム全体の設計をきれいに保つには、interfaceと実装を分ける考え方がとても役に立ちます。
protocolとは何か
一方でprotocolは“この部が満たすべき動作の約束そのもの”を表します。Swiftの世界では、プロトコルはクラス、構造体、列挙型といったさまざまな型に適用でき、これらの型がどんな機能を提供するかを決める役割を持ちます。プロトコルを採用することで、違う型どうしでも同じ操作を行えるという利点があります。実際には、Swiftではプロトコルを宣言して、関数の名前と引数の型、返り値の型を決めます。実装側はそのプロトコルに適合するようにメソッドを定義します。クラスがこのプロトコルに適合するとき、プロトコルで定義された全ての機能を実装する義務があります。これを満たすと、その型は「プロトコルに準拠している」と呼ばれ、別の型と同じ操作を安心して結びつけることができます。プロトコルの強さは拡張機能にも現れ、プロトコルの拡張を使えばデフォルトの実装を提供でき、コードの重複を減らすことができます。
つまりprotocolは「動作の契約」を表し、強力な抽象化の道具として働きます。
以上を踏まえて、どちらを使うべきかの判断材料は「あなたが守らせたい約束の性質」と「言語が提供する仕組み」です。
今日は interfaceという言葉について友だちと雑談するみたいな口調で深掘りします。最初は“interfaceって結局何者?”という疑問から入り、クラスがその約束をどう守るのか、そしてSwiftやJavaでの使い分けの微妙なラインを、身近な例で説明します。たとえば学校の部活動での規則を想像してください。規則は誰が何をして良いかを決めていますが、実際の運用は人それぞれです。interfaceは外見上の約束を作る箱であり、内部の動作は別の人が作る。これを理解するとコードの連携や保守がラクになります。





















