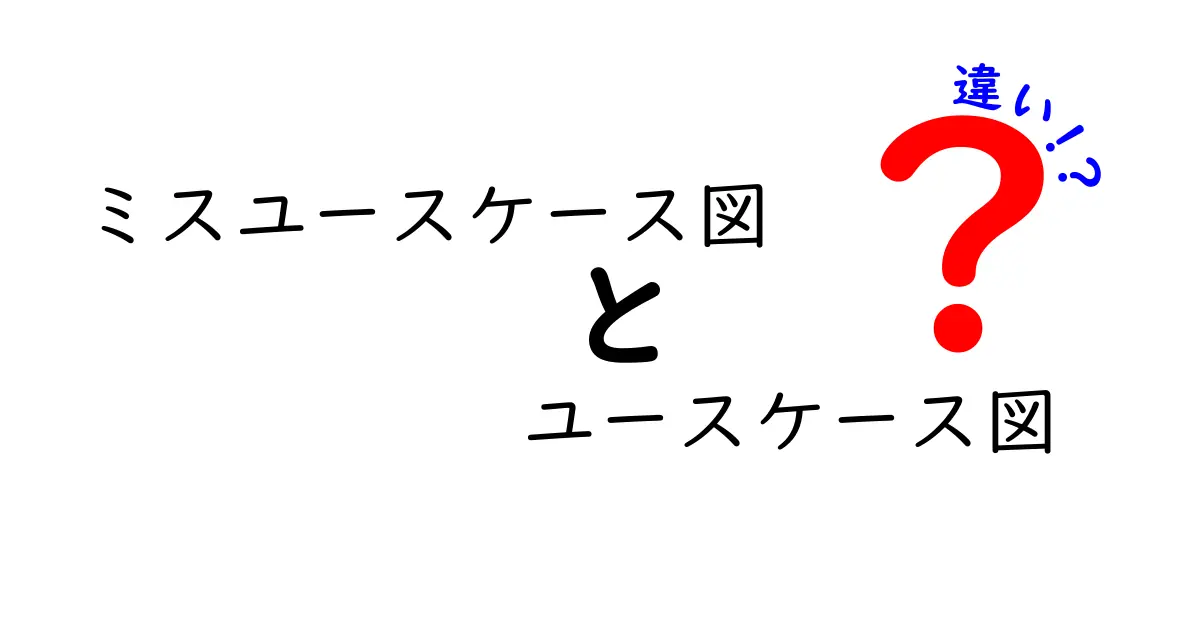

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ミスユースケース図とユースケース図の違いを正しく理解するための完全ガイド
ここでは、ユースケース図とミスユースケース図の違いについて、初心者にも分かるように詳しく解説します。
まず前提として、ユースケース図はシステムが提供する機能を、外部の人(アクター)がどのように使うかを描く図です。楕円形の「ユースケース」と、アクターを結ぶ関係線で構成され、システムの振る舞いを高いレベルで把握するのに適しています。対してミスユースケース図(Misuse Case Diagram)は、セキュリティの観点で「もしこういう不正利用が起きたら」という脅威シナリオを描く図です。
この図は、正規の機能を描くユースケース図と並べて、どの攻撃を想定して防御すべきかを明確化するために使われることが多いです。
つまり、二つの図は目的・焦点が異なり、混同すると設計の品質が落ちます。ここからは、それぞれの要素と描き方、そして現場での使い分け方を順を追って見ていきます。
ユースケース図の要素を整理すると、まず「システム境界」があります。これは図の枠組みで、外部の利用者と内部の機能を分けるための線や箱で示します。次に「アクター」と「ユースケース」です。アクターは人や別のシステムなど、ユースケースは実際に達成したい機能や目的を指します。関係としては、include・extend・generalizationなどがあり、機能の再利用や条件付きの振る舞いを表します。これらを整理して描くと、最終的に誰が何をするのかが一目で分かります。
ミスユースケース図は少し構造が変わります。ミスケース(脅威ケース)と呼ばれる不正利用の候補を描くことで、セキュリティ対策の検討材料を明確にします。アクターとして“攻撃者”を置き、ミスケースと正ケースを関連づけてどの組み合わせが弱点になるのかを可視化します。ここで大切なのは、正規のユースケース図と混同しないことです。ミスケースは「不正利用の可能性を見つけるための補助的なツール」であり、現実の設計を歪めるものではありません。実務では、両方の図を並べて検討することで、機能とセキュリティのバランスを取ることができます。
ただしミスユースケース図を作る際の落とし穴もあり、攻撃の表現が強くなりすぎて過度に不安を煽る描き方をしてしまうと、判断を誤る原因になります。適切には「どのような攻撃が考えられるか」を、事実に基づく具体的なシナリオとして描くことが重要です。
実務での使い分けのコツとしては、まず要件定義の段階でユースケース図を描き、次にセキュリティや法的要件が強い領域についてミスユースケース図を併用する方法が有効です。両図の役割を分けて考えることで、設計の透明性が高まり、チーム全体で誤解なく理解できます。図の作成手順としては、1)システム境界を決定、2)主なユースケースを洗い出す、3)アクターとユースケースの関係を線で結ぶ、4)必要に応じてinclude/extendを追加する、5)ミスケースを追加して安全性の観点を評価する、の順に進めるとよいでしょう。
また、実務ではツール上での表現だけでなく、要件定義書やセキュリティ要件仕様書とセットで管理することが重要です。ここでは、日常の設計現場で使える簡単な差分チェックリストもご紹介します。
結論として、ユースケース図は「何を実現するのか」を明確にする道具であり、ミスユースケース図は「何を狙われる可能性があるのか」を事前に探り、防御を設計する道具です。どちらを使うべきかは、プロジェクトの性質とリスク認識の程度によって決まります。日常のソフトウェア開発では、ユースケース図を基本として描き、その上にセキュリティの観点を補助的に追加する形が理想的です。所々に現れる注意点として、「用語の混同を避けること」「境界を明確にすること」「実際の運用を想定した具体性を持たせること」が挙げられます。以上を実践すると、設計資料の理解度が大きく高まり、後の仕様変更にも強い設計を作ることができます。
ねえ、ユースケース図って難しく聞こえるけど実はすごく身近な設計ツールだよ。ユースケース図は“機能を使う人と何をするか”の見取り図で、正しい描き方を覚えると、要件がはっきり見えるようになる。一方でミスユースケース図は、それとは反対の発想、つまり“もし誰かがこう不正利用するかもしれない”という脅威を描く道具。これを使うと、攻撃される前に対策を考えられるのが強み。実際の授業や課題でも、この二つをセットで使うと、機能とセキュリティの両方をバランスよく設計できるようになる。例えばログイン機能を例にとると、ユースケース図は正規の認証フローを描く。一方ミスユースケース図では“不正アクセス”のパターンを別のユースケースとして描く。こんな風に並べて考えると、設計の質がぐんと上がるんだ。私もこの違いを友人と話すときは、まず正規の流れを説明してから、次に脅威の考え方を紹介するようにしている。





















