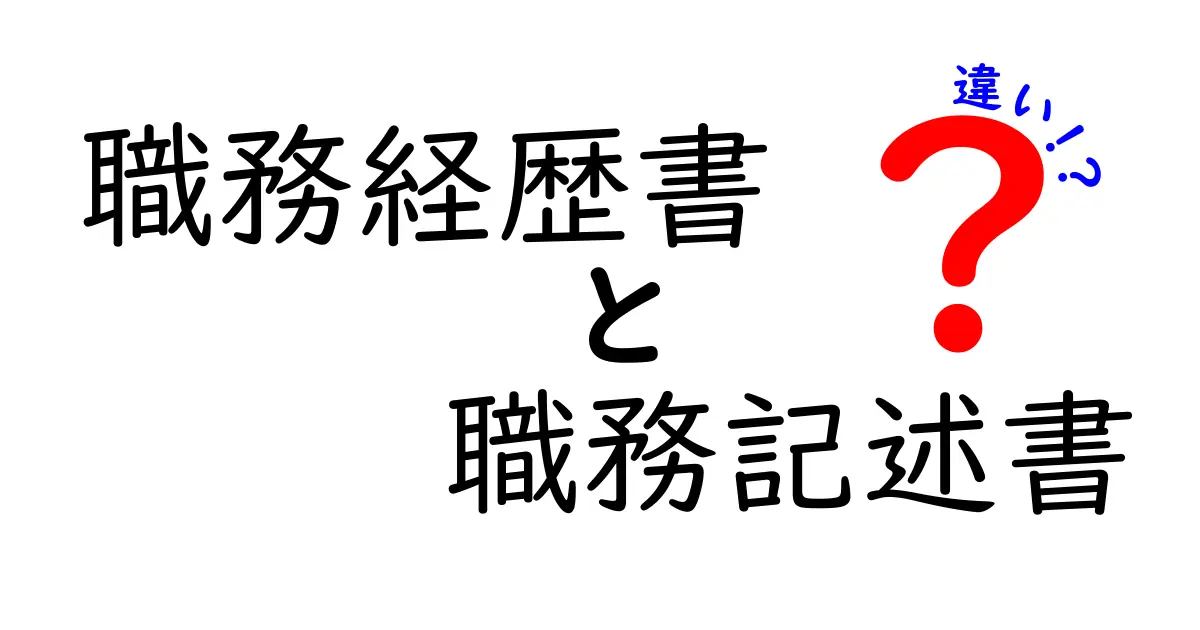

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:職務経歴書と職務記述書の違いを正しく理解する
転職活動を始めるとき、多くの人は履歴書と職務経歴書の違いを混同しがちです。実は「職務経歴書」と「職務記述書」は別物で、それぞれが果たす役割や読まれ方が違います。本記事では、いったいどんな場面でどちらを提出すべきか、どんな情報を盛り込むべきかを、できるだけ平易な言葉で解説します。ここをしっかり理解しておくと、面接官に伝わる自己PRや業務経験の表現が自然と整います。
まずは両者の基本を押さえ、次に実務での使い分けのコツや表現の工夫を見ていきます。私は就活支援の現場で多くの人がこの区別を混同しているのを見てきました。簡単なポイントだけ覚えれば、迷う場面でも適切な書類を選べるようになります。たとえば「応募先が求人票で求める情報の探し方が違う」「部門の専門家が読むときの視点が違う」という点を意識すると、どちらの書類を用意すべきか判断しやすくなります。
なおこの記事は中学生にも分かるよう、難しい専門用語を避け、具体的な例と比喩を用いて説明します。
意味が分からない用語が出てきたら、すぐに私の解説を参照してください。
最初の一歩として、これからご紹介するポイントを頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
職務経歴書と職務記述書の違いを整理する基本フレーム
まず大事な二つの違いを、読者の立場から分けて捉えましょう。職務経歴書は、あなた自身のこれまでの経験を「総合的にまとめた履歴書寄りの文書」です。読み手は人事担当者や課長クラスの人で、応募先が求める要件とあなたの実務のつながりを全体像として把握したいと考えています。
一方で職務記述書は、特定の職務の実務内容と責任範囲を詳しく記述する文書です。チーム内で誰が何を担当していたのか、どの業務をどの程度の規模で行っていたのか、数字で示せる成果とともに具体性を追求します。読者が「この人はこの職務をどう実現してきたのか」を深掘りできる資料と言えるでしょう。
以下の表は、二つの書類の違いを簡潔に比較したものです。表を見れば、どの情報をどちらの文書に載せるべきかがすぐ分かります。
なお、表の情報は実務のケースに合わせてカスタマイズしてください。
このように、二つの文書は読み手と目的が異なるため、同じ話を同じ形で伝えることは難しいです。
次のセクションでは、実務での使い分けのコツを具体的に解説します。
転職活動での使い分けのコツと具体例
まず理解してほしいのは、応募先のニーズを前提に情報を選ぶという視点です。求人票に「〇〇業務の経験が必須」と書かれている場合、職務記述書にはその業務をこなしてきた具体的な内容と成果を詳しく載せるべきです。一方で、複数の職務にまたがる経験や横断的な能力を示す必要がある場合には、職務経歴書の方で全体のストーリーを組み立て、転職の動機や成長過程を一貫して伝えます。
以下のポイントを意識すると、使い分けがスムーズになります。
- 業種・職種別の強調ポイントを変える:IT業界なら技術スキルと成果、営業職なら数字と顧客対応の実績を前面へ。
- 数字で裏付ける具体性を増やす
- 最新の職務内容を反映する
- 面接準備の材料として活用する
最後に、読者の読みやすさを心掛けて、読み手が迷わない順序で情報を配置してください。強調したい点は箇条書きや表の併用で整理すると効果的です。
文章表現は過度に専門用語を使わず、日常語で説明することが理解の近道です。
友だちとの雑談風に深掘りすると、職務経歴書は“成長の棚卸し”みたいなものだと気づきます。過去の経験を並べるだけでなく、どんな課題があり、どう解決し、何を学んだのかをつづると伝わり方が変わります。例えば前職で売上を伸ばしたエピソードを載せるとき、ただ「〜を達成」と書くのではなく、課題の大きさ、取った手段、結果の数値、学んだ教訓を順に書くと、読み手はその人の実務プロセスを想像しやすくなります。書き方を工夫するほど、面接での印象は強まります。





















